教養学部
地域 ラテンアメリカ研究コース
2023.4.15
教養学科 地域文化研究分科
目次
基本情報
| 人数 |
17名 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ2-4割 |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
院進率は学年により差があるが、例年50%前後である。※院進する学生は、東大の総合文化研究科が過半数 |
| 公式サイト |
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/academics/fas/dhss/ask/ https://sites.google.com/site/russiatouou/home |
学科概要
本コースは、9コースある地域文化研究分科の1コースであり、中南米とスペイン・ポルトガルを対象地域とする。(ただしスペイン・ポルトガルを専攻する学生はほとんどおらず(各学年一人前後)、中南米がほとんどである。)進学した学生は、上記地域のいずれかの地域について研究を始める。そして、その地域文化・社会で出会った問題を考察するのに最もふさわしい分野を選び、卒業論文にまとめていく。中南米の開発経済・移民・宗教や文学など、扱う分野は学生によって多種多様であり、アンデス考古学などを扱う学生も多い。
地域文化研究分科の他コースは、イギリス・フランスなど国家単位で編成される一方で、本コースは地域という巨大なまとまりを単位としている。
(参考:9つのコース)
イギリス研究 フランス研究 ドイツ研究 ロシア東欧研究
イタリア地中海研究 北アメリカ研究 ラテンアメリカ研究
アジア・日本研究 韓国朝鮮研究
卒業必要単位は76単位以上であり、卒論が10単位、高度教養科目(※1)が6単位、言語科目が22単位(※2)となる。コース科目が22単位で、卒論関係の「論文指導Ⅰ,Ⅱ」を除き、特にコース必修科目はない。ただし、時間割の都合上とらざるを得ない授業もある。
※1 高度教養科目:後期課程の学生が履修することができる、教養学部内の他学科/コース開講科目。自身の専門分野には直結しないことが多い、学際的内容の概論講義やグループワークが多く、国際研修の一部もこれに該当。前期生でいう「主題科目」に該当し、主題科目と合同開催される例も多いので、前期生が講義にいることも。
※2 言語科目
スペイン語とポルトガル語合わせて18単位(両言語の単位数の比率は決まっていない)、その他同一言語(専門地域の言語)4単位の修得が必須となる。基本的には卒論は日本語で書く人がほとんどだが、スペイン語やポルトガル語で書くこともできる。
留学する学生も一定数おり、日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画(日本とメキシコの政府間で行われているプログラム)を利用してメキシコに留学する学生が多い。スペインだと、マドリード自治大学(東大の全学交換留学の協定校)に留学する学生もいる。
卒論を書き始めるまでは、すべてのセメスターでやることはあまり変わらない。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
・週10~12コマが一般的。
・必修科目はとくにない。(ただし時間割の都合上とらざるを得ないものはある。)
・例年は10月か11月頃に立食パーティのような形で内定者懇親会が開かれる。内定者懇親会には、ネイティブの先生を含む教員、学部の先輩、院生やOBが来る。内定者は自己紹介などを軽く行うが、この時点で興味分野などを細かく聞かれたりはしない。(そもそも興味分野が決まっている人はあまりいない。)
・内定者懇親会(11月)の時点で卒論のテーマを決めている学生はほとんどいない。
・言語の要求レベルは、辞書を使って文学などの文章を読む程度。
3年生Sセメスター
・週10~12コマが一般的。
・言語科目は各セメスターで満遍なく取る人が多い。特定のセメスターでまとめて単位を取りきるような人はあまりいない。
・卒論教員の選択についてはあまりまだ考えない。
3年生Aセメスター
・週10~12コマが一般的。
・単位をいつ取るかを考えている人はあまりいない。
・卒論のテーマを考え始めている人も少しいる。
・3Aまでに卒論以外の単位を取りきる方が多い。
4年生Sセメスター
・「論文指導Ⅰ」という必修科目を履修。
・卒論着手報告会が行われる。
・卒業までの修得単位が足りないと、卒論関係以外の授業を受ける学生もいる。
4年生Aセメスター
・「論文指導Ⅱ」という必修科目を履修。「特殊研究演習Ⅴ」は必修ではない。
・卒論執筆に追われる学生が多い。学科室で作業している4年生が多い。
・卒論の流れ
夏〜秋 卒論中間報告会
秋〜冬 卒論科目届提出
1月まで 卒論提出、卒論審査会
入る前の想像と実際
・「教養学部という名前の通り、対象地域について幅広く、全分野を満遍なく勉強できる。」
・「逆に興味分野がひとつに定まっている人にとっては、それ以外の分野も勉強しなければならないため大変なのではないか。」
・「言語のレベルは高い。前期教養でスペイン語の成績が優秀でも、先輩たちの言語レベルは高く感じる。ただし、スペイン語の授業は来ている学生のレベルに合わせてくれるので、スペイン語に自信がなくても問題ない。前期教養で他言語選択だった人もまれにいる。」
・「学科部屋の資料がとても充実している。」
選んだ理由/迷った学科
・当コースを選んだ理由は、「考古学がやりたいから」「前期教養で受けた授業の先生の雰囲気が好きだったから」「スペイン語の勉強を続けたかったから」「貧困や移民など社会問題、開発経済に興味があるから」など。
・「経済学部と悩んだ。前期教養の経済の授業で少し躓いたことも、教養学部を選んだ一つの理由。」
・「東大に入学したときから当コースを志望していた人はあまりおらず、前期教養を過ごすなかでここに決めたという学生が多い。」
・「文科三類から進学する人がほとんどだが、例年文科二類や理系科類出身の学生もいる。当コースでは理系出身でも困ることは特にない。」
・「地域文化研究分科では、進振り時点で対象地域を選ぶことはせず、内定してから地域を選択する。また、地域コースごとの人数制限はなく、対象地域を選ぶときに進振り点数は関係しない。(必ず希望のコースに行ける)」
コミュニティとしての機能
・コミュニティ機能は強い。
・同期LINEと全学年LINE(院生も入っている)がある。
・コース内の学生同士で一緒にご飯に行ったり遊びに行ったりする。
・受ける授業は一緒であることが多いので、共通の話題は結構多い。また、人数が多いため、気の合う人を見つけやすい。明るくて親しみやすい人やサッカー好きの人が多い。
・卒論の発表会のあとには先生も含めてみんなでご飯に行く。
・学科部屋が存在する。部屋は他コースと比べてやや狭い。例年は、学科部屋で四年生が卒論を書いているが、三年生が四年生に勉強や履修などの面で相談に乗ってもらうこともある。学科部屋で空きコマを過ごす人が多く、そこで一緒に食事をすることも多い。
・地域文化研究分科間の繋がりについては、個人的な繋がりが中心である。他コースの人と何人かで飲みに行ったりすることもある。運動が好きな人が集まるライングループ(他の地域コースも含む)があり、休み時間に集まって駒場の公園でサッカーを楽しんだりすることもある。
授業スタイル
・語学の授業は履修者が少ないこともあり、双方向形式になる。
・レポート課題の授業が殆ど。各自が自身の興味に従って調べ、授業中に複数回報告を行う、などの授業も。
・授業の人数は、少ない時は数名で、ほとんどが中南米科の学生である。ただし国際関係論コースの学生がたまに一人二人参加していることもある。
・他地域の学生との合同授業も少ないながら存在する。
・授業の雰囲気は先生により異なるが、明るい先生の授業は学生が話しやすい雰囲気になっている。ネイティブの先生の授業では言語面で苦労することもあるが、助けてくれる先輩がいれば乗り切れる。
・試験は先生にもよるが、ほぼ無く、レポートが中心である。ほとんどの授業で、セメスター末に3000~4000字のレポートを課される。
研究室・資料
研究室でなにかやる、という形ではない。
学科部屋(研究室)には、教務補佐の方がいて、授業の相談や留学の相談にのってくれる。
特別な制度・その他
・サブメジャープログラム:所属コースの主専攻だけではなく、他コースが提供する15単位程度の科目群を副専攻として履修するプログラム。修了生は卒業時に、卒業証書だけではなく、サブメジャー・プログラム修了証ももらえる。
・学融合型プログラム 学問分野を超えたて横断的な学習を行うプログラム各種
各プログラムのうち、グローバルスタディーズ等は、一部の言語科目と要件科目が被っているので比較的修得しやすい。
上記のどちらのプログラムも多少負担がある。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部

教養学部
「学際性」「国際性」「先進性」を軸に、深い教養を基盤に従来の枠組み・領域を超えて新しい分野を開拓する人材を育成する学部
関連記事

法学部各類
第1類~3類までまとめて説明

A倫理学専修
A群(思想文化_倫理学)

地域 イタリア地中海研究コース
教養学科 地域文化研究分科
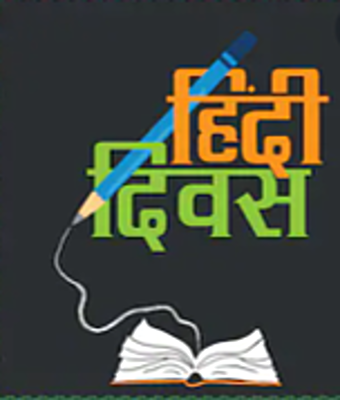
Gインド語インド文学専修
G群(言語文化_インド語インド文学)




