文学部
D西洋史学専修
2023.4.15
D群(歴史文化_西洋史学)
目次
基本情報
| 人数 |
20名程度 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ〜3割程度。学年によってかなり異なる。 |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
大体2割程度が院進する。 |
| 公式サイト |
学科概要
西洋史学専修とは
文学部歴史文化コース所属。進振りの点数は割と低めである。
取得単位数について
単位取得が必要であり、必修が極端に少なく幅広い履修ができるのはこの学科の特徴のひとつだ。特に、3S〜4Aまでは必修は各セメスター週1コマのゼミのみである。2Aでは必修2科目、3S〜4Aまでは各セメスター週1コマのゼミのみが必修である。3Sまでは週15コマ程度履修して、その後の就活や卒論に備える人が多い。
出身科類について
出身科類は様々で、文科三類が多いが、理系出身者も時々いる。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
・週12コマ前後が一般的
・必修について
| 科目 | コマ数 |
|---|---|
| 史学概論 | 週1コマ |
| 西洋史研究入門 | 週1コマ |
・準必修などは特になく、上記二つの必修以外は前期教養の授業や他学科の持ち出し科目で埋める。しかし、史学部の持ち出し科目は全体で日本史学科・東洋史学科のものが1コマずつしかないので、何かとかぶって受けられなくなることがないように2Aのうちに受けておくのが良い。
・2Aは一番暇なタームなので、この時期に旅行に行ったり、自分の趣味を充実させる人も多い。
史学概論
2020年から新しい教授に変更された。ロシア史専門の教授で、時事ネタに基づいた話や自分の旅行談など、雑談が多く面白いと評判である。
西洋史研究入門
西洋史研究の教授方がオムニバス形式で自分の専門分野について入門的な部分を解説する授業。
3年生Sセメスター
・週12〜15コマ程度が一般的
・3S〜4Aまでは、各セメスター週1コマのゼミの授業のみが必修である。その他は比較的自由に選択可能。
3年生Aセメスター
・週15〜16コマ程度が一般的(就活する人は、4Sをあけるために3Aにコマ数を詰める人が多い)
・早い人は就活ががっつりある場合も。冬ごろからはほとんどの就活が始まる。院進する人は卒業論文の文献探しなどをこの時期から進める。
・3S〜4Aまでは、各セメスター週1コマのゼミの授業のみが必修である。その他は比較的自由に選択可能。
4年生Sセメスター
・週2〜4コマ程度が一般的。ほとんど入れない人が多い。就活が本番に差し掛かりかなり忙しい。
・3S〜4Aまでは、各セメスター週1コマのゼミの授業のみが必修である。その他は比較的自由に選択可能。
・サブゼミ(卒論の中間報告をしてコメントもらう授業が毎週一回開催)、4Sの後半くらいから始まる。
4年生Aセメスター
・週1〜3コマ程度が一般的。ほとんど入れない人が多い。取得単位数が足りない人はこの時期に多く履修する必要がある。
・3S〜4Aまでは、各セメスター週1コマのゼミの授業のみが必修である。その他は比較的自由に選択可能。
入る前の想像と実際
入る前は、西洋史学科は専門的であるため、レベルについていけるかなどを不安に思うこともあった。しかし実際に入ってみると、全員が全員学問に真摯に取り組んでいるわけではないし、やる気がない人が予想以上に多くてがっかりしたところも。授業が人数も少なくてゆるい。院生が結構参加しているため、刺激を受けられる。授業後に先生に質問しに行ったりしてる人がいるなど、人数少ないからピアプレッシャーがもらえることもある。
(文三→西洋史学専修)
選んだ理由/迷った学科
西洋史に興味があったから。選択肢として後期教養のドイツ研究と迷って、研究室にアポを取って、お邪魔して話を聞いた。西洋史はそこそこの人数がいて、規模感ありつつコロナ前だと交流も盛んだったため、魅力的に思えた。談話室は本に囲まれた、落書きとかもあるところで、そこに憧れたところもある。
(文三→西洋史学専修)
コミュニティとしての機能
通常であれば、西洋史学研究室の横の談話室でコーヒーを飲みながらの交流が盛んである。だが、コロナ期間でLINEグループはほぼ動かず、slackは存在しないため交流が希薄になってしまった。
授業スタイル
出席を取る科目はほぼなく、テスト中心である。しかし、よっぽどでなければ落とすことはない。
研究室・資料
特別な制度・その他
サブゼミという制度があり、自分の卒論を院生に見てもらってフィードバックを得ることができる。また、教授方も卒論の進行具合などを頻繁的に聞いてくれるなどサポートが手厚い。
地域研究を主体としているため、当該地域に大学院で留学するケースが多いため、留学する人はほぼいない。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
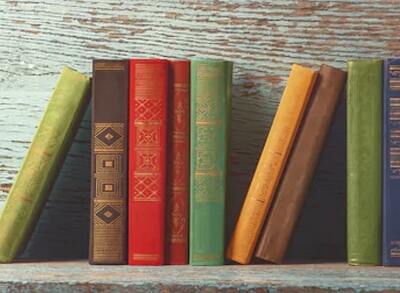
文学部
専門知識や幅広い視野を備え、異なる準拠枠を踏まえ自らの専門を相対化できる、高度な教養人として活躍する若者を育成する学部
関連記事

地域 イギリス研究コース
教養学科 地域文化研究分科

地域 ラテンアメリカ研究コース
教養学科 地域文化研究分科

比較教育社会学コース
総合教育科学専攻 教育社会科学専修

C東洋史学専修
C群(歴史文化_東洋史学)




