教養学部
超域 文化人類学コース
2023.6.30
教養学科 超域文化科学分科
目次
基本情報
| 人数 |
10名前後 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
少人数学科のため、年によって変動しやすい。女性はそこそこいる。 |
| 要求/要望科目 |
・要求科目 ・要望科目 |
| 就活or院進 |
就職:院進=9:1程度 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんなコース?
教養学部教養学科超域文化科学分科に設置されたコースである。そもそも文化人類学とは、様々な社会における日常的な文化的実践をフィールドワーク(現地調査)を通して研究する学問である。その対象は、伝統的社会、部族社会から、現代社会の多くの問題までと幅広い。社会学と似ているが、社会学はマクロかつ定量的な調査を重視するのに対し、文化人類学はインタビューや参与観察を通じて得るミクロかつ定性的な知見を大切にする学問であるといえる。
■卒業要件単位
卒業必要単位は76単位以上であり、卒論が10単位、高度教養科目(※)が6単位、言語科目が2言語以上14単位となる。コース科目が28単位で、「文化人類学基礎論」「フィールド演習」「文化人類学基礎演習」「卒業論文演習」はコース必修。
※ 高度教養科目:後期課程の学生が履修することができる、教養学部内の他学科/コース開講科目。自身の専門分野には直結しないことが多い、学際的内容の概論講義やグループワークが多く、国際研修の一部もこれに該当。前期生でいう「主題科目」に該当し、主題科目と合同開催される例も多いので、前期生が講義にいることも。
■進学定数は?
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 文Ⅰ・Ⅱ(指定科類) | 6 | 2 |
| 文Ⅲ(指定科類) | 13 | 9 |
| 全科類 | 5 | 1 |
・第二段階・第三段階指定平均点
超域文化科学分科では、第二・第三段階のみ通常と異なる方法で平均点が算出される。
超域文化科学分科第二・第三段階指定平均点
=全履修科目の(評点×単位数×重率)の総計÷全履修科目の(単位数×重率)の総計
詳細は、履修の手引き94ページを参照。
■進学前の注意点は?
・2Sには超域文化科学分科全体の説明会とコースごとの説明会があるので、情報収集のためには両方参加するのが良い。
・超域文化科学分科として内定するが各コースには必修があるので、進振りの時点で進学するコースを決めないと2Aの履修を組む際に困る。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■コースに馴染む2A
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 文化人類学基礎論 | 必修 | 火曜5限 |
・週12コマ前後が一般的。
・週一2単位の「文化人類学基礎論」が必修。この授業では主に民族誌(人類学者が長期のフィールドワークの結果を記述した文献)を輪読する。マリノフスキー『西太平洋の遠洋航海者』やレヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』といった古典から、近年登場したマルチスピーシーズ民族誌でも最も広く読まれているアナ・ツィンの『マツタケ』まで。
・選択必修として「文化人類学理論Ⅰ~Ⅲ」「社会人類学理論Ⅰ~Ⅱ」「応用人類学Ⅰ~Ⅱ」「民俗学」がある。演習形式が多いが、ターム開講で人類学の下位区分(経済人類学、開発の人類学など)をひと通り学べる講義形式の授業もある。
・文化人類学の対象範囲が広いため、選択必修では自分の興味に合わせて授業を選べる。
・秋頃、内定生を歓迎する会が開かれる。
3年生Sセメスター
■フィールド演習に取り組む3S
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 文化人類学基礎演習 | 必修 | 火曜2限 |
| フィールド演習 | 必修 | 月曜2限 |
・週10コマ前後が一般的。
・週一2単位の「文化人類学基礎演習」が必修。2Aの必修は民族誌中心だが、こちらの授業は理論寄り。扱う文献としてはレヴィ=ストロース『野生の思考』やギアツの『文化の解釈学』、ラトゥールの『科学がつくられているとき』など。
・新たな必修として週一2単位「フィールド演習」が加わる。自分自身でフィールドを選び、最低8回通いつつ気づいたこと、論点をまとめる。シェアハウスに参与する人、怪しい有機食品店に通う人、ジビエレザーを追う人など様々。
・2Aに引き続き選択必修を取る。
3年生Aセメスター
■民族誌作成と就活に勤しむ3A
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 文化人類学特殊演習(民族誌作成) | 必修 | 木曜3限 |
・週7コマ前後が一般的。
・週一2単位「フィールド演習Ⅱ」が必修。Sセメのフィールドワークを基に12000~20000字の民族誌を作成する。教授によって形式が異なる。授業なしで各自で進め、困ったことがあれば聞くスタイルの年も。
・2A・3Sに引き続き選択必修を取る。
4年生Sセメスター
■卒論準備本格化、4S
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 卒論演習 | 必修 | 木曜2限 |
・週2-3コマが一般的。
・週一2単位「卒業論文演習」が必修。週一で進捗を発表する。
・卒論のテーマ決定は比較的遅く、4Sの頭にはまだ形が定まっていない人が大半。
・各自が好きなテーマを選び、自分のテーマに近い先生(複数人の場合もある)に見てもらう。授業を担当する先生はいるものの、いわゆる「指導教員」がいるわけではない。
4年生Aセメスター
■卒論を仕上げる4A
・週0-3コマが一般的。
・必修はない。4Sの必修である「卒論演習」の担当教員とたまに面談する。
・就活も終わり、卒業単位も取得済みの人は趣味程度に他学科・他学部の授業を取る。
入る前の想像と実際
・「想像以上に院生との距離が近く、14号館4階の機器室で気軽に卒論や研究分野について話せる」(文三→文人)
・「入る前は知らなかったが、アットホームかつ文化人類学っぽいイベント(後述する『お料理コンパ』など)があり楽しい」(文三→文人)
・「院生との合同授業がかなり多く、ハイレベルな議論を求められることもある」(文三→文人)
選んだ理由/迷った学科
・「最初行きたかったのは後期教養の認知行動科学だったが、研究室訪問に行って自分と合わないのではと感じた。それから別の選択肢を考え始めた。前期教養で面白かった授業を改めて振り返ると、フィールドワークをした初ゼミや文化人類学系の授業が思い浮かんだ。最終的に、学問の守備範囲の広さやフィールドで定量的には測れないものにアプローチする魅力から文化人類学に決めた」(文三→文人)
・文化人類学という学問の扱う分野が広いことから、迷う学部学科の幅も広い。中には医学部健康総合科学科と迷う人も。
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) | 5-10※1 |
| LINE | 有※2 |
| Slack | 無 |
| オフラインでのつながり | 有※3 |
| 上下のつながり | 有 |
※1 非常に少人数であることから、学科の繋がりは年によって大きく差がある。
※2 同期LINEも上下LINEもある。事務的な連絡以外もする。BBQ企画が持ち上がることも。
※3 14号館の文化人類学機器室にプリンター・デスクトップ・自習スペースがあり、コミュニティとして機能する。
・多様な興味を持つ人が集まり、個人の考え方の違いを尊重する風土がある。幅広い分野をカバーする文化人類学という学問ならではの懐の深さともいえる。
・学生や教員がお菓子や料理を持ち寄る「お料理コンパ」が3Sにある。出身地の郷土料理、研究フィールド(アフリカとか)にゆかりの料理を持ってくる。滅多に食べられないものが出てくることもあり、文化人類学っぽくて楽しい。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 数名〜10名程度※1 |
| 成績評価 | 出席/レポート※2 |
・文献を読み担当の週に発表するゼミ形式の授業が多い。
・基本的に4回欠席で落単。少人数で優3割規定がないため、レポートを提出すれば優か優上がつく。
・「フィールド演習」以外の必修には他学部の人もいる。
研究室・資料
〈研究室紹介〉
○東京大学文化人類学研究室
○教員紹介(一部)
・箭内 匡先生:スペイン・南アメリカ、イメージの人類学
・関谷 雄一先生:西アフリカ、社会開発研究
・浜田 明範先生:西アフリカ、感染症の人類学、医療人類学、経済人類学
特別な制度・その他
・サブメジャープログラム:所属コースの主専攻だけではなく、他コースが提供する15単位程度の科目群を副専攻として履修するプログラム。修了生は卒業時に、卒業証書だけではなく、サブメジャー・プログラム修了証ももらえる。
・学融合型プログラム:分野横断的な学習を行うプログラムで、グローバル・エシックス、グローバル・スタディーズ、東アジア教養学、進化認知脳科学、科学技術インタープリターの5種類がある。例えばグローバル・エシックスでは社会・人文科学系の問題のみならず自然科学やテクノロジーに関わる諸問題に対応していくための包括的な価値観や倫理に関わる判断を下す力を身につけることを目的としている。文理の壁を超えてより複眼的知識を身につけたい人は検討してみても良いだろう。詳しくはこちらを参照。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部

教養学部
「学際性」「国際性」「先進性」を軸に、深い教養を基盤に従来の枠組み・領域を超えて新しい分野を開拓する人材を育成する学部
関連記事
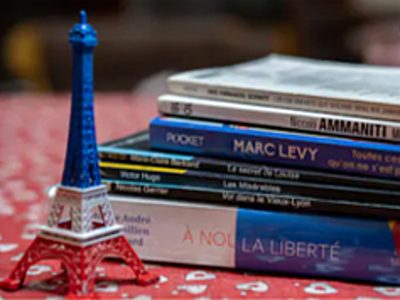
Gフランス語フランス文学専修
G群(言語文化_フランス語フランス文学)

身体教育学コース
総合教育科学専攻 心身発達科学専修
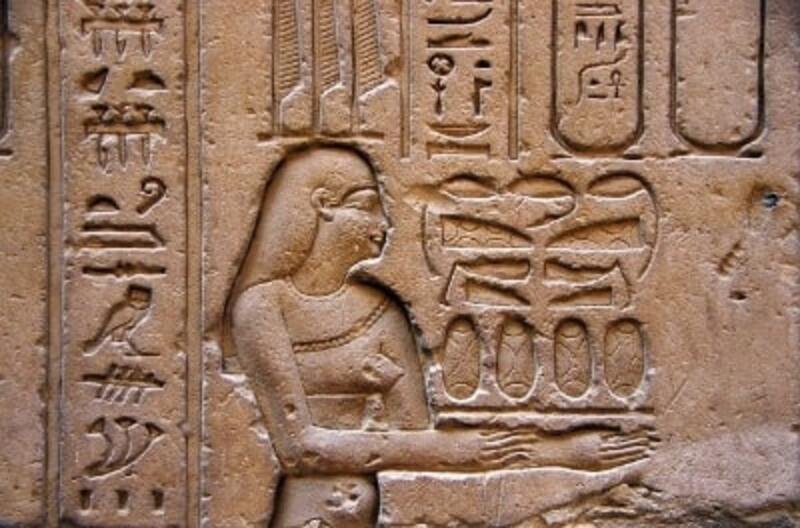
E考古学専修
E群(歴史文化_考古学)
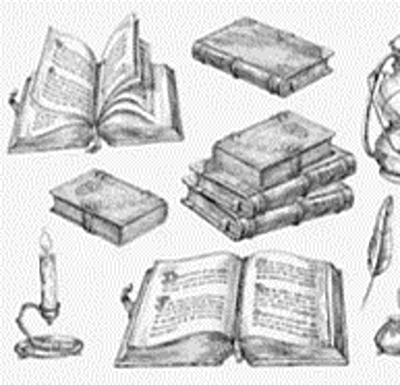
学際A 科学技術論コース
教養学科 学際科学科A群




