文学部
J社会学専修
2023.4.15
J群(社会学_社会学)
目次
基本情報
| 人数 |
50名程度 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ5割 |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
院進は一定数いるが、文学部の中では就活率が高い方 |
| 公式サイト |
学科概要
社会学専修とは
文学部社会学専修では、「学説・理論」、「家族・性・世代」、「地域・都市」、「産業・労働」、「計量・階層」、「社会意識・文化」、「計画・福祉」、「国際・世界」、「技術・環境」、「多文化共生」といった領域で研究が展開され、各学生は自身の興味に応じた履修ができる。
文学部内で最も大所帯の専修(※)で、1学年50名程度の学生が在籍。学生間の繋がりは専修全体単位ではなくゼミ単位となることが多い。中でも出口ゼミや赤川ゼミが大規模なものとして有名。
(※)「専修」…文学部は人文学科という1つの学科が設置され、その中に大きなくくりとしてのコースが複数置かれ、そのコースの下に「専修」という単位が設けられている。(コースの下、専修の上には「群」も設置。)
必修科目について
必修科目は、3年〜4年についてはゼミが必修となっているが、それ以外は4つのみで、また卒業単位の半分程度である32単位を他学部他学科の科目の単位で充当できるなど、履修の自由度が高いことが大きな特徴。3S以降、選択必修が12単位以上必要だが、中には社会学専修以外で開講のものもあり、他学部・他専修を履修するのは専修内でも一般的である。
ゼミについて
ゼミは、主ゼミと2つ目以降のゼミとで性格が分かれる。主ゼミは学年が変わったタイミング(3S/4S)で申請し、複願可能で、卒論テーマ希望も併記する形式である。学部主導で学生の関心に沿うよう振り分けられ、第一希望で通ることが一般的で、主ゼミの教員がその年の指導教官となる。2つ目以降のゼミは、選考は特に行われず、普通の授業と同じ感覚で履修することが可能。なお、他の文学部専修同様、座学であるとしていても内実はゼミというケースが多い。選択必修にもかかわらず、年によっては国内外へフィールドワークに赴く科目も存在する。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
・2Aでの必修科目は3種類ある。
| 科目 | コマ数 |
|---|---|
| 社会学概論 | 週2コマ |
| TAセミナー | 隔週1コマ |
| 社会調査 | 週2コマ |
・履修コマ数は、12コマ前後が一般的。
・持ち出し可能な文学部科目が少ないので、持ち出し可能な他学部履修をする学生が多い。分野として社学と親和性が高い後期教養が多めらしい。
※持出科目…後期課程の科目であるが、前期課程の対象学生も受講できる科目のこと。持出科目か否かはシラバスを見ればわかる。
社会学概論
オムニバス形式で、社会学専修の教員が1人ずつ講義。各分野や各教員について知ることができるので、ゼミ選びの参考とする学生が多い。毎週1500字レポートが課される。金曜1、2限が一般的。駒場1号館で開講。
TAセミナー
隔週開催で、院生主導で輪読形式のゼミのような形式。プロ倫(※)と自殺論(※)は毎年固定、もう一冊は年によって異なる。月曜5限が一般的。一回でも欠席すると、代わりの救済レポートが課される。
※プロ倫:資本主義経済に順応し「発展を遂げた国」と、「そうでない国」の間には、宗教の違いがあることを解明したマックスウェーバーの名著。
※自殺論:「社会的事実」を客観的かつ実証的に分析し、その実態を具体的な事例によって明らかにしようとしたデュルケームの意欲作。
社会調査
統計などを扱う。前期教養の基礎統計と同レベル程度で、教員も親切にいろいろ教えてくださるらしい。月曜3、4限が一般的。本郷法文2号館開講。
3年生Sセメスター
・3Sでの必修科目はゼミを除くと1種類のみ。
| 科目 | コマ数 |
|---|---|
| 社会学史概説 | 週2コマ |
・履修コマ数は、12コマ前後が一般的。
・たいていの授業は法文1号館・2号館・文学部3番大教室で行われる。
・4月にゼミ選択が行われる。詳細は上記「学科概要」の通り。
・ゼミは基本的には火水木2限のいずれか、週1コマ。
・選択必修は3S以降で履修が可能となる。そのため、3S/3Aで週3コマ(6単位)ずつ計12単位を取り切る学生が多い。
社会学史概説
社学のメインの授業となるため、レポート等も一定量課される。試験は持ち込み不可で、語句説明&大論述構成となっている。試験の救済措置は追加レポートという形式で存在するらしい。
3年生Aセメスター
・履修コマ数は、12コマ前後が一般的。
・必修が無いので、選択必修やその他の科目で卒業要件に近い単位数まで修得する学生が多い。
・3年次末までに「ゼミ論」2万字程度を執筆し、これが卒論の準備となる。
4年生Sセメスター
・4月にゼミ選択が行われる。詳細は上記「学科概要」の通り。
・3年次とは違うゼミに移る学生も一定数いるが、大半は同じゼミに残る。
・希望調査によるゼミ振り(ゼミ振分け)は、卒論テーマと指導教官のテーマとの相性で判断されると思われるので、3年生の時に入ったゼミと同じゼミを希望して落ちることはまれと考えられる。
・卒論の執筆を開始。各学期1,2回ほど指導教官と面談しながら行っていく。
4年生Aセメスター
・卒論の執筆作業が主となり、中間発表や面談も経ながら1月に発表を行う。
入る前の想像と実際
・思ったより専修としてのまとまりが弱い。もっとまとまっているものだと思い込んでいた。人数が多いからかも。
・選択必修で他専修開講の科目もあり、他学部履修も容易にできることから、色々な学科を横断的に見ていくことができる。
・各分野に一人ずつは先生がいるが、ゼミでスペシャリストや専門性を深く追求する雰囲気ではないところが多い。
・文学部開講科目を受ける機会が意外と少ない。
選んだ理由/迷った学科
・地域社会学系に関心ある人が結構いる印象で、自分もそうだった。工学部の都市工学科や後期教養学部の地理空間とは迷ったが、ハード面・ソフト面・地理面のどこから捉えるかを考えた。都市社会学は文系の視点で社会学を見るうえで有用で、興味に合っているとも感じた。(文三→社学)
・前期教養で様々な社会問題を知ったが、その問題化のプロセスや原因までさかのぼった本質的な分析を学びたかった。前期教養のジェンダー論も面白かった。元々の関心である地域や観光に、何らかの形で結びついた学問がしたかった。(文一→社学)
・主に「コミュニティ」「ジェンダー」「福祉」「格差」等が学科選択の軸と考えられる。
・数学が不要だからという理由で文二から来る人もいる。
コミュニティとしての機能
・専修全体としては繋がりが弱い。ゼミ単位では強い。
・学科LINEはあるが、あまり動かないイメージ。同じゼミなら先輩後輩の繋がりは発生する。ゼミ合宿などはあるので、そこで仲良くなる人が多い。
授業スタイル
・大教室で行われる授業も多い。
・必修はそれぞれ、レポート1つ、試験2つ。
・社会学特殊講義などの選択必修は、先生次第だがレポート課題が多い。
・出席必須かどうかの度合は授業によって異なる。ただ、全般的に緩いものが多い。
研究室・資料
特別な制度・その他
特になし
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
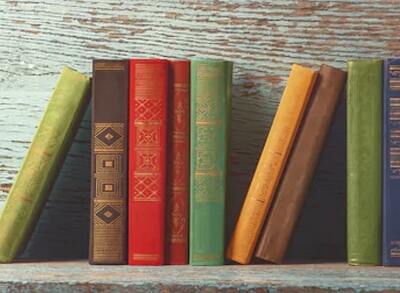
文学部
専門知識や幅広い視野を備え、異なる準拠枠を踏まえ自らの専門を相対化できる、高度な教養人として活躍する若者を育成する学部
関連記事

教育実践・政策学コース
総合教育科学専攻 教育社会科学専修

学際A 地理・空間コース
教養学科 学際科学科A群
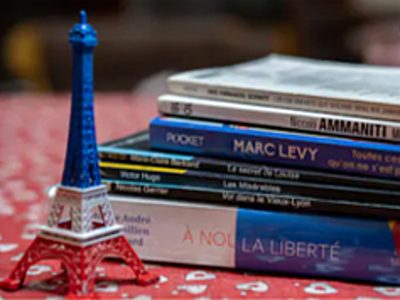
Gフランス語フランス文学専修
G群(言語文化_フランス語フランス文学)
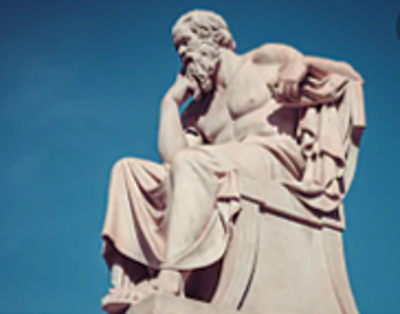
A哲学専修
A群(思想文化_哲学)




