文学部
Gドイツ語ドイツ文学専修
2023.4.3
G群(言語文化_ドイツ語ドイツ文学)
目次
基本情報
| 人数 |
2,3名(2021年度は1名) |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
人数が少ないので、年によって大きく異なる。 |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
就職:院進=1:1 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな学部?
ドイツ語ドイツ文学専修(通称「独文」)では、テーマや時代に縛られずドイツ語圏の文学作品を扱っており、毎年数人が進学する。ほとんどの授業は原典購読であり、院生と合同で受けるため学年を超えて強いつながりがある。また、同じ先生の授業を複数回受けるため、先生とも距離が近い。
他専修とのつながりとしては、学問的なつながりが強い仏文の学生と一緒に授業を受けることがある。
2021年10月現在、授業はオンラインで行われている。法文3号館4階にある研究室は月曜日と木曜日に開室しており、学生が来ることも多い。
■ドイツ語ドイツ文学専修の諸制度
卒業までに必要な単位は76単位。そのうち16単位までは、他学科の授業を含めることができる(他学部は不可)。独文の授業は、
・ドイツ語学概論(4単位)
・ドイツ文学史概説(4単位)
・独文の教授の専門に関する講義であるドイツ語学ドイツ文学特殊講義(12単位)
・輪読や発表がメインになるドイツ語学ドイツ文学演習(16単位)
・卒論(12単位)
がある。Sセメで演習という名を冠していた授業がその続きをAセメに特殊講義という名を冠して行なっていたり、概説といいながら演習形式だったりするため、授業の冠する名前と形式が対応していないことがある。
■進学定数は?
・定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 文Ⅲ(指定科類) | 62 | 15 |
| 全科類 | 14 | 15 |
■内実は?
学業及びドイツ文学に対して目的意識高く取り組んでいる人が多く、院生と関わる機会もあるため就活より究に打ち込む人が多い。
重い授業、授業外の予習や自主的な読書により、ドイツ文学にどっぷり浸かっている。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| ドイツ文学史概説 | 必修 | 火曜3限 |
| ドイツ語学ドイツ文学演習 | 必修 | 金曜5限 |
・「ドイツ文学研究入門」は履修が推奨されている。
3年生Sセメスター
・学年ごとに取らなければいけない授業はなく、個人の都合に合わせて卒業までに必修を取り切る。
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| ドイツ語学ドイツ文学特殊講義II | 必修 | 月曜4限 |
| ドイツ語学ドイツ文学演習Ⅴ | 必修 | 火曜3限 |
| ドイツ語学ドイツ文学特殊講義Ⅵ | 必修 | 火曜4限 |
| ドイツ語学ドイツ文学特殊講義I | 必修 | 水曜2限 |
| ドイツ文学史概説I | 必修 | 水曜3限 |
| ドイツ語学ドイツ文学演習Ⅵ | 必修 | 木曜2限 |
| ドイツ語学ドイツ文学演習I | 必修 | 金曜3限 |
・3年生に上がるタイミングで歓迎会がある。
・授業は8〜10コマくらいの人が多い。
3年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| ドイツ語学概論II | 月曜3限 | |
| ドイツ語学ドイツ文学特殊講義Ⅲ | 必修 | 月曜4限 |
| ドイツ語学ドイツ文学特殊講義Ⅴ | 必修 | 火曜4限 |
| ドイツ語学ドイツ文学演習Ⅴ | 必修 | 水曜4限 |
| ドイツ語学ドイツ文学演習Ⅶ | 必修 | 木曜4限 |
| ドイツ語学ドイツ文学演習Ⅱ | 必修 | 金曜3限 |
| ドイツ語学ドイツ文学演習Ⅲ | 必修 | 金曜5限 |
・授業は8〜10コマくらいの人が多い。
・実際に卒論についてガイダンスがあるのは4Sだが、卒論について教授と話す人もいる。
4年生Sセメスター
4年生Aセメスター
入る前の想像と実際
・「ドイツ文学は活気がない」と言われていたが、想像していたよりも先生が優しく、学科の雰囲気は暖かかった。
・一つの授業で多くのテーマや作家を扱うので、当初関心を持っていた作家以外にも興味を持つようになる。
・中世ドイツ語を扱うので、文法や言葉の使い方が難しい。
選んだ理由/迷った学科
・選んだ理由
文学部日本語日本文学専修の進学も考えたが、ドイツ人の作家が好きであることに加え、、国文学は自主的に勉強可能と考えたことから、ドイツ語ドイツ文学専修に進学した。また、ドイツ人作家を生涯をかけて追いかけている教授と話してみたい気持ちもあった。ドイツ語選択だったこともあり、英語とドイツ語をマスターしたかった。
(文科一類→ドイツ文学)
・迷った学科
駒場時代の「言語体理論」を受講し、担当する先生が所属している、後期教養超域文化の言語態・テキスト論コースと迷った。しかし、教養学部はテーマごとに勉強をする傾向があり、歴史や哲学なども含めて包括的な勉強がしたかった。
また、入学当初は官僚になりたかったため、法学部への進学も考えたことがあった。しかし、法学部の雰囲気が合わず、官僚になりたい気持ちが薄れた。(文科一類→ドイツ文学)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
9 |
| LINE | 無 |
| Slack | 有 |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | 有 |
・コロナ禍であっても授業が交流の場になっているため、関係性を作ることができる。一緒に授業を受けていた院生が、次の授業ではTAをやってくれる、という場合もある。
・Slackは専修全体のものがあり、雑談チャンネルがよく動いている。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 10名前後 |
| 成績評価 | 出席/レポート |
・クラスの人数は10人前後で、質問や発言が求められる。
・予習が必須で、文章が割り当てられて発表することが多い。
・よっぽどのことがない限り欠席せず、真面目に授業を受けている人が多数。担当が割り当てられているので、休むと周りにも迷惑がかかる。
・成績評価はレポートもしくは平常点で、先生の裁量による。
研究室・資料
〈所属先生〉
先生方はドイツ文学の第一人者で、今でも翻訳に携わっている人が多い。
・大宮教授:近現代文学担当。19世紀末から20世紀の文芸と思想の関わりを、ベンヤミン、エルンスト・ユンガー、ハイデガー、アーレントなどを結節点にして考えている。
・宮田教授:近現代文学担当。ノヴァーリスをひとつの中心として、現代の文芸理論も参照しつつ、<ロマン主義>がはらむさまざまな問題と可能性を、その前史と後史のなかに探ろうとしている。
・KEPPLER-TASAKI准教授:近現代文学担当。ゲーテを研究の中心としながら、近世から現代に至るドイツ近現代文学を、祈り・中世・映画という諸領域との関わりで捉えようとする研究を精力的に進めている。
・山本准教授:中世文学担当。
特別な制度・その他
・DAAD(ドイツ政府公認の奨学金の機関)と綿密な連携がある。
・「詩・言語」という雑誌に院生が寄稿している。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
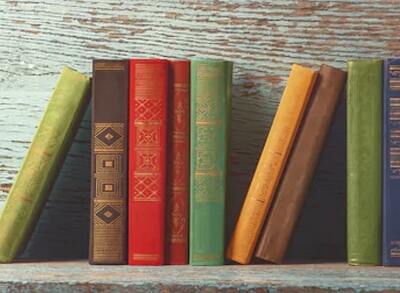
文学部
専門知識や幅広い視野を備え、異なる準拠枠を踏まえ自らの専門を相対化できる、高度な教養人として活躍する若者を育成する学部
関連記事

G西洋古典学専修
G群(言語文化_西洋古典学)
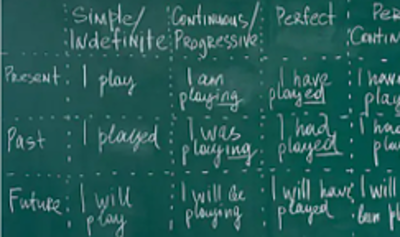
G言語学専修
G群(言語文化_言語学)

D西洋史学専修
D群(歴史文化_西洋史学)

超域 現代思想コース
教養学科 超域文化科学分科




