文学部
F美術史学専修
2023.4.15
F群(歴史文化_美術史学)
目次
基本情報
| 人数 |
15名(年によって一桁のことも) |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ2-5割程度。年度による変動は大きい。 |
| 要求/要望科目 |
特になし |
| 就活or院進 |
ほぼ全員が就職する。院進は3人程度 |
| 公式サイト |
学科概要
美術史学専修は、西洋・東洋・日本の古代から近代まで、絵画・彫刻・工芸のほとんどあらゆる分野をカバーできる学問領域を持ち、日本における美術史学の発展に寄与してきた。
現在の専任は、日本中世美術、日本近世美術、西欧中近世美術をそれぞれ専門とする教員3名。それに加えて、学内学外の美術史学出身の教員の協力を仰ぎ、幅広い指導を受けることができる。卒論を含めて学位論文のテーマは、教員の専門と無関係に学生が自由に選択できる。
進学した3年生は、通常5月に行なわれる関西見学旅行の演習に参加して、実物を楽しみ、よく観察し、それについて調べ考えるという美術史学の基本に触れる。また、日常の授業でも博物館・美術館・美術商の見学や、スライド・写真の多用によって、眼の記憶と判断力を豊かにすることが配慮されている。
活躍の場は大学・研究所・博物館・美術館・官庁・ジャーナリズムと多岐に亘る。学部卒業で就職する学生は、出版・放送など特に美術史とは関係のない職を得るのが普通である。専門家を目指す人は大学院に進学し、修士課程修了後や博士課程在籍中に、全国各地の美術館・博物館に学芸員として就職したり、大学に職を得たりする。
■美術史学専修の諸制度
| 科目 | 必修科目 | 必要単位 |
|---|---|---|
| 史学概論 | 必修 | 2単位 |
| 哲学概論、美学技術学 | 選択必修 | 4単位 |
| 美術史学特殊講義、美術史調査方法論 | 選択必修 | 16単位 |
| 日本史学特殊講義、東洋史学特殊講義、西洋史学特殊講義、考古学特殊講義 | 選択必修 | 4単位 |
| 美術史学演習 | 必修 | 8単位 |
| 卒業論文 | 必修 | 12単位 |
| 他学部他学科科目 | 自由 | 30単位 |
| 卒業に必要な単位 | 76単位 |
・卒業に必要な単位は76単位。内訳は、必修46単位と、文学部を含めた他学部の30単位。卒論は必修で12単位。学年ごとの必修はなく、基本的にどの時期にとっても問題ないが、2年生の持ち出し科目は少ない。
・研究室はないため、個人で進める。4年生の6,7月に卒論テーマを発表する機会がある。
・文学部を含めた他学部の30単位では、美術史学の授業を余分にとったり、学芸員資格や教職のための授業をとったりする。また、工学部建築学科の建築史についての授業をとる人もいる。
■進学定数は?
・定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 文Ⅲ(指定科類) | 9 | 2 |
| 全科類 | 2 | 2 |
・年によって進学する人数にばらつきがある。
■内実は?
・サークルや運動部に所属している人はそれなりにいるが、多数派ではない。美術館や博物館に行くのが好きな人が多く、授業でも推奨されている。
・学年によって異なるが、就活やインターンの話はあまり会話には出ない。
・毎年数人留年する人がいる。
・専修の先生はアドバイスを求めれば応じてくれるが、基本的には個人で勉強する。
・学生の興味の範囲は広く、卒論で取り上げるテーマは絵画、彫刻、工芸などで地域や時代も幅広い。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■【他の歴史文化コースと一緒に受ける2A】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 史学概論 | 必修 | 金曜2限 |
| 哲学概論Ⅱ | 必修 | 月曜2限 |
| 美術史学特別講義III | 必修 | 金曜4限 |
(※1)2Aセメスターににとる人がほとんどだが、3Aセメスター、4Aセメスターでも取ることは可能。ただし、対面の場合駒場で開講される。評価は期末試験のみで、論述が一問だった。
(※2)テーマが変わる可能性があるが、2018年は現象学について扱った。対面の場合本郷で開講される。評価は毎回のリアぺと最終レポート。
(※3)哲学概論、美学芸術学の中から合計で4単位を取得する。
(※4)美術史学特別講義の中で2Aで取れるのは1種類しかない。
・週平均のコマ数はバラバラ。
・2年生の持ち出し科目が少ないため、他学部の授業を受けている人もいる。
・他の歴史学科の人と共通の授業が多いので、受講している人数は多い。
3年生Sセメスター
■【ゼミが本格化する3S】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 美術史学特別講義 | 必修 | 授業によって異なる |
| 美術史学演習 | 必修 | 授業によって異なる |
| 日本史学特別講義 | 必修 | 授業によって異なる |
| 東洋史学特別講義 | 必修 | 授業によって異なる |
| 西洋史学特別講義 | 必修 | 授業によって異なる |
| 考古学特別講義 | 必修 | 授業によって異なる |
| 美学芸術学演習 | 必修 | 授業によって異なる |
(※1)3Sセメスター、3Aセメスター、4Sセメスターで2単位ずつ取得する。主に日本、西洋に分かれている。輪読、レポート、発表など評価方法はさまざま。西洋の演習には、外国語の論文や博物館のカタログを和訳するものもある。
(※2)日本史学特別講義、東洋史学特別講義、西洋史学特別講義、考古学特別講義から合計で4単位を取得する。評価方法は担当教授によって異なる。
(※3)哲学概論、美学芸術学演習の中から合計で4単位を取得する。
・週平均のコマ数は人によってさまざま。
・自分の興味にしたがって授業を柔軟にとることができる。
・学芸員を目指している人は3Sセメスターから必要な授業をとる。
・3年生のゴールデンウィークには、旅行ゼミ(科目名は美術史学演習III)が行われる。京都、奈良での研修を踏まえて自分の興味分野について発表する。2019年は大塚国際美術館に行った。そのほかにも、展覧会や寺院に足を運ぶ。2020年は実施されなかった。
・美術史学演習の中の名物ゼミがS2タームからA1タームにかけて行われる「絵巻ゼミ」と呼ばれるもの。S2タームでは、絵巻に関連する論文を学び、A1タームでは崩字を活字に起こす「彫刻」を体験することができる。ただし、必修科目としての「美術史学演習」の単位には算入されない。
3年生Aセメスター
■【自分の興味を深堀する3A】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 美術史学特別講義 | 必修 | 授業によってさまざま |
| 美術史学演習 | 必修 | 授業によってさまざま |
・時間割に余裕があるため自由に履修が組める。
4年生Sセメスター
■【卒業論文に取り掛かる】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 卒業論文 | 必修 | 通年 |
| 美術史学特別講義 | 必修 | 授業によってさまざま |
| 美術史学演習 | 必修 | 授業によってさまざま |
・週平均のコマ数は人によってさまざま。
・卒業論文は4Aセメスターの1/6頃の提出期限に向けて個人で博物館や美術館に行き、各自で進める。
4年生Aセメスター
■【進路はバラバラ】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 卒業論文 | 必修 | 通年 |
・卒業論文に勤しむ人が多い。必修の演習や取り残した単位があればここで回収する。
入る前の想像と実際
・学生生活では、よくも悪くも、イメージと大きく異なることはなかった。
・授業では古代から現代まで網羅的に扱うことがないのは意外だった。
アドバイス
・授業では「概論」と言いつつも、教授の専門のことを扱う。ざっくりとでもいいので、通史の本を読んでおけばよかった。
・美術史というと、西洋美術をイメージしがちだが、この専修では東洋や日本のことも多く扱うので、それらの分野に触れておけばよかった。
選んだ理由/迷った学科
・「もともと西洋美術に興味があり、美術館にいくのが好きだった。美芸美術学など、文学部の他の学科でも似たようなテーマは学べるが、ひたすら文献と格闘するイメージが強く、美術史学の、絵画や彫刻など実際のものを分析できることに惹かれた。」
「教養学部の比較芸術も考えたが、卒論のテーマを見て、少し違うかなと思った。個人的なイメージでは、後期教養学部では新しい分野を扱い、文学部では昔からある、確立されたことを扱えると思う。」(文三→美術史学専修)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
5 |
| LINE | 有 |
| Slack | 無 |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | 有 |
(※1)3年生のゼミで研修旅行があり、そこで同期と顔見知りになる。
(※2)内定が決まった2年生から博士課程の人までがいる学科全体のLINEグループ(39人)と、同期のLINEグループがある。全体の方は院生に卒論について聞いたり、おすすめの文献について聞き合うなどそこそこ活発に動くが、同期の方はほとんど動かない。
(※3)授業外で集まる機会は滅多にないが、2年の9月と3年の4月に専修の演習室で食事会を行った。
(※4)ゼミは院生とも合同で行う。
・研究室があるわけではないため、教授との繋がりはあまり強くない。もちろん、質問対応はしてくれる。
・現在は、院生の人が主体となって勉強会や読書会を開いてくれている。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 10~20名前後(※1) |
| 成績評価 | レポートが主 |
・2年生のうちは合同授業が多く人数もそれなりにいるが、3、4年生がとる授業は10~20人くらいになる。演習は院生も取っている。
・定期試験で評価されるのは他専修のものであり、美術史学専修ではレポートで評価される。試験がそもそもないため、シケプリは存在しない。
・美術史学では「見る」ことを重視しているため、パワーポイントを使った授業が多い。
研究室・資料
〈担当教授紹介〉
秋山聰(あきやま あきら)教授:西洋美術史
高岸輝准教授:文化資源学
芳賀京子准教授
特別な制度・その他
・死生学・応用倫理教育プログラム
人間にとって科学技術とは何なのか、何であるべきなのか、また人間にとって生きることと死ぬことはどのようなものであるべきなのか、というような問いから発した「死生学」でと「応用倫理」を分野横断的に学ぶプログラム。
・文学部夏期・冬期特別プログラム
夏期は本郷キャンパスを中心とした東京首都圏または研究科附属常呂実習施設(北海道北見市)において、冬期は英国ロンドンおよびセインズベリー日本藝術研究所がある英国南東部のノーフォーク州において、東大の学部生5名と欧州の学部生5名が、寝食を共にしながら、考古学・美術史学・歴史遺産等を学ぶことができる。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
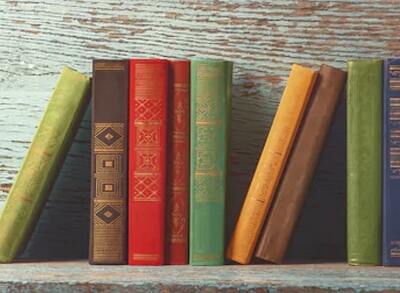
文学部
専門知識や幅広い視野を備え、異なる準拠枠を踏まえ自らの専門を相対化できる、高度な教養人として活躍する若者を育成する学部
関連記事
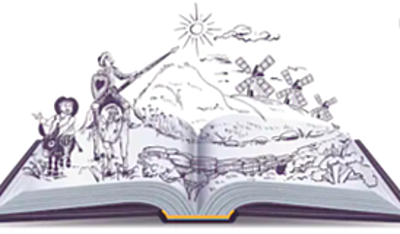
G南欧語南欧文学
G群(言語文化_南欧語南欧文学)

Gスラヴ語スラヴ文学専修
G群(言語文化_スラブ語スラブ文学)

C東洋史学専修
C群(歴史文化_東洋史学)

A倫理学専修
A群(思想文化_倫理学)




