理学部
生物化学科
2023.4.15
目次
基本情報
| 人数 |
20名 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
1-3割程度。年により大きく変動する。 |
| 要求/要望科目 |
・要求科目 ・要望科目 |
| 就活or院進 |
就職する人は1年に1名いるかいないか |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな学科?
理学部生物化学科、通称「生化(せいか、せいばけ)」。
理学部には「生物学科」「生物化学科」「生物情報科学科」と、生物系の学科が3つあり、生化は特に「代謝・神経・遺伝」等について、分子レベルから解析するような授業が多い。生化に所属しながら生物学科や生物情報科学科の授業を取る人も多く、特に生物情報科学科とは合同で実験を行うこともあるなど学科間の垣根が比較的低いのが理学部生物系の特徴の一つ。
卒業したあとはほぼ全員が院に進学し、就職する人は数年に1名ほど。多くの学生は研究室内で持ち上がり、2割程度は他学部他学科の研究室へ、そして若干名が海外大学院に進学する。
■生化の諸制度
卒業までに必要な単位は2年次に16単位以上(うち必修4)、3,4年次に合わせて63.5単位以上(うち必修35.5)。3,4年次の必修以外の28単位のうち、22単位は学科指定の選択科目から、残りの6単位は理学部専門科目から取得する必要がある。ただし,他学部専門科目について,あらかじめ所定の期日までに科目認定届を提出し認められた場合には,理学部専門科目に加えることができる。
3Sセメスターから多く利用する理学部3号館は東大内でもトップレベルの科研費をもらう研究室が集まっている。
研究室は3Aセメスターで選択し、4Sから入ることになる。3Sセメスターから行われる各研究室主導の実験を通して自身の興味を明確にし、所属する研究室を選んでいくことができるカリキュラム構成となっている。決め方は成績順ではなく、学生側の希望がなるべく通るようなマッチングのシステムが存在している。学科の人数が比較的少ないので、競争が極端に激しくなることはない。
■進学定数は?
・定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 理科(指定科類) | 13 | 6 |
| 全科類 | 1 | 0 |
・得点計算で考慮すべき科目
①理科生は、総合科目E,Fの成績上位6単位までの重率を「2」とする。(第1~2段階)
②総合科目成績上位4単位の重率を「5」とする(第1~2段階)
■内実は?
実験等による忙しさゆえか、インターンをする学生の数はそれほど多くない一方で、アルバイトをする学生は多い。東大全体の傾向と同じく教育系の割合が高いが、データ解析、プログラミングなどのスキルを生かし、専攻内の研究室でアルバイトをする人もいる。頻度としては、部活、アルバイト合わせて週に2,3回程度が標準的。
卒業研究は4年生の1年間をかけて執筆する。理系の中でもかなり忙しい方だと言われており、特に院試と並行して進める夏頃のスケジュールはハードになりやすい。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■新たな仲間に出会う2A
| 日程 | 授業内容 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 生物化学概論I | 必修 | 木曜2限 |
| 生物化学概論II | 必修 | 金曜3限 |
・必修科目2科目(4単位)の他、選択科目より計12単位以上を学習しなければならない。
・セメスター開始時には学科ガイダンス、続いて歓迎会が設けられている。
3年生Sセメスター
■忙しくなる3S
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 生物化学実験法 | 必修 | 月曜3,4限 |
| 生物化学実験I | 必修 | 火〜木曜3,4限, 金曜3~5限 |
・必修で10コマ、それ以外に10コマ程度履修するのが標準的。
・この時期に行われる実験は各研修室主導となっており、3Aセメスターの研究室選びの検討材料としての意味合いも持つ。
3年生Aセメスター
■研究室を選ぶ3A
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 生物化学実験II | 必修 | 月〜木曜3,4限, 金曜3~5限 |
・3Sセメスター同様、必修で10コマ、それ以外に10コマ程度履修するのが標準的。
・3Sまでの履修単位数が少ない場合はここでの取得単位数が増える。逆も然り。
・この時期に研究室を選択することになる。
4年生Sセメスター
■卒業研究が始まる4S
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 生物化学特別実験I | 必修 | 月曜2限,火〜金曜2~4限 |
| 生物化学演習I | 必修 | 月曜3,4限 |
・研究室に配属され、必修科目は全て卒業研究に関連したものとなる。
・3年次に選択科目の必要単位数を取りきれなかった場合はここでとることになる。
・卒業研究と並行して、院試の準備をすることになる。
・極めて稀であるが、院に進学しない場合は就活がこの時期になる。
4年生Aセメスター
■卒業研究が大詰めの4A
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 生物化学特別実験II | 必修 | 月曜2限,火〜金曜2~4限 |
| 生物化学演習II | 必修 | 月曜3,4限 |
・4S同様、必修科目は全て卒業研究に関連したものとなる。
・4Sまでに選択科目の必要単位数を取りきれなかった場合はここでとることになる。
・年度末に行われる卒業研究発表会で一年間の研究成果を発表する。
・優れた卒業研究は一流科学誌に掲載されることも。
入る前の想像と実際
・化学的な内容がほとんどかと思っていたが、情報系やマクロな生物学まで多岐にわたる内容を学習することになった。
・入試で生物を選択していた者がもう少し多いかと思っていたが、物理選択者(生物を選択していない者)がかなり多かった。授業内容的にはどちらが有利になるわけでもなく一長一短。
(理二→生化)
・前期教養レベルの生物は復習しておくべき。文系出身なら「理系総合のための生命科学」という教科書を通読すると良い。
選んだ理由/迷った学科
・理学部の生物学科や生物情報科学科と迷ったが、学習内容の垣根は低いようだったので、行きたい研究室があることを理由に生化を選んだ。
(理二→生化)
・知り合いに薬学部と迷っていた人がいるが、研究室見学等をして、研究室の研究テーマから生化を選んだと言っていた。
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
7 |
| LINE | 有 |
| Slack | 有 |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | 有 |
・学科LINEは活発ではなく、遅刻者が出席や資料配布の確認をする時に動く程度。
・slackは活発に動く。課題や資料、各種説明会へのリンクなどが共有される。
・実験の控室があり、毎日実験を行う性質上、かなりの時間をそこで学科メンバーと過ごすことになる。
・上下の繋がりは、過去問の共有がメイン。シケ長が存在し、その人経由でOnedriveの資料を共有してもらう。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 30名前後 |
| 成績評価 | 主に出席/レポート |
・生物系の他学科からの履修者がいるため、多くの科目で履修者は30名を上回る。
・レポートが多く、論文のまとめ作成、論文で登場する手法の適不適を論じる、好きなテーマで書く、など内容も多岐にわたる。
・研究室選びに成績が影響しないので、あまりストイックに試験勉強に打ち込む必要はなく、その分自分の好きな分野の勉強に時間を割くことができる。
研究室・資料
〈研究室紹介〉
多くの先生が、NatureやScience、Cellなど有名誌に論文を投稿している。
研究室一覧
特別な制度・その他
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
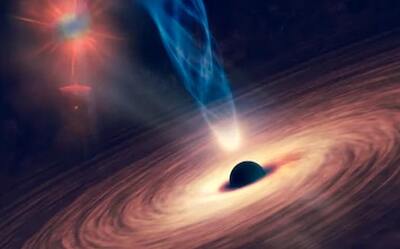
理学部
理学の理念の下に、 豊かで平和な人類の未来社会を切り拓く先端的な理学の教育・研究を推進する学部
関連記事

生命化学・工学専修
【応用生命科学課程】通称「農二(のうに)」

化学システム工学科
環境・エネルギー・医療

水圏生物科学専修
【応用生物科学課程】通称「水圏(すいけん)」





