工学部
電子情報工学科・電気電子工学科(EEIC)
2023.12.12
2学科まとめて掲載
目次
基本情報
| 人数 |
電電60名~・電情60名~で計130名 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ1割 |
| 要求/要望科目 |
・要求科目 ・要望科目 |
| 就活or院進 |
ほぼ9割以上院進/学部卒で就職する人はほぼいない |
| 公式サイト |
学科概要
電気電子工学科(電電)と電子情報工学科(電情)は、まとめてEEIC、ないし電気系と呼ばれることが多い。EEICはElectrical and Electronic engineering / Information and Communication engineeringの頭文字で、電電をEE、電情をICと書く場合もある。
ともに、現代技術の中枢を担う情報・電気・電子の技術を体系的に学び、最先端の応用へと展開していく力を養うことを目指している。
電電と電情は、研究室選択や一部の必修・選択科目が異なるなどはあっても、受ける講義の多くは同じであり、大きな差はない。また、電電でも電情の、電情でも電電の研究室を志望することも可能である。毎年度の傾向として、電情の方がやや進振り点が高いため、電情に行けるか不安な学生が電電を志望することも多い。
学部学科の魅力を紹介する映像が、学科HPから参照可能。詳細はこちら 。
進学定数は、合計120名程度。理科一類枠と第一段階の全科類枠は、電電と電情との入口が分かれている。電電は理科一類枠53名(第一段階32名+第二段階21名)、全科類枠9名(第一段階)。電情は理科一類枠41名(第一段階27名+第二段階14名)、全科類枠4名(第一段階)となっている。理科二・三類枠6名(第一段階)と全科類枠10名(第二段階)は、電電・電情の合計枠となっている。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■依然として重たい2A
・月~金の毎日に1~4限の計20コマが詰め込まれるのが基本的。課題は出るが、授業内容の確認の側面が強くそれほど重いものではない。
・2Aで開講される電気関係の科目は、3年生以降で履修する科目の基礎となるので、必修を含め週最低16,7コマ程度履修しておくことが推奨される。
・授業は全部駒場キャンパス(11号館が多い)で、電電&電情130名合同。
・1月の試験が比較的ハードだが、数学系の科目で2個の中間試験もあり、期末前以外でも勉強が必要だった。
・2Aの科目数は多く、3Aに行われる研究室選び(研振り)の点数に反映されやすいので、2Aが頑張り時。
※研振り(=研究室振分け)の基準として、昔(2017年度進学者あたりまで)は、点数×評点の総和を取る「合計点制度」が採用されていたこともあり、もっとコマ数戦争がすごかった。とはいえ、今でもコマ数が多いのは事実である。
3年生Sセメスター
■実験が多い3S
・実験が多い。月火木の3,4限が実験で、普段の座学講義の応用というイメージ。課題はレポートが多い。
・座学も月~金1,2限に入れられる。学習内容は2Aまでの科目の応用が多い。
・コンタクトグループという名前で、実験班(電電2名×電情2名×教授准教授2名程度)が構成される。履修の相談をしたり、ご飯に一緒に行ったりすることも。EEICでは、履修につき教授の判子を貰ったうえで事務に提出するのが原則となっているので、コンタクトグループの教授准教授等にお願いすることが多いらしい。
・金曜日の午後は講義が開かれず、工場見学が行われる(希望制)。柏キャンパスや先端研などEEICの研究室だけでなく、国立情報研究所やファナック、日立などにも見学に伺う。あくまで希望制なうえ、その時間帯にアルバイトを入れる学生も多く、各自3S中に5回程度参加するのが一般的とみられる。
■研振りについて
・3S末にコース選びが行われる。電情と電電の学生は6つのコース(電情寄りのA1, A2、電電寄りのB1, B2、中間のAS, BS)に分かれる。電情はA1, A2またはAS、電電はB1,B2またはBSが選択可能。各コースに応じて取るべき科目が若干異なる。コース分けに人数制限はなく自由選択である。
・必要単位数が少ないB2コースを選択し、電情の研究室に進むだけの点数上げを行う電電の人が少なからず存在する。
3年生Aセメスター
■実験が多い3A
・3Sと同じく、実験が月火木の3,4限に配置される。普段の座学講義の応用というイメージ。課題はレポートが多い。
・実験のテーマは、3Aでは自由に選択でき、電電の人でも電情系の実験が取れる。取りたい実験の希望を提出のうえ、人気のものは抽選。
・2Aと3Sで授業を多めに履修した人は、その分、授業数の負担が小さく済む。
4年生Sセメスター
■研究室と院試準備
・指定された科目のうち2コマ、4単位が必修となる(3コマ、6単位受けておいて保険かける人もいる)。4単位取れなければ即留年だが、余分に取っておくこともできるので、それほどナーバスになる必要は無い。選択必修として認定される科目はコースによって変わる。
・それ以外の時間は、基本的に卒業研究。先端研、柏、本郷などに研究室が散らばっていて、拘束時間などは研究室による。
・院試準備。
4年生Aセメスター
・卒業研究のみ。
入る前の想像と実際
・色々ことを学ぶには努力が必要で、楽して卒業したい人には向いていない学科。やりたい分野が明確にあるなら歓迎したい。(両学科)
・イメージ通りプロが多い。劣等感もたくさん抱いたが、そういった環境を利用していくべきだと考えている。(両学科)
・超マジメで学問に全力投球な人ばかりと思いきや、たまに手を抜いている人もいるので、そうした意味で悲観的になりすぎる必要はない。ただ、良い点を取るなら努力を積む必要はある。(両学科)
・入ってみると「情報系」というより「エレクトロニクス」という感じがする。(電情)
・電情といっても思ったより必修含めて電気が多い。情報だけやりたい人は楽しくない可能性がある。(電情)
・思ったより電気が好きな人が多い。(電情)
・電電と電情は授業も研究室も本当にほとんど変わらないので、進学振り分けで電情を第一志望にしている人は第二志望を電電にするべき。(電情)
選んだ理由/迷った学科
・「宇宙という軸をもとに、自科類から進学可能な選択肢として電電があったため。」(理二→電電)
・「元々情報系には興味があって、航空宇宙と迷っていたが、宇宙産業というよりは情報系を重視した。電情の先輩に知り合いがいたこともある。将来を見据えたら理学部よりは工学部が良かった。」(理一→電情)
・「電気と情報両方好きだった。競プロ(※)をやっている人とか。研究志向強い人は理情に行く。」(理一→電情)
※競プロ…競技プログラミング。本学ではAtCoderが有名。国際情報オリンピック(IOI)などでも行われる。
コミュニティとしての機能
・電電60~&電情60~の計130名のSlackグループが存在。
・一年に一回、B2(学部2年生)~院生~教授まで幅広く「縦断コンパ」が12月に行われる。そこで先輩後輩間との関係構築が可能。
・教員方も、連絡すればすぐ反応してくれるなど、熱心・親切という印象がある。
・教員同士もすごく仲がいい。研究室をまたいで、実験の授業前とか教員どうし仲良くしている。
・シケプリは過年度分が蓄積されており、シケ対制度も同期内で整っている。
・長期インターン等は、学科が忙しいからやる余裕がない人が多いが、2割程度の学生はしていそう。AnotherVisionやCASTに所属する人が割と多い。運動系も稀にいる。
・女子は、女子であるというだけで女子同士仲良くなれることが多い。
授業スタイル
■授業風景
・授業によって様々。
・実験は出席必須、遅刻厳禁。
■成績評価
・座学は授業によってレポートあるなしが分かれ、期末試験はほぼ全科目にある。座学は出席せずに単位回収する人もいなくはない。
・2Aの中間試験は毎週のペースであり大変だった。教授どうしで話し合って時期をばらしてくれているらしいが、結果として1カ月間くらい中間試験期間が続く。
研究室・資料
特別な制度・その他
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
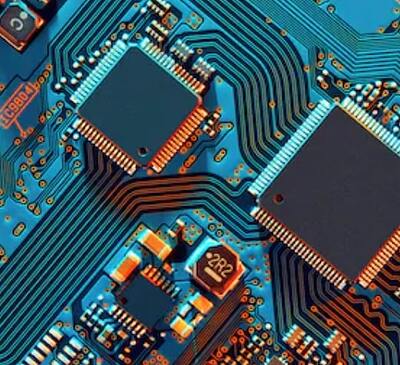
工学部
豊かで体系的な知識を身につけ、諸分野で工学的手法を活用して人類社会の持続と発展に貢献できる指導的人材を養成する学部
関連記事

システム創成学科B(SDM)
システムデザイン&マネジメント

マテリアル工学科
A,B,Cをまとめて掲載

学際B 広域システム/総合情報学コース
学際科学科B群

化学生命工学科
化学生命工学




