教育学部
教育実践・政策学コース
2024.1.9
総合教育科学専攻 教育社会科学専修
目次
基本情報
| 人数 |
25名程度(毎年数名、休学などにより入れ替わる) |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ3-4割 |
| 要求/要望科目 |
・要求科目 ・要望科目 |
| 就活or院進 |
就職:院進=8:2程度 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな学部?
・概要とカリキュラム
教育実践・政策学コース(以下、当コース)は、教育を「現場」「制度・政策」の関係を通じて捉えようとする、教育学部 教育社会科学科(※1) 教育社会学専修(※2)のコース。「制度・政策」は理解しやすいだろう。一方、一見何を意味するかわかりづらい「教育実践」とは、小中高や公民館、図書館など現場の教育活動を観察するものである。主な例として授業研究、つまり小中高での先生の問いかけや生徒の発言といった「先生と生徒の関係の観察」があり、現場に寄り添う当コースの1側面である。
※1:教育学部は、全コースともこの学科に所属する。以下、当学科。
※2:比較教育社会学コースと2コースで1専修を形成する。以下、当専修。
カリキュラムの流れは、概論で体系的な知識を身につけ、基礎演習で現場を体験し、4年次の卒論に収斂させていくようになっている。
・在籍する教員の専攻
教員は生涯学習論、教職開発、図書館情報学、教育行政学、学校教育学から成る。特定の学問上の区分や手法にとらわれず、実践的な教育に対して総合的なアプローチを行なっていく。なお、教員は大学院の「生涯学習基盤経営コース」「学校教育高度化専攻(※)」に属し、大学院進学者もそのいずれかに進むことが多い。
※:当専攻は、教職開発コース、学校開発政策コース、教育内容開発コースの3つに分かれる。
・学部卒業後の進路
就職・進学先は、公務員、民間企業、教育現場、大学院に大別される。詳細数は不明。
Cf.教育学部ホームページ コースの特色・内容
■当コースの諸制度
・必要単位数
卒業までに必要な単位は70単位。教育学部は全コースともに卒業論文8単位、必修科目30単位及び選択科目32単位の修得が必要。必修科目の30単位については、当コースの「概論」4単位と「基礎演習」6単位、更に当専修(=当コース+比較教育社会学コース)の「教育社会学演習」及び「教育社会科学特殊講義」10単位、他専修の授業科目8単位(概論2単位以上を含む)、当コース「研究指導」2単位で構成される。
・必修科目の内訳
| 科目名 | 単位数 |
|---|---|
| 教育実践・政策学概論 | 4 |
| 教育実践・政策学基礎演習 | 6 |
| 教育社会科学演習及び教育社会科学特殊講義 | 10※1 |
| 教育学部他専修の授業科目 | 8※2 |
| 教育実践・政策学研究指導 | 2 |
※1 「及び」とあるものは、「演習」と「特殊講義」にまたがって単位を取得しなければならない。なお、比較教育社会学コースと合わせた教育社会学専修の中で開講されている授業を履修することになる。詳細はUTASの「学科・コース別検索(シラバス参照)」で確認できる。
※2 概論2単位以上を含む。
・注意点
なお、当コースは前期教養で言う「情報」「ALESA」のような「特定の必修の授業」は卒論以外に無く、講義題目と授業科目が異なる点に注意が必要。例えば「概論」は、「学校教育学概論」「教育行財政学」「社会教育論Ⅰ」(以上駒場開講)、「社会教育論Ⅱ」「教職論」「情報資料論」「教育方法論」「教育課程論」「比較教育学概論」(以上本郷開講)で構成される。この時、いずれか2種類の講義を取れば4単位の要件に到達できる。
■進学定数は?
・進振り時点からコースごとに希望を出す。
・コースの定員数は26名で、受け入れ枠としては指定科類枠(文Ⅲ)、全科類枠の区分が存在する。
・定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 文Ⅲ(指定科類) | 12 | 6 |
| 全科類 | 5 | 4 |
■卒論は?
・教員10名程度、学生25名程度のコースなので、卒論は基本的に3名程度の少人数個別指導。
・ゼミに所属するわけではなく、卒論を指導してもらいたい教員に希望届を出して指導してもらうスタイル。同じ教員が4-5名指導する場合は、ゼミ形式になることも(教育行政など人気分野にて)。
・基本的には上手く希望が分かれることが多いが、教員のキャパシティを超える数の学生が集まった場合は、学生の興味分野と教員の研究分野とを照合・マッチングして学生を分散させる。
・動き出し~卒論提出までは、隔週で面談を行ったり、ある程度進捗が生まれたらその都度教員に確認を仰いだりする。教員によって内実は異なることが多い。
・卒論の質は学生による。単位を揃えて卒論を出しさえすれば、基本的に卒業は可能。「本気を出すのは大学院から」という空気があり、教員自身も学部生の卒論の質にそれほど拘る・期待することは無いよう。
〈全体的なスケジュール〉
○4S
・(現場でのフィールドワークや、教育委員会への取材を行っていく学生は)申請書・依頼書の書き方を学んだり、アポ取りを始めたりする。
・一方、文献研究中心の学生は、それほど卒論に向けた準備を行わない。
○夏休み前
・卒業論文指導会(卒論のテーマやアウトラインを発表する会)が行われる。
・教員と学生が複数グループに分かれる座談会方式。「学生が発表→教員がそれにアドバイス」という流れ。
○夏休み終わり
・文献研究メインの学生も、卒論に向けて本格的に動き出す。
○11月
・中間発表の場にて、進捗報告を行う。
○2月:最終発表(口頭質問)
・スライドを作って10分間プレゼンテーション。25名程度が1日で発表する。
・1-2名の教員から、発表内容について質疑応答を受ける。
・卒論や発表の質が低いと、教員によっては厳しく指導されることもある。
■卒業後の進路は?
・民間企業・公務員・教育現場・大学院で大別される。
・民間は、リクルートを始めとした教育系の事業会社やコンサル、また教育と無関係の企業も多い。
・プログラミング教育など、ベンチャー系の学習塾・予備校を立ち上げる学生も。
・官僚は、文科省(毎年5名程度志望者がいる)など。
・(正確に言えば公務員では無いが)大学の事務職員や図書館司書・学芸員も1-2名程度いる。
・教育現場は、高校教員や中高一貫教教員が多い。有名私立の場合、母校で採用されることが多い。※東大の教育学部では、小学校免許を取ることができない。
・大学院は、殆どが「教育学研究科」の「教育実践・政策学コース」(学校教育高度化専攻・内容開発・学校政策)へ進学。
※教育学研究科の教育実践・政策学コースは内部進学者が少なく、他大学や他学部から進学する者が多い。現場に近い内容を扱うので、教育現場経験者が来ることも。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■駒場で持ち出し科目を受ける2A
| 講義題目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 学校教育学概論 | 概論 | A2月曜3-4限 |
| 教育行財政学 | 概論 | A1月曜2限木曜2限 |
| 社会教育論Ⅰ | 概論 | A1月曜3-4限 |
| 情報・資料分析論演習 | 基礎演習 | A木曜3限 |
| 教育資料調査法演習 | 基礎演習 | A木曜4限 |
| Japanese Education | 基礎演習 | A金曜3限 |
※全て取るわけではないので注意!
・平均して8コマ前後が一般的か。
・ほとんどの人は教育学部持ち出し科目や他学部・他コース科目を駒場で受ける。
・教職を取っている学生には本郷開講を多く取る人もいるが、まれ。
・駒場で取れる持ち出し科目の数はそれほど多くない。教育学部便覧に「総合教育科学科(教育学部全5コースとも当学科に所属) 持出専門科目」として1ページにまとめられるほどの数。ただ、当コースの「概論」「基礎演習」に指定される科目がいくつかあり(上表の通り)、それらのうち幾つかを履修する。
・かなりの数取っている人もいるようだが、負担は結構重たいとの噂。「概論」「基礎演習」ともに本郷でも履修できるので、履修数はほどほどに。
・教育学部の持ち出し科目だけでなく、他学部履修として、教養学部の科目(持ち出しOKの科目が大半)を履修する者も多い。前期教養では「総合L系列」の言語系科目や、「展開科目」は、後期教養では科目名を変えるものの後期単位に参入できるものが一定数ある。シラバスを要確認。
3年生Sセメスター
■コース別だが授業はバラバラの3S
| 講義題目 | 区分 | 開講時限 (年次によって変更あり) |
|---|---|---|
| 高等教育の社会学 | 演習 | S金曜3限(偶数年度) |
| 教育行政・学校経営演習Ⅵ | 演習 | S金曜3限 |
| 博物館学特別研究 | 演習 | 通年金曜6限 |
| 教育調査分析法 | 特殊講義 | S水曜3限 |
| 教育課程論 | 概論 | S火曜5限 |
| 情報組織論演習 | 演習 | S1月曜1-2限 |
| 教育行政・学校経営演習Ⅴ | 基礎演習 | S1月曜3-4限 |
| 情報資料論 | 概論 | S1月4&木4 |
| 教育方法学演習Ⅰ | 演習 | S1火曜1-2限 |
| 日本社会の変容と課題 | 演習 | S1火4&金4 |
| 比較教育学概論 | 概論 | S1木曜3-4限 |
| 教職論 | 概論 | S2火曜3-4限 |
| フィールドワークの理論と実践 | 特殊講義 | S2火曜3-4限 |
| 社会教育論Ⅱ | 概論 | S2木曜4-5限 |
| 不良少年の社会学 | 特殊講義 | S2金曜4-5限 |
| 教育方法論 | 概論 | S2金曜5-6限 |
| 生涯学習政策論 | 特殊講義 | 7-9月(集中) |
・13コマ前後の履修が一般的。
・上表内から選ぶ形なので、人によって履修傾向はバラバラ。
・比較教育社会学コースの科目だが、「教育社会学概論」は同じ曜限にほぼ授業が無いので、履修者が多い。これは他コース生も受けるので、かなりの人数の授業となる。
・概論・基礎演習・演習・特殊講義を4年に持ち越さないため、コース科目・専修科目の履修に勤しむ。
・他学部でも文学部の心理系など似た分野の科目を取る人や、ターム制なので経済学部や農学部の授業を取る人もちらほら。
3年生Aセメスター
■卒論の足音が聞こえてくる3A
| 科目 | 区分 | 開講時限(年次によって変更あり) |
|---|---|---|
| 図書館文化史 | 特殊講義 | A金曜2限 |
| 社会教育学演習Ⅲ | 基礎演習 | A1月曜4-5限 |
| 図書館情報経営論 | 特殊講義 | A1月5&木5 |
| 教育方法学演習Ⅱ | 基礎演習 | A1火曜1-2限 |
| 教育政策研究方法論 | 特殊講義 | A木曜3限 |
| 読書と豊かな人間性 | 特殊講義 | A2月5&木5 |
| 図書館・博物館情報メディア論 | 特殊講義 | A2木曜4-5限 |
| 社会教育経営論 | 特殊講義 | 1-3月(集中) |
| 博物館学特別研究 | 演習 | 通年金曜6限 |
・13コマ前後の履修が一般的。
・上表内から選ぶ形なので、人によって履修傾向はバラバラ。
・概論・基礎演習・演習・特殊講義を4年に持ち越さないため、コース科目・専修科目の履修に3S同様もしくはそれ以上に勤しむ。
・他学部履修の傾向は3S同様。文・農・経済などが多い。
・国家一種の教養区分の試験が10月に行われる。
・任意ではあるが、4年生の卒論口述試験(2月)に出席する人が多い。その際に、先輩が何を研究していたのかを知り、自身の卒論テーマについて徐々に考えるようになっていく。
4年生Sセメスター
■卒論に着手する4S
| 科目 | 区分 | 開講時限(年次によって変更あり) |
|---|---|---|
| 卒論 | 卒論 | ―― |
| 研究指導 | 研究指導 | 通年木曜6限(隔週) |
・指導教員は5月に決める。指導してもらいたい教員に希望届を出し、1教員当たり2名以下だと個別指導、4~5名になるとゼミ形式で指導が進む。割振り・選考方法において、コースで統一した決まりがあるわけではない。
・4Sの前の2月ごろにオフィスアワーがあり、先生に自分のやりたい卒論の内容を話してみて先生を探すという、理系でいう研究室訪問的なイベントがある。
4年生Aセメスター
■卒論執筆・発表準備に追われる4A
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 卒論 | 卒論 | ―― |
| 研究指導 | 研究指導 | 通年木曜6限(隔週) |
・12月前後には、他学部・他コース同様、本格的に卒論に取り組む人が多い。
・1月上旬が提出期限で、2月上旬には口述試験も行われる。
入る前の想像と実際
・大学生らしい「必修科目」が無かったことに驚いた。
・思った以上に放任主義。履修の組み方も個人の裁量が大きく、必修は卒論だけで、フィールドワークを全員がするわけでもない。卒論も教員から口出しされてガンガン進めていく感じではない。それにフィットする人もいればしない人もいると思う。
・3年次にゼミが無く、オンライン化もあって学科懇親会や対面授業も無いので、自由な半分、学科への帰属意識をやや持ちづらかった。
・学部教育が体系的(基礎→応用などの型がしっかりしている等)に決まっているわけではない。学問の基礎をしっかりやってから、というより教育学に関することを何でもやる方がイメージに近かった。
・とっつきやすいテーマで、特に東大生は語りやすいテーマなので、「基礎なんかいらない!」と思う人もいるかもしれないが、入ってみるとまだまだ知らないことだらけだった。
・教員免許を取りたい人にとっては、教育学部の認定科目と履修科目が被りがちなので、結構お得。(同学部他コースもその傾向)
選んだ理由/迷った学科
・当初はざっくり文か教育を見ていたが、「教育とジェンダー」を扱う学生団体を経て教育に関心を持った。官僚というキャリアを考え始め、政策などを学べるコースが良いなと思い、当コースを選んだ。自身が所属したその団体の活動領域が比較教育社会学コースに近く、そことは違う世界を見たかったことや、教職が取りやすかったのも大きい。
(文三→教育実践・政策学コース)
一般的なパターンも特段なく、官僚志望なので「政策学」というテーマに魅了された人、前期教養総合C系列「教育実践学概論」での当コース教員のオムニバス講義に影響を受けた人、学科の卒論テーマを見て決めた人、など。
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) | 3 |
| LINE | 有 |
| Slack | あるけど… |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | 少 |
・例年LINEグループはあるが、Slackワークスペースは学年による。
・Slackについては、2020年度進学者の代では、入っていない人も一定数おり、月1程度しか会話が生まれない。
・教員(コース主任)からはメールで連絡が来る。コースで男女1人ずつ連絡係を予め設けておき、2人を通じてLINE等で情報共有される。
・教育学部出身者の同窓会のようなグループはあり、文科省官僚や学校教員などの講演会が行われることもある。
・コース内での学年上下の繋がりはそれほど無い。教育心理学コースや比較教育社会学コースのゼミに所属すると、そこで上下の関係は生まれる。
《ビフォーコロナ》
・学科同期同士の飲み会もあり、仲が良い。
・寝泊りできるレベルに整備された学科部屋があり、そこに入り浸る学生も多い。
・3Sセメスターが始まる4月に教育学部棟でコース内の教員&3,4年生で懇親会がなされる。そこで履修のアドバイスを頂くほか、教員・先輩との縦の繋がりが生まれる。
《アフターコロナ》
・飲み会・学科部屋での交流はあまり活発に行われていない。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 15名前後(※) |
| 成績評価 | 出席/レポート |
※概論系で他コースや他学部の人が大量に履修する授業では、100名以上になることもちらほら。
・全体的に出席が重視される。
・教員免許の授業と被るような科目は、出席票などを用いて出席を取る傾向。そのように出席点を取る科目は、出席と課題で6:4、5:5など。
・グループワーク講義が多く、グループごとに話した内容をまとめて提出することが多い。
・一般には出席3割で、期末レポートや小レポート毎回、といった形で、様々な機会で評価がなされる。
・期末試験を課す科目はあまりない。
・レポートが中心なので、シケプリを作る文化自体がそもそもない。
研究室・資料
特別な制度・その他
履修科目の関係上、当コースでは教職に加えて、社会教育主事、学芸員、司書の資格が取りやすい。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部

教育学部
教育についての専門的な研究と教育、教育に関する専門職の育成、中等教育教職養成を目指す学部
関連記事

(PEAK)国際日本研究コース
教養PEAK 教養学科

A美学芸術学専修
A群(思想文化_美学芸術学)

Gドイツ語ドイツ文学専修
G群(言語文化_ドイツ語ドイツ文学)
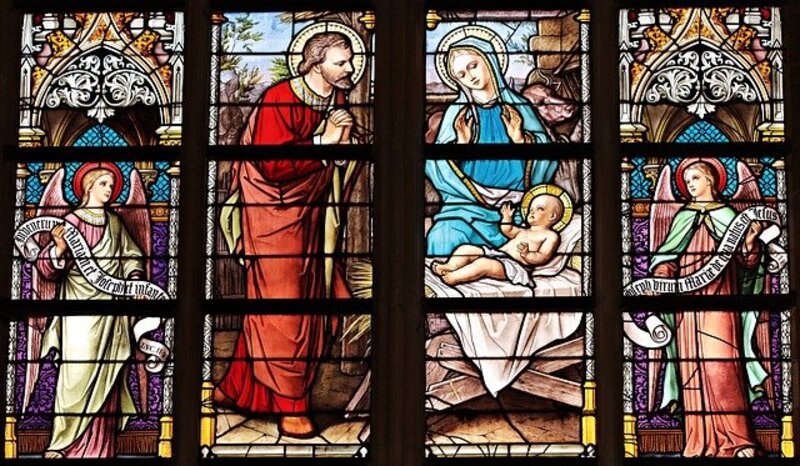
A宗教学宗教史学専修
A群(思想文化_宗教学宗教史学)




