文学部
A哲学専修
2023.4.15
A群(思想文化_哲学)
目次
基本情報
| 人数 |
20名 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
男性が多い。 |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
進路傾向は年によって大幅に異なり、就職:院進が半々の年もあれば院進する人がいない年もある。 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな学部?
教授3名・准教授1名・助教1名に加え毎年 2~3 名の非常勤講師を迎え、一方では長い歴史をもつ西洋哲学史の全体にわたり、また他方では哲学の諸分野にほぼ均等な比重をもたせた形で、授業を行っている。また、外国人研究者がしばしば訪れて、海外の研究にじかに触れる機会も豊富に持つことができる。
■学科の諸制度
卒業までに必要な単位は76単位。そのうち44単位が必修で、哲学概論、西洋哲学史概説第1部、同第2部の各4単位と、哲学特殊講義から12単位、哲学演習から8単位、それに卒業論文12単位である。
■進学定数は?
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 文Ⅲ(指定科類) | 40 | 9 |
| 全科類 | 9 | 12 |
文学部A群、思想文化コースとして、「哲学専修」「中国思想文化学専修」「インド哲学仏教学専修」「宗教史宗教史学専修」「美学芸術学専修」「イスラム学専修」を目指す学生は同じ群に志望を出す。指定科類(文Ⅲ)枠として全体の9割近くが埋まり、残りが全科類枠となる。
■進学前の注意点は?
哲学演習に積極的に参加するためには、英語の他に第二外国語やギリシア語、ラテン語を学習していると役に立つ。 また、前期課程において基礎科目の「哲学」「倫理」、総合科目「現代哲学」「記号論理学」を受講しておくことが望ましい。
■内実は?
初年次ゼミナール等前期教養学部での授業で哲学に興味を持つようになった人が半分ほどを占めており、中でも元々歴史に興味を持つ中で哲学に惹かれる人が多い。インターンや就活を積極的に行う人は少なく、本を読むなど内向的な学問をこのむ人が多い。
試験・レポートはそこまで重くないが、演習の予習は時間を要する。(例:デカルトのテクストを使う演習では一冊頭にいれておかないと議論についていけない。その日の担当者が決まっていて、担当箇所の翻訳をその場で発表しコメントする形で行っている。)
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 哲学的思考の射程 | 哲学概論II | 月曜2限 |
| ギリシア哲学史概論(2) | 西洋哲学史概説第一部II | 金曜2限 |
・持ち出し専門科目のみ記載
・週10コマ程度。
3年生Sセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 哲学の基礎 | 哲学概論I | 月曜2限 |
| ギリシア哲学史概論(1) | 西洋哲学史概説第1部I | 月曜3限 |
| 経験論の系譜(1) | 西洋哲学史概説第2部I | 水曜4限 |
・予習の重い演習が始まる。
・就活する人は一部始まる。
3年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 経験論の系譜(2) | 西洋哲学史概説第二部II | 水曜4限 |
・引き続き演習をメインに過ごすことになる。
・就活する人はその準備で忙しい。
4年生Sセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| Ch. S. Peirce:The Fixation of Belief | 哲学演習Ⅲ | 火曜2限 |
| 死生をめぐる実存哲学の諸問題 | 哲学特殊講義Ⅲ | m曜m限 |
・毎年、卒業年度の 7 月はじめの頃に卒論ガイダンスの機会を設け、教員が助言・指導等を行っている。
4年生Aセメスター
卒論の執筆を行う。
入る前の想像と実際
・思ったより演習の負担が大きく、自分の興味を自由に突き詰められるような環境ではなかった。演習の負担が多いため、講義には出ない人が多い。(理科一類→文学部哲学専修)
選んだ理由/迷った学科
・元々理系で、入学当初から歴史は好きだった。理系の勉強をしてはいたが抽象的な思考に魅力を感じ、科学の発展史などについて考えたくなり、文学部を選んだ。最初は宗教学専修を選んでいたがその後自分の興味範囲により近い哲学専修に変更した。(理科一類→文学部哲学専修)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) | 【4】 |
| LINE | 有 |
| Slack | 有 |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | 有 |
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 講義だと10-20名前後. |
| 必修は人数が多い。演習に関しては10人強ほど(※1) | |
| 成績評価 | 講義に関しては基本的に試験かレポートで評価される。出席評価はほとんどない。演習はそれぞれ評価は異なるが、出席と訳読、期末レポートの三つでの評価となる。 一回発表を担当すれば単位がくるものが多い。担当が回ってこない人に関しては担当したつもりでレポートが課される。他の演習は出席と訳読、期末レポートの三つでの評価となる。 |
研究室・資料
〈研究室紹介〉
鈴木泉教授(http://www.l.u-tokyo.ac.jp/philosophy/profsuzuki.html):西欧近世哲学ならびに現代フランス哲学
納富信教授 (http://www.l.u-tokyo.ac.jp/philosophy/profnotomi.html):西洋古代哲学(古代ギリシア世界における「哲学 (フィロソフィア)の誕生」)
古荘真敬教授:ハイデガー、人間的実存の本質構造に関する現 象学的探究
(以下多数)
特別な制度・その他
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
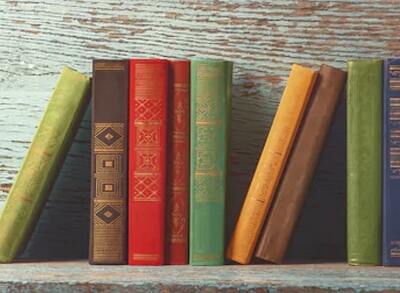
文学部
専門知識や幅広い視野を備え、異なる準拠枠を踏まえ自らの専門を相対化できる、高度な教養人として活躍する若者を育成する学部
関連記事

B日本史学専修
B群(歴史文化_日本史学)

地域 ドイツ研究コース
教養学科 地域文化研究分科

地域 ラテンアメリカ研究コース
教養学科 地域文化研究分科

G西洋古典学専修
G群(言語文化_西洋古典学)




