文学部
E考古学専修
2023.12.30
E群(歴史文化_考古学)
目次
基本情報
| 人数 |
10名弱 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性は0〜2割程度 |
| 要求/要望科目 |
・要求科目 ・要望科目 |
| 就活or院進 |
就職:院進=3:1 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな専修?
文学部人文学科歴史文化コース考古学専修では、土器や石器をはじめとした遺物や遺構などの考古資料の情報を読み取り、文字史料に依らない歴史像の再構築を目指す。各地域・時代の考古資料に関する文献や研究成果を活用した授業が中心。しかしモノを活用した歴史叙述という特徴から、資料整理などの実習活動も多いのが他の歴史学科とは大きく異なる点と言える。8月から開講される常呂研修施設での実習はその最たるものと言える。また学科以外にも総合研究博物館をはじめとした関連施設との関係も強く、各施設の教員による指導が多いことも特徴。
■考古学専修の卒業単位数
| 科目 | 必修科目 | 必要単位 |
|---|---|---|
| 史学概論 | 選択必修 | 2単位 |
| 考古学概論 | 選択必修 | 8単位 |
| 考古学特殊講義 | 選択必修 | 16単位 |
| 考古学演習 | 必修 | 6単位 |
| 野外考古学演習 | 選択必修 | 4単位 |
| 卒業論文 | 必修 | 12単位 |
| 他学部他学科科目 | 自由 | 28単位 |
| 卒業に必要な単位 | 76単位 |
■進学定数は?
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 文Ⅲ(指定科類) | 4 | 3 |
| 全科類 | 1 | 2 |
文学部E群、歴史文化コース。指定科類(文Ⅲ)枠として7割が埋まり、残りが全科類枠となる。
■内実は?
時代・地域を問わない学問であるため、学生の研究内容も千差万別。その一方で少人数の学科であることや実習の長さなどから学年を問わず学生間の交流は盛ん。
■進学前の注意点は?
「本郷に赴き、研究室訪問すると良い。二年生の五月に研究室訪問が可能になる期間があり、自分は石川先生(中国の青銅器が専門)からお話を伺った。研究室に加え収蔵庫で考古資料を見学させてもらい、進学後がイメージ出来た。法文二号館の地下一階はものすごく資料が豊富」
(文三→考古学)
「2Sでも歴史関係の授業を多く履修しておくと良い。必須ではないが、考古学では年代測定で理系の知識も必要なので、理系科目に興味を持つのも良いかもしれない。授業にとどまらず、博物館などで色々な考古資料にも触れておくのもオススメ」
(文三→考古学)
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■駒場と本郷、行ったり来たりの2A
| 科目 | 区分 | 開講曜限 |
|---|---|---|
| 考古学概論Ⅰ | 考古学概論Ⅰ | 火曜2限(本郷) |
| 史学概論 | 史学概論 | 金曜2限(駒場) |
| 人類学概説 2 | 考古学特殊講義ⅩⅢ | A2木曜5・6限(駒場) |
※持ち出し専門科目のみ記載
・週12コマ程度。
・以下に、必修・選択必修の授業の概要を示す。
考古学概論Ⅰ:
考古学の学史や理念、研究手法について学ぶ。月曜2限、本郷で開講。
他学科と合同ではないものの、受講者の過半数を他学科が占めることも。
学科の教授1人が講義を行う。
史学概論:
歴史学の理念・概要や手法について学ぶ。日本史学・西洋史・東洋史などの専修課程と合同で受講。火曜2限、駒場で開講。例年西洋史学の教授が講義を担当する。
考古学特殊講義ⅩⅢ:
猿人から新人に至るまでの人類の進化について学ぶ。必修ではないものの、受講が望ましい。理学部の「人類学概説」と同時開講。
A1タームの木曜4・5限、駒場で開講。
理学部の教授などによるオムニバス形式。
3年生Sセメスター
■北海道での実習がメインの3S
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 野外考古学 | 野外考古学Ⅰ | S2木曜 |
| 野外考古学Ⅱ | 野外考古学Ⅱ | 集中 |
| 博物館学実習B | 博物館学実習B | 集中 |
| 日本旧石器研究Ⅰ | 考古学特殊講義Ⅰ | 月曜3限 |
| 日本先史文化概説 | 考古学特殊講義Ⅲ | 金曜3限 |
| 民族考古学演習Ⅰ | 考古学演習Ⅰ | 火曜3限 |
※特殊講義、演習は他にも多数。
・週12コマ程度。
・演習(ゼミ)が必須。学生ごとに指導教員が開講するゼミを履修することになる。複数のゼミの受講も可能。
・「野外考古学Ⅰ・Ⅱ」について、他の授業に比べ拘束時間・期間が長くなることから3年次での単位取得が必要。
・後期課程から学芸員資格の授業の履修が可能となるが、先述の通り「博物館学実習B」が必修で資格取得に有利であるため授業を取る人も多い(学科の半分程度)。
・教員免許取得のための授業を取る人もいるが、学芸員資格と同様多くの科目の履修が必要となるため、綿密な履修計画を組む必要がある(3A以降も同様)。
・以下に、必修・選択必修の授業の概要を示す。
考古学概論Ⅱ:
「考古学概論Ⅰ」の続きで同様の形式の講義が行われる。
テキストも同じものを利用する。
野外考古学Ⅰ:
遺物の実測や拓本作成、測量など考古学研究で必要な手法を実践形式で学ぶ。
S2タームに2コマ連続で開講。
例年法文2号館の列品室や屋外での活動を行うものの、2020年度はオンラインの座学形式で講義が行われた。
考古学概論Ⅱ:
「北海文化研究常呂実習施設」に滞在し、「野外考古学Ⅰ」での学習内容を用いて遺跡の発掘や報告書の作成などを行う。
例年8月後半から2週間程度実施する。
考古学特殊講義Ⅶ:
縄文時代〜アイヌの出現までの北海道の歴史を考古資料を通して学ぶ。
「野外考古学Ⅱ」の前準備として、7月末に開講。
3年生Aセメスター
■演習を頑張る3A
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 日本旧石器研究Ⅱ | 考古学特殊講義Ⅱ | 月曜3限 |
| 日本先史文化概説Ⅱ | 考古学特殊講義Ⅳ | 金曜3限 |
※特殊講義、演習は他にも多数。
・週12コマ程度。
・ゼミが必須。
・3S以上に学芸員資格の授業が多いため、そちらを優先する人もいる。
4年生Sセメスター
■卒論の準備を始める4S
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 卒業論文(卒業論文指導を含む) |
・週6コマ程度。
・卒論の準備を行う。
・ゼミが必須。連続した6タームに渡り6単位の取得が必要となるため、3Sから順調に単位を取れれば4Sで必須単位は確保可能。
・就職活動以外にも夏の院試に向けた勉強を行う人もいる。
4年生Aセメスター
■卒論執筆に専念したい4A
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 卒業論文(卒業論文指導を含む) |
・週6コマ程度。
・卒論執筆、冬の院試の準備などが活動の中心。
・引き続きゼミに参加する学生もいる。
入る前の想像と実際
「イメージ通りだったのは、扱う領域が広いこと。『モノ』を扱えればokなので、地域や時代が限定されていない。ヨーロッパからアンデス山脈まで調査出来る。一方で想像より実習が少なかった。発掘、測量といった基礎的な技術を沢山学ぶイメージだったが、実際は各先生が研究されてきたことを座学で学ぶことが中心である。」
(文三→考古学)
選んだ理由/迷った学科
「地元で近くにあった古墳に関する博物館で『考古学面白そう!』と思ったのが原点。高校生の頃から考古学を志しており、考古学を学べる大学を探した結果、東京大学を選んだ。日本史学専修と少し迷ったが、最終的には文献の読解よりも遺跡や遺物の分析に魅力を感じ、そのまま考古学専修へ」
(文三→考古学)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
4~6 |
| LINE | 有※ |
| Slack | 無 |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | 有 |
※学部3年生から院生まで入る全体LINEと、同期LINEが両方ある。研究室関係の連絡事項など事務連絡の際にのみ動く。
・授業とは別途、「談話会」という集まりがある。院生や学部四年生の発表を教授陣と学部三年生が毎週聞き、質疑応答をする。
・夏休みに北海道の研修施設で実習がある。発掘後に食事会などの交流の機会がある。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 10名前後 |
| 成績評価 | 出席/レポート |
・原則座学だが、「野外考古学Ⅰ・Ⅱ」のような屋外実習に加え、ゼミによっては研究室の資料を活用し土器の水洗や注記といった資料整理を行うものもある。
・2020年度の授業はオンライン・リアルタイムのものが大半。但し「野外考古学Ⅱ」は現地での実習を行ったほか、Aセメではオンライン・対面併用のゼミや対面限定での座学も開講された。
・レポートでの成績評価が多い一方、授業で得た知識を問う試験形式での評価は少ない。
・前期教養に比べると成績は良くなる傾向がある。各授業ごとに勉強をしっかりすれば、撤退をしない限り単位は確保可能。
研究室・資料
〈研究室紹介〉
東京大学考古学研究室
福田正宏先生:先史考古学・東北アジア考古学
根岸洋先生:縄文・弥生時代の考古学
森先一貴先生:旧石器考古学・東アジア考古学
新井才二先生:動物考古学、西アジア・中央アジア考古学
特別な制度・その他
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
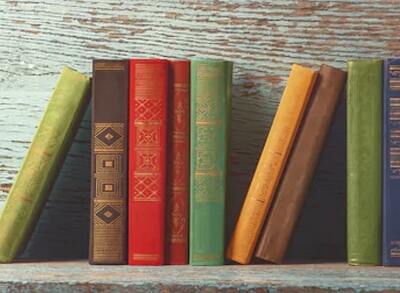
文学部
専門知識や幅広い視野を備え、異なる準拠枠を踏まえ自らの専門を相対化できる、高度な教養人として活躍する若者を育成する学部
関連記事

身体教育学コース
総合教育科学専攻 心身発達科学専修

超域 学際日本文化コース
教養学科 超域文化科学分科
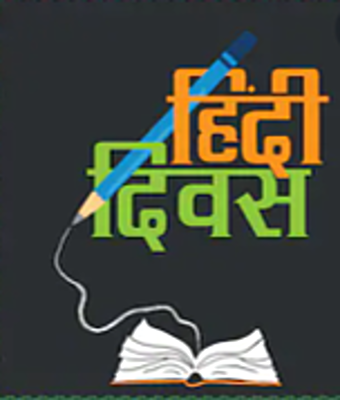
Gインド語インド文学専修
G群(言語文化_インド語インド文学)

Gドイツ語ドイツ文学専修
G群(言語文化_ドイツ語ドイツ文学)




