文学部
G中国語中国文学専修
2023.3.12
G群(言語文化_中国語中国文学)
目次
基本情報
| 人数 |
0~7名程。年により大きく変わる |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
母数が小さく年により大きく変わる |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
母数が小さく年により大きく変わる |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな学部?
研究・教育分野は、古典、現代文学、言語(文字・文法)の大きく三つ。テクストの背景にある中国語圏文化の特徴を丁寧に調べるという共通原則のもとに、甲骨文字から現代台湾映画まで幅広く扱う。学部は「読む訓練」、大学院は「文化的・社会的背景の考察」のイメージ。
中国語に触れながら、中国語圏の人々の情念に迫っていくことが魅力である。
また、国際色豊かな雰囲気やきめ細かい学部教育により、大学院に進学する学生も多い。また大学院には留学生のほか、他学科・他学部・他大学の出身者が多いことも特色である。(HPより)
■学科の諸制度
卒業までに必要な単位は76単位。必修科目単位以外は、他学部の単位を卒業単位に含めることができる。卒業論文を執筆することになる。
■進学定数は?
・定員数と各科類からの受け入れ数
※以下は、「文学部言語文化」の定員。中国語中国文学は、文学部言語文化の12専修の1つである。
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 文Ⅲ(指定科類) | 62 | 15 |
| 全科類 | 14 | 15 |
■内実は?
所属する学生には色々なタイプがいる。専門分野の学習に熱心な学生は毎日のように研究室や漢籍コーナー(専門の図書館)に通い、そうでない人も書籍や授業を通じて学ぶぐらいのことはする。学業以外以外に目を向けると、部活動に熱心に打ち込む学生や、長期のインターンシップに時間を割く学生、短歌や漢詩、小説創作などの創作活動を手掛ける学生などがいて、本当に多様である。
講義式の授業は少なく、ゼミ形式の授業が多い。負担は大きくないが毎週のように予習が必要で授業では発言を求められる。評価は、テストはあまりなく、基本的にレポート評価になる。授業中に発表が多い授業だとレポートも課されず発表内容で学期評価がされることもある。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
必修科目は存在しない。
印象に残った科目:「中国語学中国文学演習Ⅶ」
史記の遊侠列伝を原文、つまり漢文の白文で読むという作業が求められ、驚いた。句読点や改行もない文章なので、予習した内容の間違いを授業で直すことに必死だった。
授業以外での印象深い事柄:
持ち出し科目は大まかに中国文学を理解することを目的としている。
積極的に受講することがおすすめだという声も。
3年生Sセメスター
必修科目は存在しない。
印象に残った科目:「中国新文学大系講読」
中国現代文学の有名な作品を受講者で分担して翻訳する。現代中国語の読解力を高め、作品理解にも繋がるお得な授業となっている。
授業以外での印象深い事柄:
院生も一緒に受講する授業で、学部生の比率が低くなると授業の議論の難易度が上がりやすい。このことを認識した上で受講すると良いそうだ。
3年生Aセメスター
必修科目は存在しない。
印象に残った科目:「水滸伝を読む」
日本語でも多く出版されている水滸伝を原文で読み進める授業。日本語で読んだことがあると、白文読解力がさらに向上しやすいという声も。
授業以外での印象深い事柄:
この時期から大学院に進まないことを決めている学生は就職活動を始めることになる。
4年生Sセメスター
必修科目は存在しない。
印象に残った科目:「中国現代文学史」
文学史に関する英語の文献を読んで発表する授業。
発表担当会に必要となる予習の量には驚いたが、英語文献の読解力と中国現代文学史に対する理解が深まった。(文科三類→中文)
授業以外での印象深い事柄:
夏に卒論構想発表会があるので、卒論のテーマを決めて教授に相談しておく必要がある。
4年生Aセメスター
必修科目は存在しない。
卒論の執筆に専念することになる。
入る前の想像と実際
基本的には学科説明会の通りだった。大学院生には中国人留学生が多く、研究室が国際色強めだと感じた。厳しい教授だと予想していたが、どの教授も優しく、学生の置かれてきる状況(アルバイトで忙しい/部活に打ち込んでいる)にとても理解がある。
中文の開講数が少なく、他学部での授業で単位を獲得する必要がある。教養学部の中国現代文学や中国語演習などの授業も同時に受講すると学習の相乗効果があるだろう。
(文科三類→中文)
選んだ理由/迷った学科
中国についてより深く学べる学科だと考えたため。自分のルーツである中国への理解を深めたいと思い、大学入学時に第二外国語で中国語を選んだ。そして、授業外でも中国語/中国会話に力を入れて取り組み、中国語能力は高めることができた。
しかし当時は、あくまで中国語が上手な外国人でしかなかった。そこからより一歩踏み込んだ「日本人と中国人の中間」のような存在になりたいと思い、文学を通して中国人の思想を研究できる中国語中国文学専修課程を選択した。
(文科三類→中文)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
【3】 |
| LINE | 有 |
| Slack | 無 |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | 有 |
コロナ前は、研究室に行けば学部生も院生も誰かしらに会えるという印象。授業でわからなかった部分や、工具書(漢籍や原典一次資料を読んだり、先行研究を探したりするための辞書・辞典・目録類)の使い方について質問することができた。何かしらのお菓子が机の上に置いてあり、みんなで分けて食べることもあった。納涼会という飲み会もあったようだ。
コロナ後は、ランチを一緒に食べに行く程度。教授も参加するオンライン交流会が一度企画された。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 5~10名前後 |
| 成績評価 | 主にレポート |
レポートによる評価がメインとなる。出席数の成績への影響が明示されることはないが、授業の3割以上を欠席している人は見かけないそうだ。
研究室・資料
〈研究室紹介〉
研究室一覧
東京大学中国語中国文学研究室
特別な制度・その他
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
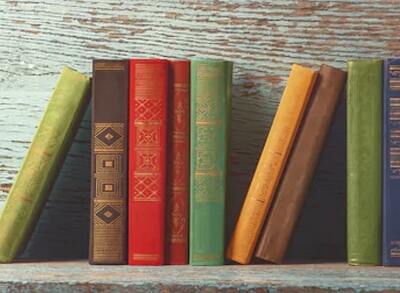
文学部
専門知識や幅広い視野を備え、異なる準拠枠を踏まえ自らの専門を相対化できる、高度な教養人として活躍する若者を育成する学部
関連記事

地域 イタリア地中海研究コース
教養学科 地域文化研究分科

地域 北米研究コース
教養学科 地域文化研究分科
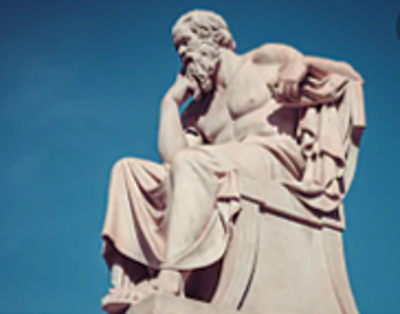
A哲学専修
A群(思想文化_哲学)

超域 表象文化論コース
教養学科 超域文化科学分科




