文学部
G南欧語南欧文学
2023.3.12
G群(言語文化_南欧語南欧文学)
目次
基本情報
| 人数 |
少数名 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
母数が小さく年により大きく変わる |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
母数が小さく年により大きく変わる |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな学部?
研究対象となる南欧語は、ラテン語から分化・発達したロマンス諸語のうち、イタリアから南仏・イベリア半島にかけて成立した諸言語を指し、イタリア語のほか、南仏のオック語、スペイン語、ポルトガル語などを含む。研究室の教育・研究の中心はイタリア語イタリア文学だが、ロマンス諸語全体に関わる講義や中世オック語文学、あるいはスペイン語スペイン文学などの授業も随時開講されている。
■南欧語南欧文学専修の諸制度
| 科目 | 必修科目 | 必要単位 |
|---|---|---|
| イタリア語学概論、イタリア文学史概説 | 選択必修 | 8単位 |
| イタリア語学、イタリア文学特殊講義 | 選択必修 | 8単位 |
| イタリア語学、イタリア文学演習 | 選択必修 | 16単位 |
| 卒業論文 | 必修 | 12単位 |
| 他学部他学科科目 | 自由 | 32単位 |
| 卒業に必要な単位 | 76単位 |
卒業までに必要な単位は76単位。そのうち32単位までは、他学科の授業を含めることができる。
■進学定数は?
定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 文Ⅲ(指定科類) | 62 | 15 |
| 全科類 | 14 | 15 |
■内実は?
少人数による輪読形式の講義が多いため、必然的に日常的に真面目に講義に参加するタイプの学生が多いと言える。また、現在研究室に所属する学生の大半が院生であり、学生達が持つバックグラウンドも多様。そのため研究室内の学生単位で何か行動するという機会は極めて少ない。その一方で少人数であるため、特に努力せずとも講義に参加するだけで全員と顔見知りになるので、個人的に研究室内の学生同士がコミュニケーションをとる機会を作る事自体は難しくない。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■【イタリア文学への導入】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| イタリア文学史概説Ⅱ | 選択必修 | 水曜4限 |
| イタリア語学イタリア文学特殊講義 Ⅲ | 選択必修 | 木曜4限 |
・イタリア文学史概説
イタリア語が俗語として成立する以前のイタリア詩について学べる。先生の丁寧な解説によって、中世のイタリアにおいて愛がどう捉えられていたのか、その姿を垣間見ることができる。
3年生Sセメスター
■【授業が本格化する3S】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 現代イタリア語の基礎知識(1) | イタリア語学概論 | 火曜3限 |
| イタリア文学史(1) | イタリア文学史概説Ⅰ | 水曜4限 |
| トルバドゥールの言語 | 南欧語圏言語文化特殊講義 | 水曜5限 |
| イタリア近現代文学散文講読 | イタリア語学イタリア文学特殊講義 Ⅱ | 月曜4限 |
| Letteratura moderna e contemoranea: poesia e critica (1) | イタリア語学イタリア文学特殊講義 Ⅳ | 木曜3限 |
| レオパルディを読む(1) | イタリア語学イタリア文学特殊講義V | 火曜2限 |
| 現代イタリアの女性作家フランチェ スカ・メランドリの小説を読む | イタリア語学イタリア文学特殊講義 VII | 木曜4限 |
| Letteratura moderna e contemoranea: prosa (1) | イタリア語学イタリア文学演習Ⅲ | 火曜4限 |
| Letteratuta del Novecento (1) | イタリア語学イタリア文学演習V | 金曜2限 |
| 騎士道物語詩研究 | 南欧語圏言語文化演習Ⅰ | 月曜3限 |
・南欧語圏言語文化演習Ⅰ
15世紀の詩人プルチの『モルガンテ』という作品を読む。教授の浦先生が重厚で隙のない解説をつねに提供してくださるため、古い時代のイタリア語への親しみがしだいに湧いてくる。
・院生の方々に対しては厳しさを見せることも忘れない教授だが、学部生には容赦してくださる場面も多く、恐れる必要はない。
3年生Aセメスター
■【単位を取り切る3A】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 現代イタリア語の基礎知識(2) | イタリア語学概論Ⅱ | 火曜3限 |
| イタリア文学史(2) | イタリア文学史概説Ⅱ | 水曜4限 |
| ダンテ研究(2) | イタリア語学イタリア文学特殊講義Ⅰ | 水曜5限 |
| ルイージ・マレルバの短篇を読む | イタリア語学イタリア文学特殊講義Ⅲ | 木曜4限 |
| レオパルディを読む(2) | イタリア語学イタリア文学特殊講義VI | 火曜2限 |
| ボッカッチョ研究(4) | イタリア語学イタリア文学演習Ⅰ | 月曜3限 |
| リソルジメント期の文学 | イタリア語学イタリア文学演習Ⅱ | 月曜4限 |
| Letteratura moderna e contemoranea: prosa (2) | イタリア語学イタリア文学演習Ⅳ | 火曜4限 |
| Letteratutra del Novecento (2) | イタリア語学イタリア文学演習VI | 金曜2限 |
| Letteratura moderna e contemoranea: poesia e critica (2) | 南欧語圏言語文化演習Ⅱ | 木曜3限 |
4年生Sセメスター
■【卒論に向け準備する4S】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 卒業論文 | 必修 | 未定 |
・卒論(12単位)を除くと、4年次でなければ履修出来ないというような科目は存在せず、卒論以外の必修科目の扱いで特に差があるわけではない。
・卒論は12単位と単位数が大きいが、そのための特別な講義やゼミのようなものがあるわけではない。4S開始のガイダンス時に卒論執筆要綱のような冊子が配られ、そこに記されている執筆のルールに則って、 自らテーマを設定し、基本的には自主的に書き進める事になる。勿論その過程で教員達に質問アドバイス等を求める事は推奨されている。
・例年7月上旬頃に研究室内の学部生達が一同に会し、その段階での卒論の構想に関し教授や他の学生達の前で発表する機会がある。
4年生Aセメスター
■【卒論に取り組む4A】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 卒業論文 | 必修 | 未定 |
・10月中に正式に卒論題目を提出する。そして11月の中旬頃、中間報告という形で、10月に提出した卒論題目に則った論文執筆の進捗状況を教授の前で報告する機会が再度設けられている。
・院試では現代文は勿論、中世やルネサンス期の文章、更にイタリア語作文や文学史の知識まで幅広い分野の出題がなされるため、院進希望者は、作品の時代、及び散文か韻文かと言った形式に関わらず3年次から幅広く講義を履修し、イタリア語の原典に触れておく事が重要であろうと思われる。特に院試の直前期と卒論執筆の追い込みの時期が重なるため、その両立はそれほど容易ではない。進学すると決めたら早めに準備を開始する方が成功の確率は高くなると思われる。
入る前の想像と実際
おおむね想像通りで、満足している。(文三→南欧)
講義の多くが原典講読であるため、講義への参加には予習が必須。講義によっては相当な翻訳精度が求められるため、その負担は軽くないが、その一方で試験やレポートは存在しないか、存在する科目でもその負担はそれほど重いとは言えない。この専修課程における成績評価は概ね日常の講義における平常点でつくと考えてよい。経験上きちんと予習し講義に参加していれば単位の心配はない。逆に講義にあまり参加せず、テスト期間で帳尻を合わせる事を得意とするタイプの学生には不向きの専修課程であると言える。
選んだ理由/迷った学科
特にありませんでした。(文三→南欧)
特に他に迷った専攻は無かったが、イタリアを中心とするロマンス語文化圏の諸問題を文学というフィルターを通して考える事に関心があったため、教養学部のイタリア地中海コースや、美術史学、西洋史学など、隣接分野の講義には進学後も積極的に参加していた。
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
6(※1) |
| LINE | 無 |
| Slack | 無 |
| オフラインでのつながり | 有(※2) |
| 上下のつながり | 有(※3) |
(※1)院生も含めた数値。
(※2)コロナ後に、研究室内で院生の方々とお会いする機会を設けた。
(※3)院生と共通の読書会に参加したり、メールにおいて学習面での助言を院生から頂いたりすることができている。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 3名前後(※1) |
| 成績評価 | レポート |
(※1)院生を含む
研究室・資料
〈研究室紹介〉(一部)
特別な制度・その他
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
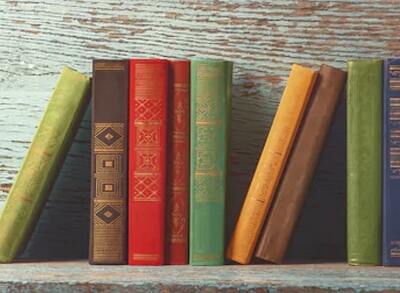
文学部
専門知識や幅広い視野を備え、異なる準拠枠を踏まえ自らの専門を相対化できる、高度な教養人として活躍する若者を育成する学部
関連記事
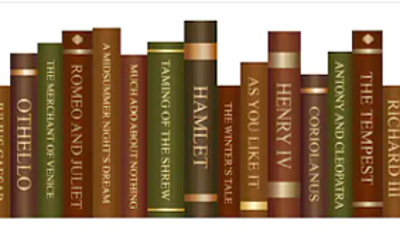
G英語英米文学専修
G群(言語文化_英語英米文学専修)

地域 イタリア地中海研究コース
教養学科 地域文化研究分科

地域 ドイツ研究コース
教養学科 地域文化研究分科

A美学芸術学専修
A群(思想文化_美学芸術学)




