教養学部
地域 ドイツ研究コース
2023.4.15
教養学科 地域文化研究分科
目次
基本情報
| 人数 |
3名程度 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
少人数のため、年によって異なる |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
就職:院進 = 4:6 程。航空会社や外資系など、国際的な仕事をする人がやや多い。 |
| 公式サイト |
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/academics/fas/dhss/ask/germany/ |
学科概要
■どんな学部?
ドイツ語圏を多角的に研究する学科。現近代ドイツの歴史,政治,思想・文化,近世ドイツの歴史と思想に重点があるが、自らの関心に基づいて自由に研究テーマを選ぶことができる。
■学科の諸制度
卒業までに必要な単位は76単位。卒論はドイツ語で執筆する。卒論の指導では日本人教員とドイツ人教員が協力するという体制ができている。
■進学定数は?
・定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 文Ⅰ,Ⅱ(指定科類) | 8 | 3 |
| 文Ⅲ(指定科類) | 12 | 6 |
| 全科類 | 2 | 2 |
※上記は教養学部教養学科地域文化研究分科の定員数。
■内実は?
様々な学生がいるので一概に言えないが、勉強や研究に熱心で積極的な人が多い。サークルなどで珍しい活動をしている人も。ドイツ科ということもあり音楽に関心の強い人が多く、楽器を弾ける人も多い。
■各コースの違い
教養学科の中でも地域文化研究分科は、ある特定地域についての研究を行う分科である。そのアプローチは文系のものには限られるが、政治・歴史・文学・言語など様々で、それらを組み合わせることも可能。その地域のことならなんでも研究できる、といったイメージ。
地域文化研究分科の中でも小地域に分かれている。ドイツ科はその名の通りドイツについて学びたい人たちが集まる。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
必修は定められていない。
ドイツ語を第二外国語としていなかったり、前期課程であまり力を入れてこなかった学生にとっては、はじめの数ヶ月は大変な思いをする可能性が高い。それでも着実に力をつけられるドイツ語の授業が多数開講されている。
・印象的な授業
ドイツ語で書かれた政治学の入門教科書の輪読。毎週膨大な予習量をこなして授業に臨まなければならずはじめは大変だが、続けていくと次第にそれが苦ではなくなり、語学面での成長を実感できる授業となる。
・授業外で印象的なこと
新入生歓迎会では大学院の先輩も参加するなど、縦のつながりは強い。普段のゼミでも院生と一緒になる事が多いので、学部生のみを対象にしたゼミ以上に成長を実感できる(もちろん教員は学部生に配慮してくれる)。
3年生Sセメスター
必修は定められていない。
・印象的な授業
ドイツ文学のテキストの輪読。これまで読んできたアカデミックなドイツ語とは違い、近代文学独特の堅いドイツ語に触れることができる。参加した学生が少ないと(二人の年も)、テキストだけでなくその周辺のことについても議論したりすることができる。
・授業外で印象的なこと
2Aまででドイツ語の力を伸ばし余裕が生まれると、教養学科の他の分科の授業や文学部の授業など、専門外の授業も履修したりして幅広く知見を蓄えることができる。それでも「試験やレポートに追われて大変」という事態には比較的なりにくいため、適度に忙しい中で自分の興味に合わせて最大限に学びたいことを学べる期間になるだろう。
3年生Aセメスター
必修は定められていない。
・印象的な授業
2Aで開講されているドイツ政治の輪読授業(年によって内容は少し異なる)をもう一度履修する学生もいる。2Aの際にはとても苦労した授業だったのに一年経つと全く大変さはなく、一年間でこんなにも読めるようになったのかと驚いたという声も。
・授業外で印象的なこと
ドイツ科でクリスマス会を開催する年もある。その際には、教務補佐が美味しい料理を用意してくれたり、楽器演奏などのちょっとした出し物があったりと、教員や他学年の学生も多く集まって和やかな楽しい会になったそうだ。
4年生Sセメスター
必修は定められていない。
必修ではないが、基本的には卒論指導とドイツ語論文(卒論を書くための授業)を取ることになる。
卒論をドイツ語で書くコースなので、その準備のために共通ドイツ語(論文)という授業がある。具体的には簡単なドイツ語作文に始まり、アカデミックなドイツ語論文の作法などを実践的に学んでいく。毎週課題があり、それを積み重ねることでなんとかドイツ語で論文を書くということをイメージできるようになる。
コロナ禍でほとんど研究室との関わりはなくなってしまったが、オンラインのゼミが行われ、近況報告会なども軽く開かれている。人との繋がりがどんどん希薄になっていた時期だったので、久しぶりに研究室の先輩や先生方と画面越しにでも会える機会があったのは学生にとっても嬉しいことだったようだ。
4年生Aセメスター
4年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 卒業論文 | 必修 | 年度により異なる |
| 卒論指導 | 必修 | 年度により異なる |
| 共通ドイツ語(論文) | 必修 | 年度により異なる |
4Aはひたすら卒論を書く。卒論指導では指導教官に、共通ドイツ語(論文)ではネイティブの先生に卒論を指導してもらう。
月に一回程度指導教官と面談をして内容の方向性を固め、実際に書いたドイツ語の文を、共通ドイツ語の授業としていつでも好きな時に添削してもらう。
ドイツ語で論文なんて書けるわけないと初めは思っていたが、この手厚いサポートのおかげで書き上げることができたという声も。
・授業外で印象的なこと
感染対策を行いながら、新入生歓迎会が対面で行われた(2021年)。
新入生とも顔を合わせることができ、親睦を深める機会となった。
入る前の想像と実際
・「ドイツのことならなんでもできる」と聞いてたが、所属している先生は政治・歴史・文学なので、一定の制約はある。しかし、非常勤で来られる先生方の専門は多岐に渡っているため、基本的には自分の関心に合った授業や先生を見つけられると考えてもよいだろう。
・想像以上に留学へのサポートが手厚いことに驚いた。ドイツ科と強い結びつきのあるDESK(東京大学ドイツ・ヨーロッパ研究センター)という東大の組織から潤沢な奨学金を受け取ることができる場合が多いため、短期長期問わず留学へのハードルが低い。また東大のプログラム以外にも、DESKのプログラムでドイツに渡航するチャンスも複数与えられている。留学を考えている学生には最適な環境だろう。
・学部生だけの授業を受けるのかなと思ってたが、ドイツ科のコース科目の多くは大学院科目との合併で、院生と一緒に受ける授業が半分ほどだった。しかしそれは難しすぎるということを必ずしも意味するわけではなく、院生と共に授業を受けることで数年後のあるべき姿を描くことができ、先生や先輩の手厚いサポートの下実力を伸ばしていくことができるので、非常に恵まれた環境だなと感じている。
・ドイツ語の授業とドイツ科のコース科目の履修が主(6割ほど)ではあるが、想像していた以上に履修を自由に組むことができた。英語ドイツ語以外の語学や他地域他学科の授業、文学部や法学部の授業、理系分野の集中講義など、興味のあることはなんでも手を出すことができ、そうしていても特に大変すぎることはなかった。この履修の高い自由度は魅力的な部分だと思う。
(文一→ドイツ科)
選んだ理由/迷った学科
文学部西洋史学科と迷った。
「自分のやりたい時代と地域を専門にしている先生がドイツ科にしかいなかった」というのが今の学科を選んだ一番大きな理由。先生三人に対して学生が多くても三人程、という手厚い環境だったことも理由の一つ。ドイツに留学する際の奨学金が、他のどの地域よりも恵まれている。これもドイツ科を選択する理由の一つとなった。
一般には、文学部の歴史系、文学系と迷う人と、教養学部の国関や地域文化研究分科の他地域と迷う人が多い印象。迷う理由は人それぞれなので一概に言えないが、最終的には「ドイツをやりたいかどうか」で決める人が多いのではないだろうか。
(文一→ドイツ科)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
【3】 |
| LINE | 無 |
| Slack | 無 |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | 有 |
コロナ前は新入生歓迎会、クリスマス会、卒業祝いなど、折々で集まり小さなパーティーをしていた。これらはドイツ科の先生やドイツ科にゆかりのある先生、院生も多く参加する会となっていた。
コロナ後は、新入生歓迎会と卒業祝いを、食事なしの簡略化された形だが対面で行った。
繋がりがあるのは基本的にゼミの場となる。ゼミの内容によっては先輩にフォローしてもらうこともあるため、そういった繋がりがある。上にもあるように、折々の食事会などには必ず先輩も参加するため、かなり先輩との交流の機会は多い。卒論や留学についても相談に乗ってもらうことができる。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 2~10名程度 |
| 成績評価 | 出席/発表 |
成績評価については、基本的に授業への出席と発表が全て。授業によっては学期末レポートが課されることもあるが、試験が課されることはまれ。
研究室・資料
特別な制度・その他
サブメジャープログラムというプログラムがある。所属コースの主専攻だけではなく、他コースが提供する15単位程度の科目群を副専攻として履修する。修了生は卒業時に、卒業証書だけではなく、サブメジャー・プログラム修了証ももらうことができる。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部

教養学部
「学際性」「国際性」「先進性」を軸に、深い教養を基盤に従来の枠組み・領域を超えて新しい分野を開拓する人材を育成する学部
関連記事

I社会心理学専修
I群(社会心理学_社会心理学)
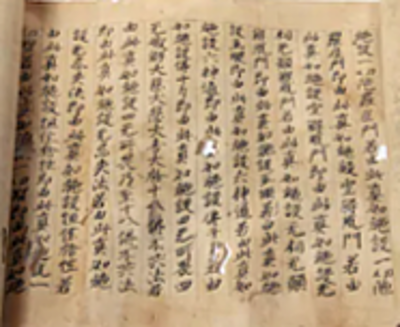
G国文学専修
G群(言語文化_国文学)

A倫理学専修
A群(思想文化_倫理学)

G中国語中国文学専修
G群(言語文化_中国語中国文学)




