文学部
G現代文芸論専修
2023.4.15
G群(言語文化_現代文芸論)
目次
基本情報
| 人数 |
6-8名 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
少人数学科のため、変化しやすい。 |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
母数が小さいので割愛 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな専修?
一国一言語の枠を超えて、欧米の近代を中心にしながらも世界の文学を広い現代的な観点から(日本文学も視野に入れて)研究することを目指す。
学生の多様な研究上の関心に応えるようなカリキュラム編成をしている。
「現代文芸論」という専修課程名はもっぱら<現代文学>を扱うということではなく、<現代的な観点からの>文学研究という意味であり、広く近現代文学全般が研究対象となる。
他専門分野(欧米文学および日本文学)の授業をかなりの程度まで自由に履修できる柔軟な制度(認定科目制度)が大きな特色。
■学科の諸制度
| 科目 | 必修科目 | 必要単位 |
|---|---|---|
| 現代文芸論概説 | 選択必修 | 4単位 |
| 比較文学概論 | 選択必修 | 4単位 |
| 近代語学特殊講義 | 選択必修 | 4単位 |
| 近代文学特殊講義 | 選択必修 | 8単位 |
| 現代文芸論演習 | 選択必修 | 8単位 |
| 近代語学近代文学演習 | 選択必修 | 4単位 |
| 卒業論文 | 必修 | 12単位 |
| 他学部他学科科目 | 自由 | 32単位 |
| 卒業に必要な単位 | 76単位 |
卒業までに必要な単位は76単位。そのうち32単位までは、他学科の授業を含めることができる。卒論は12単位。専修の科目で取得する44単位の内訳は、現代文芸論概説4単位、比較文学概論4単位、近代語学特殊講義4単位、近代文学特殊講義8単位、現代文芸論演習8単位、近代語学近代文学演習4単位、卒論12単位である。
■進学定数は?
・定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
| :---: | :---: | :---: |
| 文Ⅲ(指定科類) | 60 | 28 |
| 全科類 | 14 | 15 |
上記は文学部G群(言語文化)全体の定数。この区分ごとに進振りを行う。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
卒業論文執筆を除いて、必修は1科目もない。履修する授業は認定科目群の中から選ぶ。他専修開講も幅広く認定されるので、現文開講科目をどれくらいとるかは学生の裁量次第となる。
■印象的な科目
・現代文芸論演習(柳原孝敦)
一般的に、演習の授業では原文を扱うものである。しかし、ラテンアメリカ文学をあつかう柳原先生の演習は原典へ開かれながらも翻訳を底本にしており、特徴的。
・世界文学
社会やジェンダーを大きな視点で捉える科目。
・現代文芸論概説ⅠⅡ(阿部賢一)
翻訳論を扱うが、「対象によって翻訳の仕方が変わり、一つの正解があるわけではない」など、哲学系の内容を含む。参考までに、初めの課題は「”social distance”を、報道向けと小学生向けの二通りに訳す」というもの。
3年生Sセメスター
同上
3年生Aセメスター
同上
4年生Sセメスター
同上
4年生Aセメスター
必修:卒業論文
全ての学生が卒業論文を執筆する。7月に各自で決めたテーマを発表する。
過去のテーマの例としては、「ピランデッロ『作者を探す六人の登場人物』の翻訳論」、「テクストの存在論的、読者論的考察――円城塔『Self-Reference ENGINE』を題材に」、「テロという「悲劇」を描く―ジョナサン・サフラン・フォア『ものすごくうるさくてありえないほど近い』」等がある。
入る前の想像と実際
・印象は進学前後であまり変わっていない。
・「現代文芸論」を「文芸批評」と捉える人が多いが(現代への視点)、実際は世界文学と翻訳論の2つから成り立つ。日本語以外のものも19世紀のものも対象にできるし、同時代的な批評を専ら扱うわけではない。参考までに、ある学年では日本語を扱うのは1or2人/6人で、修士課程で日本語のものを扱っている人はあまりいないイメージ。
・興味対象が広くて絞れないという学生も来るし、興味対象が狭く他に学べる学科が無いために進学してくる学生も結構いる。
・言語やテーマが限定されない分、卒論の題材は学生の自主性による。研究したい対象が具体的に定まらないからという消極的な理由で選ばない方がいいかもという声も。
(文三→現代文芸論専修)
選んだ理由/迷った学科
美学芸術学/国文学/哲学/スラ文/表象文化論/法/建築などと迷った。何をするか予め決めたくはなかったが、言語芸術をやりたいということは決まっていたため。教員の専門性も考慮した。
一般には、文学部G群の英文・仏文・中文・独文・スラ文・南欧や、教養の比文・表象・言語態などと迷うことが多い印象。
(文三→現代文芸論専修)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
【7】 |
| LINE | 無 |
| Slack | 無 |
| オフラインでのつながり | 無 |
| 上下のつながり | 有 |
・世界文学というイデオロギーのもとに集まっているともいえる専修なので、研究室はひとつ、まとまり感がある。その点、メーリングリストで各種イベントの案内が回ってきたりする。院生は留学生の割合が高い。
・研究室では個人的な上下のつながりはある。コロナ前には毎年夏に合宿もあった。コロナ後にもつながりを確保しようと先生方も頑張ってはいるがあまり強い繋がりは築けていない印象。学生間で授業もそこまでかぶっていないことが一因か。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 概論:20名以上,特殊講義:10-20名,演習:5〜15名 |
| 成績評価 | 基本的にレポート。科目によって比重が異なる |
研究室・資料
特別な制度・その他
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
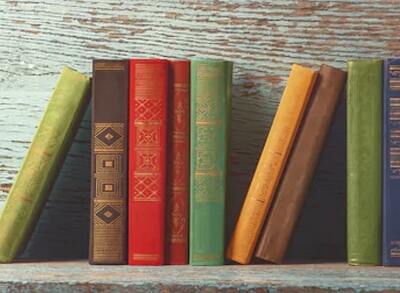
文学部
専門知識や幅広い視野を備え、異なる準拠枠を踏まえ自らの専門を相対化できる、高度な教養人として活躍する若者を育成する学部
関連記事

超域 学際日本文化コース
教養学科 超域文化科学分科

Gドイツ語ドイツ文学専修
G群(言語文化_ドイツ語ドイツ文学)

Aイスラム学専修
A群(思想文化_イスラム学)

F美術史学専修
F群(歴史文化_美術史学)




