文学部
I社会心理学専修
2023.4.15
I群(社会心理学_社会心理学)
目次
基本情報
| 人数 |
20-25名 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ8割 |
| 要求/要望科目 |
・要求科目 ・要望科目 |
| 就活or院進 |
就職:院進=5:1程度。 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな専修?
文学部人文学科社会心理学専修、通称「社心(しゃしん)」。
社会心理学は言うなれば、「心と社会を議論するためのプラットフォーム」。社会的な環境における人々の行動と、その背後にある心的過程、社会文化的な基盤との間のダイナミックな相互規定関係について研究する実証科学である。研究対象は、社会的状況の認知・理解やそれを支える情報処理過程、対人的行動、規範の形成やリーダーシップ、集団・組織行動、文化・歴史的な影響等と幅広い。
教育に関しては、実験や調査法を中心とする実証研究スキルの養成を重視。2,3年次に受講する調査実習や実験実習、統計を必修とし、仮説検証型の実証研究を集中的に学ぶ。卒業論文では、各自がオリジナルな仮説を検討するための実験や調査を行い、得たデータに基づき「社会の中の私たち」の心の仕組みや、社会現象に関わる社会心理学的要因の働きについて考察を行う。
1974年に研究室が設置された比較的新しい専修である。
■当専修の諸制度
| 科目 | 必修科目 | 必要単位 |
|---|---|---|
| 社会心理学概論 | 必修 | 4単位 |
| 社会心理学特殊講義 | 選択必修 | 12単位 |
| 社会心理学演習 | 必修 | 8単位 |
| 社会心理学実験実習 | 必修 | 4単位 |
| 社会心理学調査実習 | 必修 | 4単位 |
| 社会心理学統計 | 必修 | 4単位 |
| 卒業論文or特別演習 | 選択必修 | 12単位 |
| 他学部他学科科目 | 自由 | 28単位 |
| 卒業に必要な単位 | 76単位 |
卒業までに必要な単位は76単位。そのうち28単位までは、他学科の授業を含めることができる。卒論は12単位。
「概論」で4単位、「特殊講義」で12単位、「演習」で8単位、「実験実習」で4単位、「調査実習」で4単位、「統計」で4単位の修得が必要、卒論12単位を含めると、本専修修了に最低限必要な単位は48単位となる。
卒業論文による卒業を考えている者は、必修科目群には無いものの「実習Ⅲ、Ⅳ」を履修していることが望ましい。ただ、「実験実習」および「調査実習」を修得していない者は履修できないので注意。
■進学定数は?
定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 文理Ⅲ(指定科類) | 12 | 3 |
| 全科類 | 2 | 3 |
■卒論は?
・学部卒業論文(卒論)または特別演習レポートの提出が卒業には必須。
・4月頭(2021年度は4/2(金))に研究室ガイダンスが行われる。4名の教授が、それぞれ自分の研究内容を紹介する。数日間のうちに希望を出し(2021年度は4/5(月)が期限)、ほぼ希望通りに割り振られる。
・教員・院生を交えて、必修科目である「社会心理学演習Ⅴ(Sセメスター),Ⅵ(Aセメスター)」を毎週受講しながら、研究を進めていく。
・卒業論文は、社会心理学の特定のテーマに関してのデータ収集、或いは既存のデータを用いて結論を導き出すことが求められる。特別演習は、社会心理学の特定のテーマに関するこれまでの研究をまとめて、自分なりの結論を出すことが求められる。特別演習レポートの提出締切日時および体裁は、卒業論文に準じる。
・卒論および特別演習については、例年1月下旬~2月上旬に成果発表会を行う。
大まかな流れ
・4-5月:研究テーマ確定、関連文献の収集を行う。先行研究を検索し、それを踏まえて自分のリサーチ・クエスチョンを設定する。その問いに答える研究法についても考える。
・6-7月:研究計画を具体化しつつ、関連文献収集を進める。夏休み中のデータ収集が必要な場合、具体的な研究計画をリサーチミーティング(※)で提示・討論の上、許諾を得る必要がある。既存データの二次分析を行う場合もそれに準じる。
・8-9月(夏休み):研究計画の精緻化、データ収集に励みつつ、関連文献収集は依然進める。夏休み前に研究計画が確定した人は、1〜2週間を要する倫理審査を終え次第、データ収集に入る。計画策定中の人は、できるだけ早くの確定を目指す。
・10-11月:遅くとも10月中には倫理審査をパスし、データ収集を行う。結果の分析と考察を踏まえて、論文全体のストーリーを確定させる。
・12月:追い込み期。本格執筆、校正を経て、できれば12月初旬、遅くとも中旬までに第1稿を完成させる。
・1月:1月上旬(2021年度の場合、1/5(水))に卒業論文提出。1月下旬~2月初旬に卒業論文・特別演習発表会がなされる。
※リサーチミーティング:大学院生の研究相談や学会発表練習、またゲストスピーカーのトーク等の場として、週1回定例開講される。定期的に学部生の進捗報告の場も設けられるのが通例。連絡は基本的にメーリスで行われる。
※過去の卒業論文はこちらから。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■【最初にして最大の関門、2A】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 心理学統計法 | 統計Ⅰ(必修) | A金曜2限(駒場) |
| 心理学実験 | 実験実習(必修) | A火曜3-4限(本郷) |
| 調査実習 | 調査実習(必修) | A月曜3-4限(本郷) |
・週10~12コマ程度。
やや必修が多いセメスターなので、数はこれくらいに抑えた方が良い。
・3Sセメスターまで、必修として統計を受ける学生が一般的。3Aセメスター以降も、特殊講義なので必修では無いが、統計学を引き続き勉強していく人もいる。
・ガイダンスでは必修2科目(後述)から、「大学生活一番きついと思うけど頑張って下さい」と言われる。課題自体の量は非常に多いが、回を重ねるごとに効率よく課題をこなせるようになるので、平均6時間程度でできるようになる。
・「調査実習」と「心理学実験」(通称「実験実習」)が主。
・「調査実習」は毎回A4レポート1~2枚、「実験実習」は毎回8000字程度課される。
・「心理学統計法」が行われる金曜1コマのみ駒場開講。
・準必修も「心理学研究法」も駒場で行われる。
3年生Sセメスター
■【演習が始まる3S】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 心理学統計法Ⅱ | 統計Ⅱ(必修) | S火曜2限 |
| 社会・集団・家族心理学 | 概論Ⅰ(必修) | S火曜3限 |
| 社会行動の適応的基盤 | 概論Ⅱ(必修) | S水曜2限 |
| 社会心理学演習Ⅳ | 演習Ⅳ(選択) | S月曜3限 |
| 社会心理学演習Ⅱ | 演習Ⅱ(選択) | S水曜3限 |
| 社会心理学実習Ⅲ | 実習Ⅲ(任意) | S木曜2限 |
・多くて週12コマ程度。
・「演習」は3Sセメスターから4Aセメスター、全セメスターで履修しなければならない。「社会心理学演習Ⅰ~Ⅳ」は3年生対象の演習である。随って、当専修の学生はSセメに開講される演習2つのうち、どちらか一方を必ず履修することになる。
・上にあげた統計1つ、概論2つは必ず履修する。
・「特殊講義」は、「社会心理学特殊講義Ⅰ~Ⅴ」など当専修のものだけでなく、心理学専修・社会学専修からも履修することができる。
・「社会心理学実習」は、各研究室主導の研究プロジェクトに受講生が参加する形式で行われる実習授業である。大学院進学を検討している3年生の履修が推奨されている。
3年生Aセメスター
■【必修をほぼ取り切る3A】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 社会心理学演習Ⅲ | 演習Ⅲ(選択) | A火曜3限 |
| 社会心理学演習Ⅰ | 演習Ⅰ(選択) | A金曜3限 |
| 社会心理学実習Ⅳ | 実習Ⅳ(任意) | A水曜2限 |
・「演習」は3Sセメスターから4Aセメスター、全セメスターで履修しなければならない。「社会心理学演習Ⅰ~Ⅳ」は3年生対象の演習である。随って、当専修の学生はセメに開講される演習2つのうち、どちらか一方を必ず履修することになる。
・「特殊講義」は、「社会心理学特殊講義Ⅰ~Ⅴ」など当専修のものだけでなく、心理学専修・社会学専修からも履修することができる。
・3Aセメスターまでで、演習と卒論以外は取り切る学生が多い。
・「社会心理学実習」は、各研究室主導の研究プロジェクトに受講生が参加する形式で行われる実習授業である。大学院進学を検討している3,4年生の履修が推奨されている。Sセメスターは大学院生についていく感じだが、Aセメスターでは自分たち主導で実験調査を進めていく。
4年生Sセメスター
■【研究室に配属される4S】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 卒業論文 | ||
| 社会心理学演習Ⅴ | 演習Ⅴ(必修) | S水曜1限 |
| 社会心理学実習Ⅲ | 実習Ⅲ(任意) | S木曜2限 |
・3Aセメスターまでで、「演習Ⅴ,Ⅵ」と卒論以外は取り切った学生が多く、週1,2コマ程度が多め。
※「演習」は3Sセメスターから4Aセメスター、全セメスターで履修しなければならない。
・ただ、落とした不足単位の回収に励む学生も一定数いる。
・4月頭に研究室ガイダンスが行われる。4名の教員が、それぞれ自分の研究内容を紹介する。数日間のうちに希望を出し、ほぼ希望通りに割り振られる。教員・院生・学部生でリサーチミーティングを「演習」として毎週行っていく。
4年生Aセメスター
■【卒論を着々と進める4A】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 社会心理学演習Ⅵ | 演習Ⅵ(必修) | A水曜1限 |
| 社会心理学実習Ⅳ | 実習Ⅳ(任意) | A水曜2限 |
・「演習」は3Sセメスターから4Aセメスター、全セメスターで履修しなければならない。
入る前の想像と実際
・統計の勉強を思ったより一生懸命やらないといけない。
・専修は課題が多い等、かなりハード(部活やっている人は辞めないと持たない等)と聞いていたが、それほどでは無かった。実際2Aセメスターは忙しいが3Sセメスター以降はそれなりにやっていける。なんなら、自分で興味関心見つけて深めていかないと暇になってしまう。
・実験実習は心理学系統であるように、心理学・認知学に近い内容を思った以上に扱った。
・社会のニーズというより、自分の興味ベースで実験は進めるもの、という価値観の院生が多く、それに驚いた。
・「点数高いけど人当たり良い人が多い」と思っていたら、年によってはイカ東な学生が多く、それはギャップに感じた。とても真面目だしコミュニケーションが積極的なわけでは無いけど、基本は静かだけど物腰が柔らかい人たち。
※2020年度進学選択者に取材を行ったが、前後の代では、「点数高いけど人当たりが良い人」が相対的に多いとの声。年度によって変動が大きい。
(文三→社心)
選んだ理由/迷った学科
・底点が相対的に高いので、まじめで優秀な人が比較的多いと感じた。自分だけでなく周りもそういう人が多い印象。
・国際系団体で活動しており、日本国内や世界各地の文化の違い、人の雰囲気の違いに関心を持っていた。環境が個人に与える影響、個人が環境に与える影響、それぞれ双方向性を持って学べるのではないかと思った。後期教養とも迷ったが、文化人類学や表象文化論など、かなり抽象的、マクロな視点になってしまうと感じた。
(文三→社心)
・経済学部、文学部社会学専修と迷った。行動経済学系、心理学系に関心があり、総括して両方できるのは社心だと感じた。
・進振り点がそれなりに取れたので、せっかくなら底点がそれなりに高い所に行きたかったのもある。第一段階は83点程度、第二段階だと70後半でも行けるとか(※)。
※2020年度進学選択者の一意見です。ご参考までに。
(文三→社心)
・政治とかメディアとか世論に興味がある人が多い印象。法・経済に比べると、学問領域に深い関心を持っている人が多い。
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
3 |
| LINE | 有 |
| Slack | 無 |
| オフラインでのつながり | 無 |
| 上下のつながり | 有 |
・2019年度進学者までは、履修合宿みたいのがあったらしい。
・先輩との上下コンが1回だけ行われた。
・同期内で1名、パ長が置かれる。同期間の繋がりはパ長次第。
。演習では毎週zoomしたのもあり、同期との双方向的なコミュニケーション量は多い方だと感じた。
・教員と学生との距離感も近い。気軽に質問できるし、教員の方々の面倒見も良い。
・上下LINE、同期LINEそれぞれある。Slackは無い。
・学科部屋がある。4年生になってから行くもの、という雰囲気がある。行ってみると、いつもTAをされている院生など先輩方が多いので、3年生で行くと結構緊張するらしい。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 6-80名前後(※1) |
| 成績評価 | 出席/レポート/期末試験 |
※1:調査実習や実験実習は20~40名程度、選択科目は他学部・他専修も来るので80名前後になることも。一方で4年次の演習は6,7名くらいになる(※2)。
※2:3年生の演習は10数名ほどで、4年生の演習は4分割されるので6,7名ほどになる。
・2Aセメスターの調査実習と実験実習はレポートが非常に多い。演習系は、期末レポート等、最後に提出する成果物のため途中途中に課題を少しずつ提出していくことが多い。統計は最後の期末一発勝負。その他、大教室の科目は試験評価が多い。
・必修はきちんと出欠を取られる。遅刻しても単位修得はできる。ただ、1分遅刻でも-10点される等、キッチリ減点される。授業開始時点でレポート提出が必要な科目もそれなりにあり、そうした科目だと遅刻に敏感。
・期末一発勝負の統計は、出席がそれほど厳しくなく、切る学生も少しいる。
研究室・資料
〈教員紹介〉
なお、卒論指導教員となるのは、唐沢先生、村本先生、亀田先生、大坪先生の4方(検索結果順)。
唐沢 かおり先生(教授)
村本 由紀子先生(教授)
亀田 達也先生(教授)
金 惠璘先生(特任助教)
岩谷 舟真先生(助教)
大坪 庸介先生(准教授)
〈資料〉
学科ガイダンス資料
過年度の卒業論文
特別な制度・その他
社会調査士および専門社会調査士に関して、研究室ガイダンスなどを通じて資格案内がなされるが、実際に資格取得に向けて動いている学生は少数。
社会調査士の場合「統計Ⅱ」「実習Ⅱ」が、専門社会調査士の場合「応用多変量解析」が、それぞれ社心開講で資格認定に活かせる科目となっている。詳細は社会調査協会ホームページを確認のこと。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
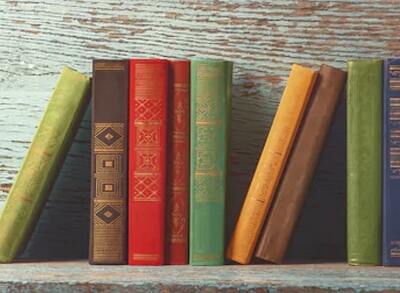
文学部
専門知識や幅広い視野を備え、異なる準拠枠を踏まえ自らの専門を相対化できる、高度な教養人として活躍する若者を育成する学部
関連記事

A中国思想文化学専修
A群(思想文化_中国思想文化学)

A倫理学専修
A群(思想文化_倫理学)

教育心理学コース
総合教育科学専攻 心身発達科学専修

G中国語中国文学専修
G群(言語文化_中国語中国文学)




