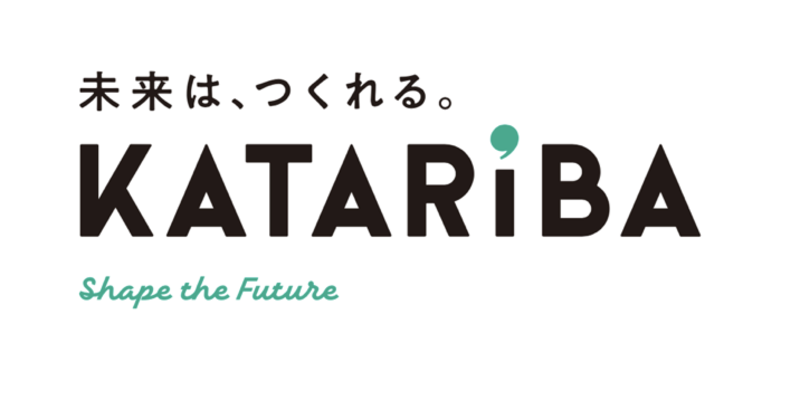■組織概要
「どんな環境に生まれ育っても未来をつくりだす力を育める社会」をビジョンとして2001年に設立された。
大学生・社会人が本音で語り合い、対話をすることで、「心に火を灯す」きっかけを高校生に与えるという「総合的な学習」の先駆けとなる事業を出発点としてスタート。
2011年の東日本大震災の際には宮城・福島・岩手の3県で放課後支援、学校外教育を開始し、子供たちの「自分で未来をつくろう」という思いを支えた。
今回の記事の中でインターン及びボランティア情報を紹介する「アダチベース」はカタリバが2016年に足立区からの委託を受けて開始した施設で、困難を抱えた子どもたちに真正面から向き合うことを掲げて活動している。経済的な事情をはじめとした様々な困難をを抱えた家庭の子どもたちが対象の学習支援・居場所支援事業を行う。
■活動の特徴
①子どもの支援を多様な角度から経験できる
アダチベースは教育に関する多様な事業を行っているNPO法人カタリバの事業部の一つなので、不登校児童の支援や被災地での居場所支援をはじめとした他の事業部の人と情報交換できる。また、都市部で家庭環境に困難を抱える子ども支援以外の課題に取り組む人とのつながりもできる。
ただし、この際には自分から機会を取りに行くことが大事である。他の事業部の人との情報交換や関係構築の機会は、インターン・ボランティアの総合窓口を担当している職員に自分から相談することで初めて実現する。
②自由度が高く裁量権が大きい!
似た活動を行っている他の団体では、決まっているカリキュラムをシステマチックにこなし、現場に落とし込む活動形式が多い。それに対してカタリバでは生徒に対して同様、スタッフの間でも対話が重要視される。ボランティア・インターンでも自分の意見を伝え、それが理にかなうものであれば受け入れられる土壌がある。(ボランティアとインターンで比較した場合はインターンの方が活動における裁量権が大きい)
③教育格差の最大の壁である「意欲」格差に挑む
経済的事情だけが生活の困窮を招くわけではないことを背景に、アダチベースでは「文化資本」(興味関心や資格、コミュニケーション能力など) と「社会関係資本」(頼れる人や友人) を育むことによる困難の連鎖の切断を目指している。家庭への経済的支援や学習支援だけに特化したピンポイントなアプローチでは「困難を抱えてた子どもたち」が孕んでいる問題の核には近づきづらいため、学習以外の面でも彼らと関わる仕組み作りである「複合的な教育支援」を行う。
しかし、近年教育格差の根本的問題として指摘されている「意欲」格差は、施設における教育支援で改善できる問題なのだろうか。アダチベースCentral拠点責任者の野倉優紀さんによると、目に見えない「意欲」格差の改善を考える上では、子どもにとってのロールモデルとなる人物が子どもたちのハビトゥス (※) に対して別の生き方や考え方を提示していくアプローチが重要だという。ロールモデルとの関わり合いのなか、子どもには日々の小さな成功体験を通じて「自分もそこ (ロールモデル) に近づいていきたい」という希望や憧れが生まれ、自己肯定感が育つのだそうだ。
「ロールモデルが一緒に手を引きながら歩いていく」という野倉さんの言葉がアダチベースにおける子どもたちとの関わり方、そして「意欲」格差に対しての向き合い方を象徴している。
※ハビトゥス (Habitus) :フランスの社会学者ピエール・ブルテューが「 (無意識の下に内面化される) 人生選択の根源的な考え方」として理論化した概念。