i.schoolは2009年に東京⼤学で始まったイノベーション教育プログラム。現在は東京大学から独立し、より開かれた教育を目指している。
本プログラムでは社会的課題を解決するアイディア創出法に焦点を当て、⼈間中⼼イノベーションを体系的に学ぶ。人間中心イノベーションとは、ニーズ起点で考え、未来に求められることから逆算して発想し変革を生んでいくことだ。その体得のために多様なアイディア創出法を体験できるいくつものワークショップが用意されている。これらの詳しい内容は「過去の事例」で紹介する。
通期で開催され、月に1回〜数回程度のペースでレギュラー・ワークショップがあり、年間で9回ほど提供される。修了要件は指定のワークショップに参加すること、かつ参加率が70%を超えていることである。なお、各レギュラー・ワークショップ長さについては合宿形式で密に行うものや、月に各回数時間で数回程度行うものまで色々ある。ベースとなる開催場所は基本的に赤門前のi.schoolのスタジオであるが、ワークショップによっては開催場所が山中湖寮だったり、企業施設だったりラボだったりと豊富である。
参加に関しては審査がある。2-3月に公式サイトおよびFacebookにて応募が始まり、書類審査、グループディスカッション、最終面接で毎年20名ほどが選ばれる。今までの修了⽣は160名以上であり縦横の繋がりは充実している。学部生・院生・社会人から募集を受け付けている。

i.school
学生向け
東大外部
2021.2.1
東大発のワークショッププログラムで、イノベーティブなアイディア創出法を学べる。
目次
基本情報
| 正式名称 |
i.school |
|---|---|
| 公式リンク | |
| カテゴリー |
ワークショッププログラム。イノベーティブなアイディア創出法について学ぶ。 |
| 対象者 |
学部3・4年生、院生、社会人が参加。東大生に限らない。社会人は学生もしくは企業からの派遣者が対象。学部1・2年生向けにはi.school ZEROという入門編のプログラムがある。 |
| 実施期間 |
通期で開催。年に9回個ほどの様々なワークショップを開催。 |
| 設立日 |
2009年 |
| 実施場所 |
本郷赤門前のi.schoolスタジオやその他の企業施設、研究室などで行われる。現在はオンライン。 |
| お問い合わせ方法 | |
| 参加方法 |
2-3月に公式サイトおよびFacebookにて募集がある。 |
| 審査有無 |
有り。書類審査、グループディスカッション、最終面接で20名ほどが選ばれる。 |
| 参加費 |
無料である。交通費などは実費負担。 |
過去の事例
i.schoolで行われてている具体的なワークショップの例をあげる。以下は2021年度の予定例である。
このように、様々なイノベーション創出方法を学ぶことができる。ワークショップによっては事前課題が出ることもある。記載の通り、各ワークショップは長さも色々である。
現在はコロナの影響でオンラインでの開催となっている。
ともすれば負担が重そうに思えるかもしれないが、就職活動と並行して参加する人もそれなりにいるとのことなので、興味があれば応募してみるといいだろう。
プログラムで学べること
多様な体験活動による様々なイノベーション発想方法が学べることが第一に挙げられる。
また、イノベーションのためのマインドセット、スキルセット、モチベーションの3点が体得できる。まず、ワークショップでアイディアを創造したり、グループファシリテーションを行ったり、コミュニケーションを取っていく中で自分以外との外の繋がりができ、イノベーションのためのマインドセットができていく。そして、ワークショップをこなしてスキルセットを獲得し、また様々な経験をつむことで自信がつき、モチベーションも上がるというわけだ。
また、大学内外で縦横の繋がりを得られることも魅力だ。OB・OGの人脈も得られ、先輩たちにインタビューする機会などもある。
本プログラムに向いている人
イノベーションを起こしたい人はもちろんのこと、方法論を知りたい人や、ワークショップを自分で設計して実行してみたい人におすすめである。
本プログラムに向いていない人
i.schoolのプログラムは事業化こぎつけまでまでは目指していないので、すでにやりたいイノベーションアイデアや起業アイデアがあり、それのアクセラレーションを期待する人には向いていない。i.schooでは課題を設定して、プロトタイプ、仮説検証する段階までが対象となる。
その他
選抜審査の詳細
i.schoolでは20名ほど参加者の選抜を行う。募集は公式サイトおよびFacebookで2-3月に始まり、書類審査、グループディスカッション、最終面接の3段階で選抜される。倍率は倍率は3~,4倍程度である。求められる人物像は、イノベーションを起こしたい人、円滑な議論が日本語でできる人、やりたいことがある人、また求められれば英語でのディスカッションに参加できる人である。プログラムのワークショップによっては事前課題が出ることがあり、かつ修了要件で一定以上の出席が要求されるのでどの程度コミットできるかも審査基準になる。
学部3・4生・院生・社会人学生から募集を受け付けている。実際の参加者は院生が一番多く、次に学部3年、4年生が多いとのことだ。なお、参加にあたりプログラミング、デザインスキルなどは要求されない。審査にあたっては多様性を重要視しており、たくさんの分野から選抜者が来るようにしている。
効果的な教育のためのシステムとツールの存在
議論の活性化のための様々な支援システムが存在する。
i.schoolでは創造力に人間の発想に関して学術的に積み上げられてきた知⾒に基づき効果的なワークショップを設計している。たとえば、ワークショップ中の笑顔の比率はディスカッションの活性度の相関関係があるという研究から、ワークショップ中の参加者の笑顔の比率を計測・分析し、それを元により議論が活性化するようi.schoolのファシリテーターやスタッフがアドバイスをして与えてくれる。
また、ワークショップ中の各チームの議論の様子をリアルタイムでみつつ、アイデアがより出るようにチームをスタッフが適宜サポートする体制が取られている。
このように議論が活性化するように支援するようによく考えられたシステムが採用されている。
独自開発のオンライン付箋バーチャルポストイットツール “APISNOTE”が議論の活性化と記録を支援する。
APISNOTE(アピスノート)は2009年にi.schoolが始まった当初から改良を重ねて開発してきたオンライン電⼦付箋プラットフォーム。これを用いることで、ワークショップのプロセスはすべて保存され、後から⾒直したり、研究に活⽤したりすることが可能だ。また、APISNOTEを使うことで遠隔からのワークショップへの参加も容易になり、ワークショップで実現できることの幅が広がる。
なお、この APISNOTE のサービスは公開されており、学生なら無料で、社会人なら一部無料で使用可能である。( https://www.apisnote.com/ )
トークイベント、「イノトーク」
ワークショップの他に、i.schoolでは、「⼩⼈数」かつ「カジュアル」な学びの機会として、「イノトーク」(イノベーショントーク)が開催される。イノベーションをキーワードとして、⽇本または世界の最先端で活躍する実務家や研究者を招き、プレゼンテーションをしていただく他、オーディエンスを交えたディスカッションが⾏なわれる。
i.schoolの体験版、ischool zero 【学部1,2年生向け!】
学部1、2向けに設計されたものである。実際1、2年生の受講が多いが、学部3年以上・大学院生にも門戸は開かれている。学部生がここから参加するのもおすすめだ。これは不規則に前期にやることがおおいようだ。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事

(学部1,2年生向け)NPO法人エンカレッジ東大支部
就活する東大生に対し、就活相談やメンタリング、自己分析や面接対策をサポートするNPO法人。

全学体験ゼミナール「ゲームデザイン論 ー先端技術が生み出す新しいあそびー」
人類にとって「あそび」とは何か、未来の「ゲーム」はどうあるべきかを考え、実践するゼミナール。

GCI (松尾研)
AIを研究する松尾研が運営する、国内最大のデータサイエンス及びマーケティングのオンラインプログラム。
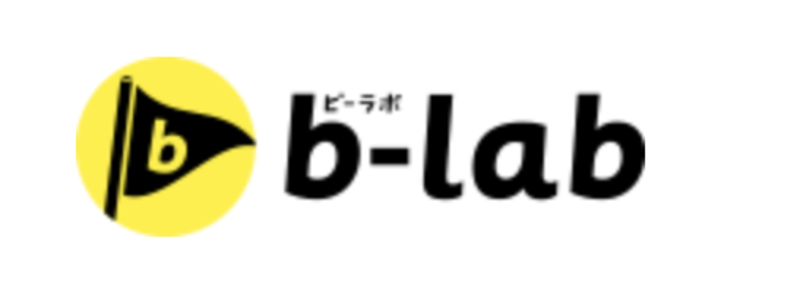
NPO法人カタリバ b-lab
NPO法人カタリバ運営の、中高生に向けて学校でも家庭でもない第3の居場所づくりを行う施設




