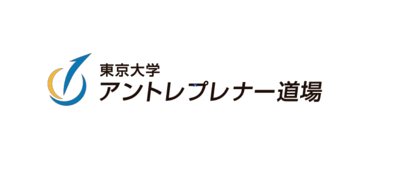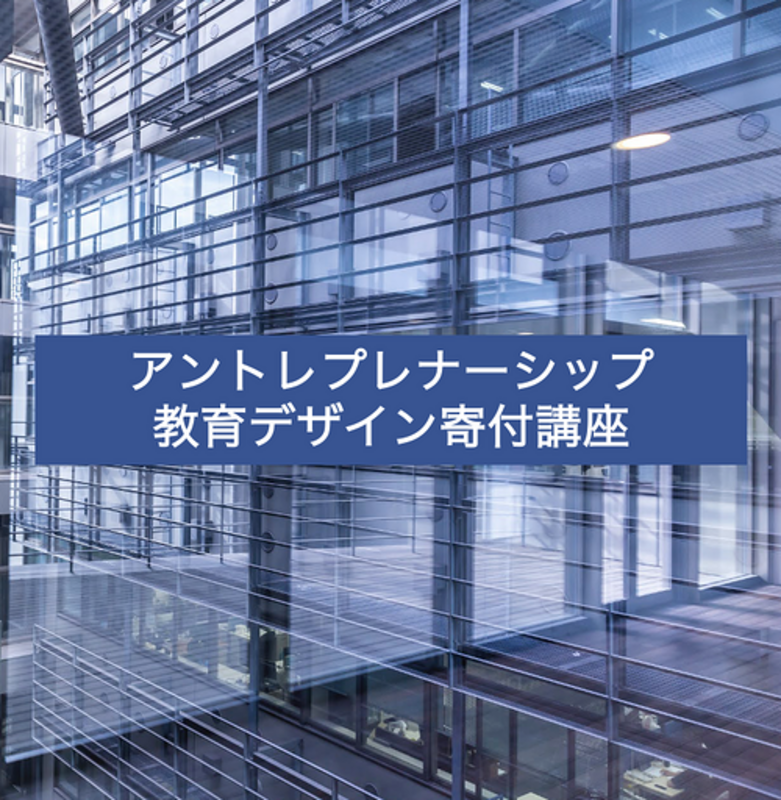参加者:Fさん(2018年度参加者・当時は理科2類2年)
Q:このプログラムでどんな活動をしていましたか?
ー 私がプログラムでやってきたのは、人口減少に苦慮する市で「大学生の関係人口を増やす」にはどうすればいいかという施策を考えることです。
時系列で振り返ると、4月にプログラムに応募して5月に合格通知が来ました。そして6月に活動地域が島根県雲南市に決まり、学内でのワークショップがあったり、他地域担当者との交流機会があったりと様々な準備が始まりました。夏と秋で合わせて3週間ほど、実際に雲南市役所に足を運び、他の時期はZoomなどのオンラインツールを用いて東京から市役所の方との協議を続けましたね。
市役所だけでなく、現地のNPO法人などとも連携して施策を考え、3月の最終報告会で現状の問題点を指摘し、「大学生の関係人口を増やす」ことに向けた改善策を提示しました。
Q:このプログラムで楽しかったことは?
ー 島根県との接点がなかったので突然地域に入り込めるかが不安でした。しかし、学内のワークショップで、「どのように地域の人と接するのが良いか」などのインプットがあったので、恐れることなく地域に飛び込むことはできました。
実際に、飛び込んだ先(島根県雲南市)では他の大学から地域に飛び込んだ学生もいたので、第三者でも地域のコミュニティに入れるんだということを実感しました。都市部出身の私には新鮮な体験でした。
Q:このプログラムで大変だったことは何ですか?
ー やはり1年や2年といった長い期間に渡って地域に参画するわけではないので、地域の意思決定を行ったり、意思決定に影響を与えたりしている人が誰なのかは釈然としませんでした。それに加えて、地域独特のしがらみもあり、話を聞きたい人に聞きに行けないことや地域の人の足並みが揃わないこともありましたね。
学生というフラットかつ外部の立場だからこそ、「街を活性化したい」という志がある人とは繋がる機会が多いものの、実際街の多くの人たちは「街の活性化」に対してどのように感じているのかをハッキリと理解することはかないませんでした。つまり、地域に入る期間が短く、あくまで外側の立場として関わることが理由で、地域の全体像が掴みづらかったのです。
Q:プログラムで得られた学びはどんなものですか?
ー 地域の活性化と一口に言っても、そこには様々な立場上の都合ありました。例えば、市役所は財政の観点から判断を行わなければならなかったり、頻繁に部署が変わったりします。「やりたいこと」よりも「やるべきこと」を優先しなければなりませんし、引き継ぎも入念に行わなければなりません。一方でNPO法人は、これから先も意欲ある人材に現地で働きたいと感じてもらえるように、活動の魅力を最大限に引き出し、アピールしなければなりません。時には必要以上に「見せ方」を考えなければならない時もあります。
このように、地域では色々な立場の人が、それぞれの視点で活動しており、利害調整が大変難しいことを知りました。また、政策はビジネスと異なり、地域で活動している人や暮らしている人たちの声を具に拾って行かねばならず、それぞれの価値観や正義の対立を乗り越えることに難しさを感じました。こうした経験から、私は「地域を見る目」が変わりましたね。様々な問題に対し、「自分の地域ではどうなのかな」と思うようになったり、旅行先などで「いいな」だけではなく、「この地域はどんな人が暮らしているのか、将来どう変わっていくか」など巨視的な目線で地域を見るようになったりしました。東京出身の学生にこそ、大きな学びがあるような気がしています。
Q:このプログラムを考えている人へのメッセージをお願いします!
ー 初めて訪れる地域に深く入っていく際、きっと戸惑いもあるかもしれません。しかし、一度やってみると「飛び込む」ことが好きになります。このプログラムを通じて、こうした積極性を備えたマインドセット(自分から行かないとダメだという気持ち)が身につきました。