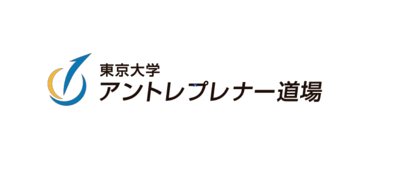概要
「これから100年経っても、地球上のあらゆるものと共生しながら生きていける世界」を実現するべく、他者を巻き込みながら新しい価値を創造できる科学者たちを「One Earth Guardians=地球医」と定義。大学で行われる講義に加え、企業や省庁から講師を招いたワークショップやセミナー、さらに産官学協働で課題に取り組む実学研修などを通して地球医の育成を目指すプログラム。
応募条件/アドミッションポリシー
・東京大学農学部、あるいは東京大学大学院農学生命科学研究科に所属する学生であること。※
・現在の地球が抱える問題に危機意識をもち、その課題解決に取り組む科学者になる熱意を持っていること。
・国際感覚を身につけ、他者を尊重しながら連携し、柔軟な思考力をもって課題を解決しようとする意欲を持っていること。
・自らの専門性を活かしつつ、同時に広範な学問分野を俯瞰し、サイエンスの相乗効果に結びつける力を持っていること。
※従来はこのような条件だったが、2022年4月に参加する第5期生は他学部からも若干名を募集する予定。One Earth Guardians認定に必要とされる認定科目の履修条件等については、個別に対応可能とのこと。
問い合わせ先
One Earth Guardians育成機構:office@one-earth-g.a.u-tokyo.ac.jp
住所:〒113-8657 東京都文京区弥生1-1-1 東京大学 大学院農学生命科学研究科 One Earth Guardians育成機構/One Earth Guardiansオフィス