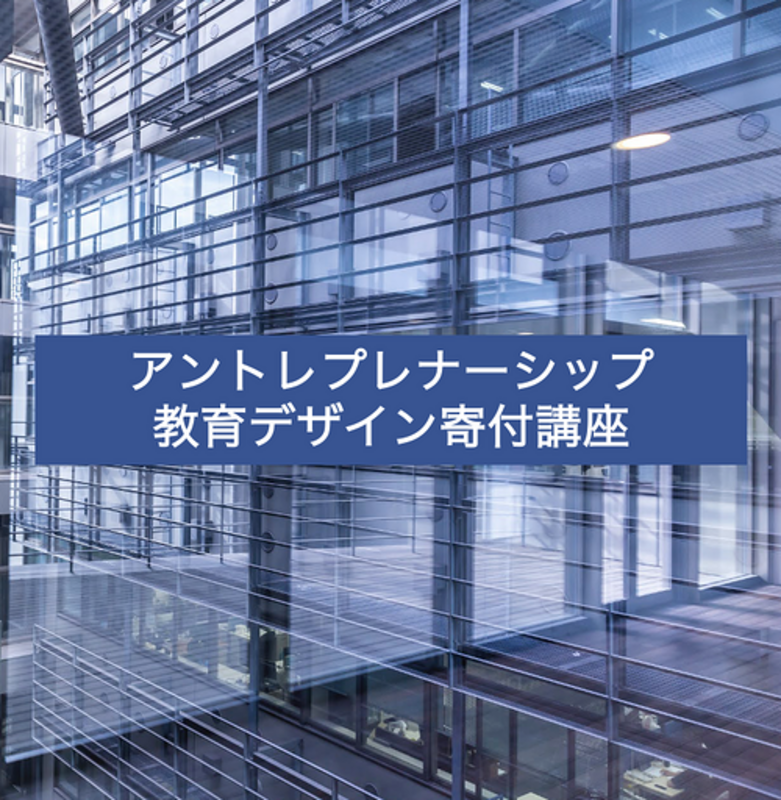プログラムの理念
東京大学発のベンチャーや日本国内のスタートアップにおいて、最新の研究成果を活かした科学技術の分野である「ディープテック」(※) における起業は少なく、十分なエコシステムも確立できていないことが課題として存在している。本講座は、そうした分野の研究と社会実装をつなぐ教育・起業モデルを確立するため、東京大学と複数の企業が連携して開講したものである。
※本講座が焦点を当てる「ディープテック」とは、①新規性・先端性、②産業へのインパクト、③グローバル展開へのポテンシャルという3つの要素を持つ技術のうち、特に大学のような研究室で研究される分野を指す。例としてはハードウェア・バイオヘルスケア・化学素材・環境エネルギー・宇宙開発などがある。
プログラムの概要
Sセメスターの全学体験ゼミナール (2単位付与) の形式を取ったアントレプレナーシップ育成講座。講義とフィールドワーク・発表とで全部で13回の授業が開講される。講座全体としてアウトプットを重視しつつもインプットとしては、東大の工学部教授陣・研究開発系起業家・寄付企業4社 (経営共創基盤、KDDI、東京大学協創プラットフォーム開発、松尾研究所) による講義が受けられることに加え、研究室や企業へのフィールドワークも行うことができる。また、毎週5限前後では生徒有志で懇親会が開かれたり、チームでの課題の提出が可能だったりするため同級生との横のつながりを深めることもできる。
プログラムの教育目標
講座を通じて、「東大にある技術を用いて、長期的にどのような社会の構築を目指せるか」、「長期的により良い社会を構築するために、東大にあるどのような技術の活用が考えられるか」、という問いに学生が答えられるようになることを教育目標としている。それに伴い、講座で求められる最終的なアウトプット (レポート形式) の内容は以下のようになる。
・自らの関心領域における、2050年における理想的な社会はどのようなものか。
・理想の社会の実現にあたり、どのようなテクノロジーが現状との乖離を解消しうるのか。
・当該テクノロジーを用いてどのような事業を展開するのか。
これらを学生個人、又は視座を同じくする学生間チームで練り上げることが当講座の最終目標といえる。
活動の様子