「アントレプレナーシップ」というと起業家精神と訳されることが多いが、本講義ではアントレプレナーシップをより広く「自らのコントロール可能な範囲を越えて好機とリソースを追い求め、社会の課題を解決することにより新たな価値を創造して維持可能な形で提供し続けること」と定める。よって本講義ではこれを実現するためのマインドセットと基礎知識を提供している。その際の具体的な教材として、起業を題材にしているのであって、学ぶ内容自体は大企業や公的機関、研究機関に属していても有用なものになっている。
本プログラムは講義形式の工学部共通科目「アントレプレナーシップI(S1)」「アントレプレナーシップII(S2)」と、ビジネスアイデアコンテストの「アントレプレナーシップ・チャレンジ」の3つにより構成される(年度によってプログラム数は変化することに注意)。詳しい内容は後述「過去の事例」で紹介する。
どのターム(および各タームの途中)からでも参加可能で、アントレプレナーシップI(S1)、II(S2)は水曜6限に本郷キャンパスの工学部の教室で開講される。現在はZoom開講だ。
受講者については、工学部共通科目であるが工学部以外の他学部や大学院からも受講可能だ。受講人数はアントレプレナーシップIが300-400人ほどで、アントレプレナーシップIIが200人ほどであり、夏休みのアントレプレナーシップ・チャレンジは6チームほどが選抜され参加する。工学部の学生がメインで参加しているが、他学部の学生も多く参加する。受講者は院生よりも学部生の割合が多いようである。
参加方法は公式サイトに掲示される参加フォームからの応募である。アントレプレナーシップ・チャレンジは参加に際し審査があるが、他のプログラムに関しては審査はなく、東大生であれば誰でも参加できる。
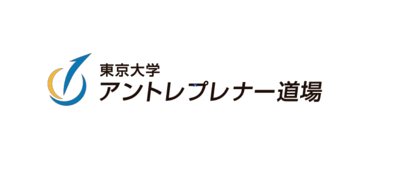
アントレプレナー道場
学生向け
東大内部
2021.9.10
東京大学産学協創推進本部が展開する3段階の起業家精神育成プログラム。
目次
基本情報
| 正式名称 |
東京大学アントレプレナー道場 |
|---|---|
| 公式リンク |
https://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/activity/venture/education/dojo.html |
| カテゴリー |
大学講義・ビジネスコンテスト |
| 対象者 |
東大生で学部不問である。起業に対し抵抗感がある学生こそ受けてほしい。 |
| 実施期間 |
S1,S2タームの水曜6限と夏休みに3つのプログラムを開講。 |
| 実施場所 |
通常は本郷の工学部の建物だが、現在オンラインで開講。 |
| 参加方法 |
参加は公式HPにあるフォームに加え、単位取得希望者はweb登録に加えてUTASから履修登録も必要。 |
| 審査有無 |
一部有り。アントレプレナーシップ・チャレンジのみ審査される。 |
| 参加費 |
無料 |
過去の事例
アントレプレナー道場は3段階のプログラムで構成されるので、ここでは各プログラムの詳細について説明する。
なお、どのターム及び途中からも参加が可能である。参加方法は公式HPに掲示される参加フォームに記入して応募する。単位不要者はフォームの登録のみ(履修届不要)で参加可能である。単位取得希望者はフォーム登録に加えてUTASから履修登録が必要となる。なお、アントレプレナーシップ・チャレンジは講義ではないので単位は出ない。
アントレプレナーシップI(S1ターム)は基礎知識習得のための座学形式である。
まず、アントレプレナーシップI(S1ターム)は基礎知識のインプットの「座学」が中心である。受講に際し審査はない。将来起業することになった時に知っておく必要がある基礎知識や考え方を講義形式で学ぶとともに、起業家をゲスト講師として迎え、アントレプレナーシップのマインドセットとスタートアップのアイデアについて学ぶ。受講人数は300-400人ほど。2021年度の講義内容は以下の通りであった。
(公式HPから引用)
アントレプレナーシップⅡ(S2ターム)は実践のための体験活動形式である。
次に、アントレプレナーシップII(S2ターム)はグループワークによる体験活動が中心である。受講の際にはチームに分かれ受講する。また、3週間で2回でチーム入れ替えも実施される。受講に際し審査はない。実際のスタートアップを進める上で必要なプロセスやアクティビティを体験を通じて学ぶ。なお、この時に行われる体験は顧客FB(ユーザーインタビュー)という意味上での「体験」であり、プロダクトづくりが主体という意味合いでの「体験」ではない。受講人数は200人ほど。講義内容の例は以下の通りである。受講の際にはチームに分かれ受講する。また、3週間で2回でチーム入れ替えも実施される。2021年度の講義内容は以下の通りであった。
(公式HPから引用)
アントレプレナーシップ・チャレンジ(夏休みから3ヶ月)はさらなる実践のための選抜式アイデアコンテストである。
最後に、アントレプレナーシップ・チャレンジ(夏休みから3ヶ月)はチーム制のビジネスアイデア・コンテストである。「アントレプレナーシップI(S1)、II(S2)」を受講していなくても、ビジネスアイデアとチームがあれば応募可能だ。本プログラムは40チームほどから6チーム程度が選抜される。テーマは解決すべき課題へのユニークな視点、これまで存在しなかった解決方法、大きな社会的インパクトを持った事業アイデアである。審査基準は課題の価値・解決策の価値・MVPによる検証度とトラクション・ピッチのうまさの4つの基準で5点満点の計20点だ。なお、応募時点ではほぼ全てのチームが各基準1,2点だそうなので、ブラッシュアップした後での得点の伸びしろを重視して評価されることがポイントとなる。
このプログラムではおよそ2ヶ月間、最終発表に向けてチーム毎にビジネスプランの作り込みを行い、各チームには、アントレ道場OB/OG起業家、プロフェッショナル・ファーム等の社会人が専属メンターとしてアドバイザーにアサインされると共に、選抜されたチームにはプロジェクト資金として各チームに5万円が配布される。最終発表で優秀な成績を収めると賞金(最優秀賞は20万、優秀賞は10万)が出る。
プログラムで学べること
まず将来どの分野に行こうが使うであろう、不確実な環境で生き抜く方法を体得できる。
加えて、得られるものとして学生同士の横の繋がりが得られることも挙げられる。毎週毎週顔を合わせる中で「面白そう」という人とつながれることは魅力だ。過去の例では一緒にスタートアップ創業や就職後のスタートアップ創業の事例がある。
さらに、時々外部のプログラムの参加枠の案内が流れてくる。
注意点として、よく誤解されるが、プログラミング技術や電子工作技術などのモノ作りの技術は学習対象ではないので本講義では学習しない。実際に本プログラムではハードウェアを作ったりプログラミングすることは課題としては行われない。
本プログラムに向いている人
起業や商品開発に一定の興味がある学生はもちろん、本プログラムは今現在起業に抵抗感がある学生こそ受けてほしい。なぜなら、起業など別世界の出来事だと考えている学生に起業を身近に感じてもらい、将来的な「キャリアの選択肢を広げてもらう」ことも本プログラムの目的の一つであるからだ。
また、プログラミングなどは使わないため、技術はないがこのような話題に興味がある学生でも参加できる。
一方ものづくりが得意な学生にも、本講義で行われるユーザーインタビューなどの体験は将来的に重要になってくると言えるので、受講はおすすめである。なお、ものづくりや開発が中心のプロジェクトに取り組んでみたい学生はSFP(Summer Founders Program)に挑戦するのがオススメ。また、ものづくりや開発プロジェクトを「ゼロから」学んでみたい学生はものゼミに参加してみるのも良いだろう。
本プログラムに向いていない人
他のメンバーとの共同作業があるので、コミュニケーションやインタラクションを極力したくない人にはおすすめされない。しかし、苦手でも挑戦・克服したい人は歓迎である。
その他
留意点:すぐの起業を促したり、モノ作りをするプログラムではない。
本プログラムは不確実性が高い今、「10年後20年後の変化した世界」で受講生が生き抜くことができるように教育する。なので、本講義は「直ぐ」に起業せよと促すものではないし、実際本講義終了後にすぐ起業する学生は稀である。しかしながら、卒業後の10年以内に実際に起業する例は多いとのことだ。その際に講義の受講生同士で創業することもあるという。このように本プログラムは、未来でその効果をじわじわと実感できるものである。
またプログラミング技術や電子工作技術などのモノ作りの技術は学習対象ではないので本講義では学習しない。なので、それらの技術に抵抗感がある学生でも受講可能である。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事

地方創生インターンTURE-TECH
ソフトバンクが主催するインターンシッププログラム。
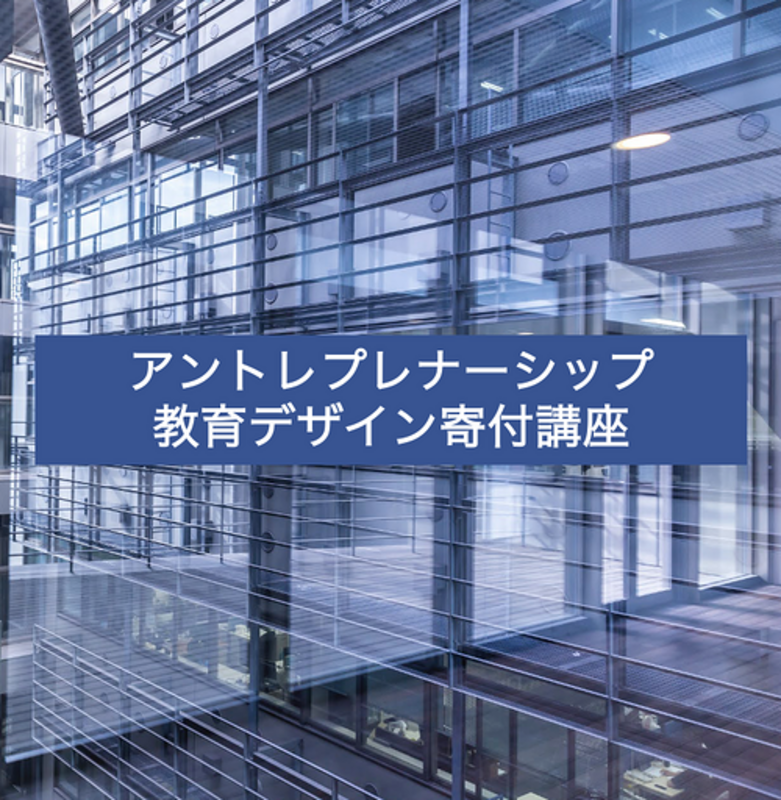
全学体験ゼミナール「ディープテック起業家への招待」
最新の研究成果を活かした科学技術の分野におけるアントレプレナーを育成する全学体験ゼミナールの講座。

MATLABアンバサダー主催 ワークショップ
高機能計算ソフトMATLABを幅広く学ぶワークショッププログラム。

(学部1,2年生向け)NPO法人エンカレッジ東大支部
就活する東大生に対し、就活相談やメンタリング、自己分析や面接対策をサポートするNPO法人。




