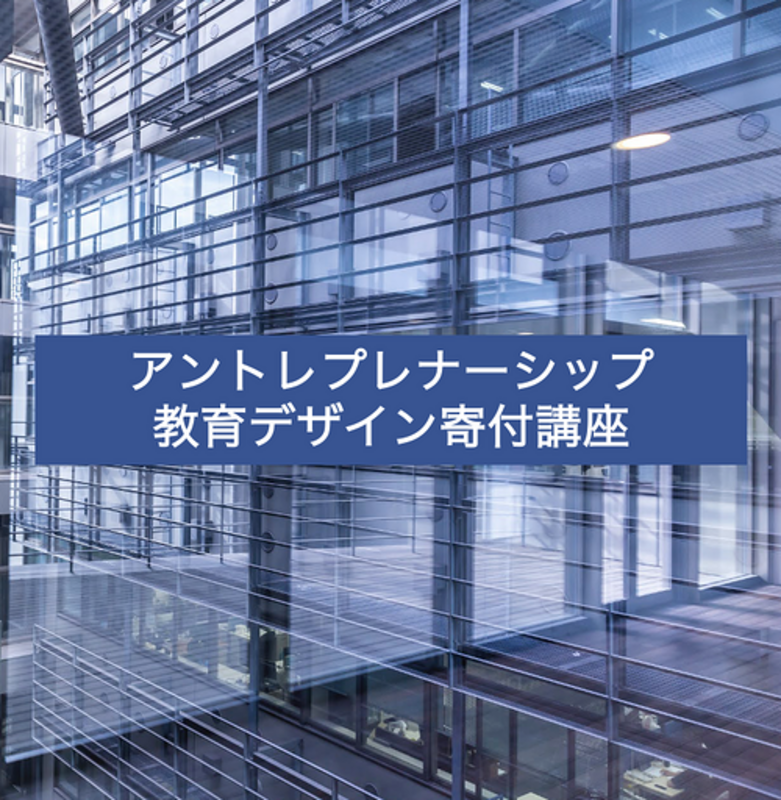UTokyo Global Unit Courses(UTokyo GUC)は、グローバルキャンパス推進本部が提供する海外の学生向けの短期受入プログラム。8つのメインコースと、海外の大学生を対象にした4つのコースで構成されている。各コースの参加者は10名~20名前後。東京大学の学生も参加することができる。受講修了者にはグローバルキャンパス推進本部が発行する「グローバル・ユニット」が付与される。
※グローバル・ユニットとは?
・国際総合力認定制度の活動として利用可能
・1ユニット:1回90分×10回=15時間 、0.5 ユニット1回90分×5回=7.5時間
・修了証明書を発行(所属学部等が認定する通常の単位の発行はない)
開講されるコースは以下の8つ
■Media in Japan and the World / Professor Kaori Hayashi (online, synchronous)
■Law in Transnational East Asia/ Professor Kentaro Matsubara (online, synchronous)
■Writings About Japan: Analyzing Cultural Representations, From Orientalism to Artificial Intelligence / Professor Yujin Yaguchi (on-demand, nonsynchronous)
■Group Theory and Its Applications: Introduction to Beautiful Modern Mathematics / Professor Yukari Ito (online, synchronous)
■Nanoscience / Professor Satoshi Iwamoto (online, synchronous)
■Sustainable Urban Management/ Associate Professor Kiyo Kurisu (online, synchronous)
■Early Language Acquisition: How Human Infants Learn Language Within Their Social Environment /Assistant Professor Sho Tsuji (online, synchronous)
■AI and Social Justice/ Professor Yuko ITATSU (online, synchronous)
他のプログラムとの違い
PEAKとUTokyo GUCの違いは?
PEAKは教養学部の正規の授業で、教養学部の単位や評価がついてくるのに対し、GUCは正規科目の外にあり、単位ではなくユニットが付与される。また、UTokyo GUCは有料。(ただし東大生は海外の学生の1/10の金額で受講可能。)正規の科目を優先した上で、課外活動としての受講を期待している。
UTokyo GUCの魅力
・身近:オンラインで日本から受講できる。従来型の留学とは異なる、学びを提供する「身近な」国際体験である。
・学生の多様性:東大生ではなく世界中の学生が集まってくる。PEAKの場合はサークルが一緒だったりと、色々共通している部分が多いが、UTokyo GUCの場合は世界中から学生が集まるから面白い。基本は学部生だが、博士課程学生の参加もあった。時差のため中国・アジア圏の学生が多かったが、欧州含む世界中から参加があった。