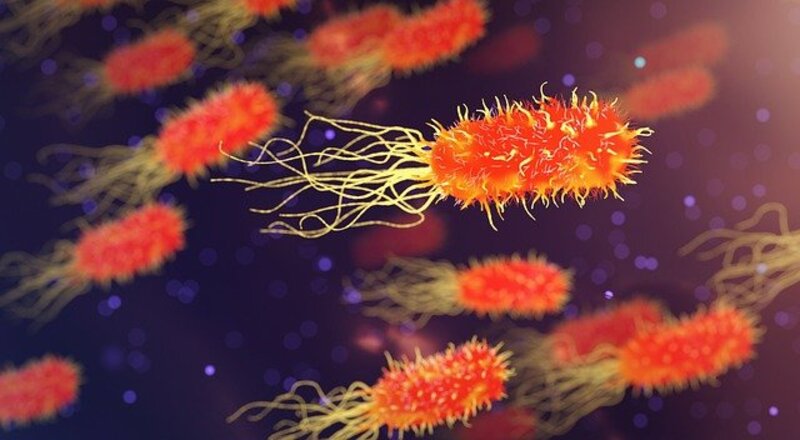はじめに
多くの東大生が頭を悩ませる意思決定である「進学選択」。
「〇〇に興味はあるけど、どの学科で学べるのかわからない」なんて思ったことはありませんか?
この記事では、そんな皆さんのお悩みに応えるべく、医学分野について学ぶことができる学科を「横断的に」比較紹介しました。
皆さんの選択を少しでも支えることができれば幸いです。
※本記事の内容は2022年度以前の情報に基づいています。現在記事を更新中ですのでしばらくお待ちください。
目次
医学部:医学科
概要
医学部は生命科学・医学・医療の分野の発展に寄与し、国際的指導者になる人材を育成することを目標とする。医学部のうち、医学科の特徴としては生命現象を明らかにするという基礎科学の面だけではなく、疾病の克服を通して人類の福祉に貢献するという応用科学の面の二面性を持つ。その研究は分子レベル(再生医療など)から社会レベル(公衆衛生学など)まで多岐にわたる。
基本情報
- 定員
- 医学科 110名
- 要求/要望科目
- 要求科目
- 文科各類
- 基礎科目「生命科学Ⅰ」か「生命科学Ⅱ」
- 基礎科目(基礎実験)「基礎物理学実験、基礎化学実験、基礎生命科学実験」から1科目
- 理科一類
- 基礎科目(生命科学)
- 理科二・三類生の「生命科学Ⅰ、生命科学Ⅱ」から1科目
- 文科各類
- 要望科目
- なし
- 要求科目
- 公式HP
カリキュラム紹介
2年(M0)Aセメスター
- 生化学
- 生化学・分子生物学の基本を身に着ける。
- 組織学
- 人間の臓器を個別にミクロに学習・観察する。
- FQ(フリークオーター)
- 各自の興味に基づいて研究室で研究を体験したり、病院に入って実際の現場を見学したり、日本の外に出て医療の実態を見聞したりできるように、M0とM1の春に一定期間の自由な時間が設けられている。
3年(M1)
- 解剖学
- 主に実習を通して人体の構造に関して学習する。実習では献体の解剖も。
- 微生物学
- 細菌やウイルスなどの微生物による感染症やその発症メカニズムについて学ぶ。
- 免疫学
- 免疫学の基礎的な知識技法について、講義や実習を通じて学ぶ。
- 生理学
- 生体機能の仕組みについて学ぶ。
- 薬理学
- 化学物質と生体の相互作用の学習を通じて、薬物に関係する研究・診断をするために必要な基本的知識・考え方を学ぶ。
- 病理学
- 遺伝子レベルから身体レベルまでの疾患について、疾患をベースとした座学と実習を交えて学ぶ。
- FQ
- 上記のFQと同様。
4年(M2)
- 系統講義
- 内科・外科・小児科などの診療科ごとに関連疾患について学ぶ。
- 臨床導入実習
- クリニカルクラークシップ以降で必要となる技能や態度、思考過程などの病院での実習で必要不可欠な基本的な臨床能力を身に着ける。
- 臨床実習前OSCE
- 判断力・技術力・マナーなどの臨床技能の習得を確認する試験。
- CBT
- 系統講義で学んだ知識を問う、コンピュータ上で行われる試験。
- 臨床実習前OSCEとCBTの両方に合格しないとクリニカルクラークシップに参加できない。
- クリニカルクラークシップ(1期)
- 5~6人の班で各診療科をまわり、実際の診療チームの一員として診察や診断、治療法を学ぶ。
5年(M3)
- クリニカルクラークシップ(1期続き)
- クリニカルクラークシップ(1期)の続き。
- クリニカルクラークシップ(2期前半)
- クリニカルクラークシップ(1期)と回る診療科が異なるが、内容は同じ。
6年(M4)
- エレクティブクラークシップ
- 1ヶ月単位で診療参加型臨床実習を行う。
- 東大病院以外にも学外施設や海外施設で実習が可能。
- 臨床研修マッチング試験
- 卒業後に臨床研修を行う学生と、それを受け入れる病院をマッチングする試験。
- クリニカルクラークシップ(2期後半)
- クリニカルクラークシップ(2期前半)の続き。
- 臨床実習後試験
- 臨床実習を終えたのちに行う、面接や模擬診療などの試験。
- 医師国家試験
その他プログラム
- PhD-MDコース(出典:https://square.umin.ac.jp/UTPhDMD/index.html)
- M2またはM3終了後に医学部を休学して博士課程大学院に入学するプログラム。
- 博士課程を卒業した後に医学部に戻ることも、そのまま研究者としての道を歩むことも可能。
- 早い段階から研究者を志すことを決めている学生のために設けられたプログラム。
- MD研究者育成プログラム(出典:http://www.ut-mdres.umin.jp)
- 通常の医学科の授業を履修しつつ、基礎医学の研究者に必要な素養を身につけ実践するプログラム。
- 研究室に所属しそこで研究活動を行うと同時に、このコースを履修している学生による活動(少人数ゼミ・英語・他大学とのリトリート・短期留学など)を行う。
- 臨床に進むことも研究に進むことも考えている学生にとって、二つを並列して体験・学習できるプログラム。
- 臨床研究者育成プログラム(出典:http://cr.umin.jp)
- 医学における臨床研究の重要性や臨床系研究者としての基本的な考え方について学ぶ。
- 週一回の全体レクチャーシリーズと少人数コースがあり、教員と履修者で議論を行う場も設けられている。
- 発展的には各臨床科で行う研究への参加も行う。
主な研究室紹介
- 衛生学教室(石川俊平教授・加藤洋人准教授)
- キーワード:バイオインフォマティクス・ゲノム科学
- 主な研究内容
- 体内の腫瘍を用いたがん細胞・がん環境の包括的な遺伝子解析
- がんに対する免疫の遺伝子解析と新規機能抗体の探索
- 腫瘍組織画像の解析のための深層学習技術の開発
- 研究室HP:https://plaza.umin.ac.jp/prm/
- 生体情報学教室(浦野泰照教授)
- キーワード:ケミカルバイオロジー
- 主な研究内容
- 光機能性プローブの論理的精密設計法の確立
- 新規化合物・プローブの開発とその生体への応用
- 開発したプローブの応用による生体内でのがんイメージング・治療
- 研究室HP:http://cbmi.m.u-tokyo.ac.jp
学科インタビュー
Coming Soon
学生の声
- 解剖を実際に体験できることが医学部の最大の魅力だと思います。緊張感も伴いますし、約2ヶ月にわたる解剖は、それなしにはあり得なかった身体に対する見方をもたらしてくれます。その他、第一線の研究者の方々から、生化学や免疫学などを学べることも魅力の一つだと思われます。
医学部:健康総合科学科
概要
医学部では生命科学・医学・医療の分野の発展に寄与し、国際的指導者になる人材を育成することを目標としている。医学部のうち健康総合学科は、ひとびとの生活にとって重要な構成要素である健康を軸に置き、幸福(ウェルビーイング)向上を目指す。
基本情報
- 定員
- 健康総合学科 44名
- 要求/要望科目
- 要求科目
- 文科各類
- 基礎科目「生命科学Ⅰ」か「生命科学Ⅱ」
- 基礎科目(基礎実験)「基礎物理学実験、基礎化学実験、基礎生命科学実験」から1科目
- 理科一類
- 基礎科目(生命科学)
- 理科二・三類生の「生命科学Ⅰ、生命科学Ⅱ」から1科目
- 文科各類
- 要望科目
- なし
- 要求科目
- 公式HP
カリキュラム紹介
2Aセメスター
- 健康総合科学概論
- 健康総合科学とは、環境生命科学、公共健康科学、看護科学などの「健康科学」分野について、自然科学・人文社会科学・実践科学を互いに結びつけながら、社会への実践的な貢献を目指す学問であり、ひとびとの健康を通じたウェルビーイングの達成を目的としている。
- 感染症
- 感染症学の基礎知識、院内の感染防御について学ぶ。キーワードとしては、細菌学、ウイルス学、外科と感染、内科と感染、医療廃棄物、針刺事故、消毒・滅菌と感染など。
- 健康心理学
- 心理学・行動科学の学問大系から、保健・医療・福祉に深く関連する諸分野の理論とその応用について学ぶ。キーワードとしては、行動科学、認知心理学、生理心理学、社会心理学(対人行動)、動機づけ、ストレス科学、発達心理学(生涯発達)など。
- 解剖学
- 授業は、大筋は人体の器官系統に沿い、日常生活の事例を用いて進められる。必要に応じ、器官系を越えて関連する機能や病態についても紹介される。
- 国際保健学
- 国際保健学(Global Health)が扱うテーマは地球規模での健康問題であるが、自然科学・社会科学にまたがる様々なアプローチがどのように問題解決に寄与するのかを、大学院「国際保健学専攻」各分野のスタッフからそれぞれの経験を踏まえて解説を受ける。一連の講義を通じて、Global Health の問題は途上国のみにとどまらず先進国も共に協働して取り組むことが必須になりつつあること、従来の医療や保健という場にとどまらない多様な領域の理解が必要であることに加えて、基礎科学的にも興味深い課題、重要な課題が数多く存在していることが実感されるであろう。
- 生命・医療倫理
- 保健・医療の分野における、意思決定が困難な問題を、倫理的側面から考察する。授業では、医療倫理学の基礎理論を講義するだけでなく、具体的なケースを用いたディスカッションも行う。
3Sセメスター
- 疾病論・病態疾患論
- 臨床医学と薬剤学を理解するために必要な基礎的知識や思考過程と、諸疾患を理解するために必要な知識を学ぶ。
- 疫学
- 疫学(Epidemiology)は、健康・疾病に関する事象を集団の中で計量的に捉え、これらの原因や影響因子とその強さを評価し、最終的には予防手段につなげる実践の学問であり、古くは感染症の疫学から始まり、がん・循環器疾患などの生活習慣病の疫学にその研究テーマが移ってきた。本講義ではその基礎を学ぶ。
- 免疫と生体防御
- 免疫の歴史的背景を踏まえてその概念と基礎知識をオムニバス形式で説明し、更に最新の免疫学研究のトピックや免疫学についても触れる授業となっている。キーワードとしては、T細胞、B細胞、抗原認識、免疫グロブリン、MHC拘束、接着分子、免疫系とシグナル伝達、免疫系の遺伝子発現、母子免疫、サイトカインなど。
- 救急処置
- 災害などを含めた救急場面に際しての基本的な考え方、緊急度の判断方法を学び、災害時・緊急時の望ましい救急医療システムを理解・考察するとともに、救急処置法・心肺蘇生法について学び、演習を行うことで、実施できるようになる。
3Aセメスター
- 医学データの統計解析
- 臨床研究・疫学研究で頻用される統計解析法について講義するとともに、SASを用いて実習を行う。午後の医学データの統計解析実習と関連しており、基本的には午前中に実習も行うことがある。
- 臨床・疫学研究の実例
- 疫学研究(臨床試験研究も含む)の方法論について、実際の応用事例を中心とした講義を受ける。
- 母性看護学
- 妊娠・分娩・産褥各期と新生児期を中心に、心身の生理的変化と健康事象のアセスメント及び看護の計画、実施、評価法を学習する。各期に適した保健指導および異常の早期発見の方法について考察し、看護計画を立案し、ケアを実施するうえで必要な知識を身につけることができるようになる。
- 解剖示説
- 人体の構築について学習するとともに、「生」「健康」の対極にある「死」「疾患」について学び、生命・生活についての深い理解に役立てる。
4Sセメスター
- 地域看護学・看護管理学
- 地域看護学では、地域で生活している個人、家族、特定集団を対象に、健康増進、疾病の予防と回復、日常生活や社会生活への適応を図るための支援方法を学び、看護管理学では看護管理学の概要と看護管理実践に必要な基礎的知識を習得する。
- 学校保健学
- 学校保健には、保健教育、 管理、健康診断、環境保健の4分野があり、本シリーズの講義では学校保健の総論に加え、各分野を深掘りする。キーワードとしては学校保健管理、学校環境保健、学校保健教育、学校健康診断、 障害児、学校安全活動と事故障害、伝染性疾患とその対策、幼児教育、思春期保健など。
- 公衆衛生倫理
- 公衆衛生に関する問題を、主に倫理的側面から検討する。授業では、公衆衛生倫理の基礎理論を講義するだけでなく、具体的なケースを用いたディスカッションも行う。
主な研究室紹介
- 生物医化学教室(野崎智義教授)
- キーワード:生物医化学
- 主な研究内容
- 昆虫を媒介とする感染症の機構・代謝
- 研究室HP:http://www.biomedchem.m.u-tokyo.ac.jp
- 医療倫理学教室(赤林朋教授)
- キーワード:医療倫理学
- 主な研究内容
- 医療倫理について、総論的な内容から歴史、理論を兼k集している。
- 研究室HP:http://www.ethps.m.u-tokyo.ac.jp
- 疫学・生物統計学教室(松山裕教授)
- キーワード:疫学、生物統計学
- 主な研究内容
- 社会の中での疾病・健康に関する事象とその予防
- 研究室HP:http://www.epistat.m.u-tokyo.ac.jp
学科インタビュー
Coming Soon
学生の声
- 必修の段階で、公衆衛生学、生物統計学など臨床研究寄りのことから、基礎研究まで幅広く学べる。看護学にも触れることで、生物学的なヒトのみならず、社会的な人についても広く学ぶことができる。また、実習なども豊富で、座学のみならず実際の現場で医学を学ぶことができる。
薬学部
概要
薬学部は、薬学を中心に、医学・生命科学・化学・物理学について幅広く扱う学部である。
もともと医学部の一学科であったが、近年独立したため医学部とも歴史上は距離が近い。しかし研究内容としては医学系のものだけでなく上記分野についての基礎研究も幅広く行なっており、人体や健康とも関わりつつ、より理工学的な研究ができるのが特徴である。
一般に、「薬学部=薬剤師を養成する6年制の学部」というイメージが強いと思われるが、それは薬学部の内、薬学科の方である。(学部内は6年制の薬学科と4年制の薬科学科に分かれており、薬科学科は、薬科学研究者を養成するため、大学院への進学を前提としたカリキュラムが組まれている4年制の学科で、2006年入学者より設置されたコースである。)募集要項は8人程度とされていて、多い時は12人程まで増える。逆に言えば、薬剤師になる人間として学部内で医療に触れたいのであれば、85名の定員のうち、8人に入る必要がある。
3年の11月に面接があり、3年の1月から学科別に分かれるため、進振りの段階でこの8人は決定しない。つまり、進振りで「医療に触れる道に進める」という保証はされないということになる。
しかし、前述の医学部の2学科と異なる点として、化学や分子生物学に触れるという点がある。これらの切り口、例えば創薬などから医療に触れたいと思っている人に向いていると考えられる。
基本情報
- 定員
- 計85名
- 要求/要望科目
- 要求科目
- 文科各類
- 基礎科目(基礎実験)「物性化学、熱力学または化学熱力学、生命科学または生命科学Ⅰ」から2科目
- 文科各類
- 要望科目
- 総合E「化学薬学概論、生物薬学概論、有機反応化学」
- 要求科目
- 公式HP
カリキュラム紹介
4年制の薬科学科と6年制の薬学科では卒業要件が異なる。
そのため、ここでは学部のシラバスに則り以下のような表記をする。
④:薬科学科の必修
4:薬科学科の選択
⑥:薬学科の必修
6:薬学科の選択
*:指定なし(履修できるが修得単位は卒業要件の単位とはならない)
2A1ターム
- 機能形態学 ④⑥
- 生命体の成り立ちを個体、器官、細胞レベルで理解するために、生命体の構造と機能などに関する基本的事項を解説する。 これらの講義から、ヒトの身体を構成する臓器の名称、形態および体内での位置、役割分担を理解する。キーワードとしては、中枢神経系、体性神経系、自律神経系、骨格と筋肉系、心臓、血管系、呼吸器系、消化器系、肝臓、泌尿器系、生殖器系、内分泌系、神経系の興奮と伝導、シナプスにおける神経伝達、筋収縮機構、ホルモンの作用・分泌機構・関連疾患、血圧の調節機構、尿の生成と調節、消化・吸収の調節機構など。
- 薬学概論 ④⑥
- 薬学という学問のアウトライン、歴史、将来像等について、オムニバス形式から分かり易く解説し、医療、製薬産業などを含めて、薬学と社会との関わりを様々な視点から考える。生命に関わる職業人となることを自覚すると同時に、薬学生としてのモチベーションを高めるために、薬の専門家として身につけるべき基本的知識、技能、態度を修得し、卒業生の活躍する現場などを体験する。
2A2ターム
- 微生物学・化学療法学 4⑥
- 微生物の基礎と病原体としての微生物に関して、基本的知識や研究から明らかにされた原理を学びつつ、微生物感染症とその予防・治療についても扱う。キーワードとしては微生物の分類、構造、生活環、代謝、増殖・複製、遺伝子発現制御、変異、遺伝子伝達、微生物と宿主の相互作用、抗生物質、ワクチンなどである。
- 病理学 ④⑥
- ヒトに生じる各種疾患の病理変化の基本原理について学ぶ。この授業では、循環障害、代謝障害、炎症、腫瘍性変化が種々の臓器・系統を冒す疾患である病理学的変化を総論として学び各種疾患の分類・病態について講義を受ける。
3S1ターム
- 免疫学 46
- 免疫系の異常は、免疫不全症や感染症のみならず、自己免疫疾患、炎症性疾患、アレルギー、がんなど様々な疾患の発症に関わっている。この講義では、免疫系と免疫応答の基本的な特徴とその制御メカニズムについてや免疫系の制御異常がどのようにしてこれら多様な疾患の発症に関わるかを学ぶ。
3S2ターム
- がん細胞生物学・バイオ医薬品 46
- 悪性腫瘍の増殖に関わる遺伝子の変化と病態の関係を概説する授業である。この講義では、薬物治療が有効な悪性腫瘍とこれに抵抗性を示す腫瘍の違いを理解し、これに関係する遺伝子の機能について紹介する。キーワードとしては、がんと宿主の相互作用、がん転移、悪性腫瘍などである。
- 医薬品情報学 4⑥
- 医療現場では、医薬品の適正使用とリスクマネジメント、さらには市販後の医薬品に関する新たなデータ検出による創薬への貢献が重要である。この一連のプロセスである医薬品ライフタイムマネジメントにおける医薬品情報の重要性や医薬品情報に関する基本的事項、市販後の医薬品情報の収集・評価・提供などについて学ぶ。
3A1ターム
- 医療薬学 ④⑥
- 医療制度の歴史と現状、高度化が進む医療現場における薬剤師の活動などについての講義を受ける。また、個々の疾患と治療薬について、疫学的背景、疾患の要因、治療薬の薬効発現機序、副作用発現機序についての説明が行われ、最新の治療ガイドラインに基づく薬物治療方針を学ぶ。
- 医薬化学 ④6
- 化学物質の代表的な反応や有機合成法、そして生体分子の機能と医薬品の作用を化学構造と関連づけて理解するための基本的知識を修得することを目指す授業。医薬品開発に必須の有機合成戦略の方法論と生体関連反応及びその解析法・設計法を学ぶ。キーワードとしては、逆合成解析、遷移金属触媒などである。
- 疾患代謝学 4⑥
- 生体は、タンパク質、核酸、脂質、糖の四大成分により構成されている。これらの成分は、それを構成する分子(アミノ酸、脂肪酸等)を経て、絶えず動的に変換(代謝)されている。この代謝に異常を来すと、糖尿病、動脈硬化症、神経変性疾患に代表されるような様々な疾患を引き起こす。この講義ではこれらの代謝を理解するとともに、薬学的に重要と考えられる代謝性疾患について学ぶ。
3A2ターム
- 医薬化学Ⅲ ④*
- Comming Soon
- 医薬品安全性学 4⑥
- Comming Soon
- 薬学特別講義 4⑥
- Comming Soon
4Sセメスター
- 医薬品・医療ビジネス 46
- Coming Soon
- 公衆衛生学 4⑥
- Coming Soon
主な研究室紹介
有機薬科学や生物薬科学、創薬学に関わる研究室など、詳細はこちらを参照されたい。ここでは、医学との関わりが深い、医療薬学と社会薬学に関する研究室を取り上げる。
- 分子薬物動態学教室(楠原洋之教授)
- キーワード:医療薬学、(投薬の)効果と安全性の予測と制御、分子解析
- 主な研究内容
- 薬物の肝腎振り分け機構と血液脳関門透過機構の解明
- トランスポーターの膜局在制御の解明
- トランスポーターの利用によるドラッグデリバリーシステム(DDS)の開発
- 薬物による組織毒性発現機構の解明
- トランスポーターの転写制御・エピジェネティック制御機構の解析
- 研究室HP:https://dotai.f.u-tokyo.ac.jp/ja/index.html
- 臨床薬物動態学教室(高田龍平教授・通称:薬剤部)
- キーワード:医療薬学、予防・治療法、副作用、創薬治療、システム薬理学
- 主な研究内容
- 生体内輸送を制御する分子メカニズムの解明による、生活習慣病治療法の確立を目指した研究
- 骨吸収・骨形成に関わるシグナル分子の制御メカニズムの解明による、骨代謝疾患治療法の確立を目指した研究
- 分子標的抗がん剤の薬理・毒性発現メカニズムの定量的理解と、臨床応用および新規創薬手法の確立を目指した研究
- 研究室HP:http://plaza.umin.ac.jp/~todaiyak/
- 医薬品評価科学教室(小野俊介准教授)
- キーワード:社会薬学、評価科学、新薬研究開発、産学連携
- 主な研究内容
- 信頼性の高い薬効評価データを生みだす方法論の開発
- 医薬品及び医薬品開発技術の価値評価に関する研究
- 医薬品開発ガイドラインの評価研究
- 研究室HP:https://yakuhyou.f.u-tokyo.ac.jp/
学科インタビュー
Coming Soon
学生の声
- (医学を学びたい学生にとって、魅力が)とてもあると思います。どちらかというと臨床の医薬学よりも化学・物理・生物といった方向の授業が多いです。薬剤師を目指すコースの薬学科(6年制)はより臨床の医薬学についてはの授業が多いですが、薬科学科(4年制)でも薬の臨床事例を扱う授業や、統計学を活用した処方の選択に関する授業等々必須のものが多いです。また薬科学科(4年制)でも薬学科(6年制)の授業の履修は可能です。
- 医療や製薬のスペシャリストの方々の話が聞ける講義も1ターム1コマ程度ある。
- 最先端で研究されている先生方のお話を聞く機会が多数提供されるのは非常に良いと思う。オムニバス形式で東大以外の先生の講義が毎タームある。
農学部:獣医学課程獣医学専修
概要
「獣医学の基礎化学と応用技術を習得し、動物医療と公衆衛生に貢献する人材」を育成するべく、哺乳類と鳥類を中心としつつ爬虫類や魚類についてまでを研究対象としている。卒業には6年を要し、6年次には国家試験を受験して獣医師の資格を取得する人がほとんどである。このことから、実習やインターンシップをはじめとする「臨床」の道に進むための授業も非常に多い。
動物の形態や機能と病態を、個体レベルから細胞レベル、さらには分子レベルまで、総合的に理解することを目的として教育・研究が行われているため、生命科学分野と医学分野をどちらも重点的に学ぶ。これは、人間を含めた動物の病理や病態についても研究対象だからである。「想像以上に医学だった」「解剖が多く意外だった」などの声をしばしば聞くことがこれを裏付ける一方で、病理や疾病治療に関心がある学生にとっては進学先の選択肢として検討の余地はあろう。
カリキュラムの観点から言えば、2Aセメスターから3Sセメスターは生命科学を中心に動物についての「基礎」を学ぶ一方で、3Aセメスターからは医学を中心に動物についての「応用・実践」を学んでいくことから、徐々に授業内容は公衆衛生学や病理学などをはじめとする「医学」的なものが中心的になる。従って、本記事では3Aセメスター以降の獣医学専修での学びを主に取り上げる。生命科学について学ぶことが多い3Sセメスター以前については、分野別学部学科紹介の生命科学分野をご参照頂きたい。
基本情報
- 定員:30名
- 要求科目(文科各類)
- 基礎科目(生命科学)「生命科学、生命科学Ⅰ、生命科学Ⅱ」から1科目(2単位または1単位)
- 要望科目
- なし
カリキュラム紹介
3Sセメスター以前は生命科学分野の分野別学部学科紹介を参照されたい。必修授業から、医学分野のものを抜粋して紹介。なお、こちらには記載していないが、公衆衛生学に関する授業も複数開講されるので、興味がある方はシラバスを確認して頂きたい。
3A1ターム
10月頃に研究室紹介が行われる。その後、任意で研究室を訪問したり、先輩に話を聞いたりして自分の関心に添った研究室を探す。各研究室が主催しているゼミに参加することも可能。
- 応用免疫学(月曜1限・水曜3限)
- 免疫学を個体、細胞、分子など様々なスケールから学ぶ。キーワードは、自然免疫、獲得免疫、液性免疫、細胞性免疫、免疫病態、アレルギー、ワクチンなど。
- 獣医解剖学(集中講義)
- 基本的な解剖用語の説明を受けた後に、犬の身体の構造、他種(馬・牛・鶏・豚)との違いを学ぶ。
- 解剖学実習(集中講義)
- 犬の骨格標本をスケッチし、骨の各部の名称を学ぶ。続いて、メスとピンセットを用いて実際に犬を解剖し、筋・血管・神経・内臓の構造を学ぶ。さらに、豚・山羊・鶏を用いた解剖も行う。(馬はビデオを見て学ぶ。)
- 細菌学実習(集中講義)
- 病原細菌の取り扱い(無菌操作・消毒・滅菌法など)と培養・同定について実際に手を動かしながら学ぶ。
3A2ターム
12月頃に卒業研究で配属となる研究室の希望調査が行われる。以下は必修授業から医学分野のものを抜粋して紹介したものである。
- 動物感染症学(火曜1限・木曜2限)
- Coming Soon
- 病理学総論(火曜2限・木曜1限)
- Coming Soon
- 内科学総論・呼吸器病学(月曜2限)
- 前半では、獣医療診療における問診・診療の進め方の基本を学ぶ。その際のキーワードは、Evidence-based medicine (EBM)、インフォームドコンセント。後半は肺などの呼吸器疾患とその診断法(CTについてなど)や治療法を学ぶ。
- 獣医解剖学(集中講義)
- 同上
- 解剖学実習(集中講義)
- 同上
- 細菌学実習(集中講義)
- 同上
4S1ターム
- 消化器病学(月曜1限)
- 小動物の消化器疾患の診断、検査法、治療法を学ぶ。その後、咽頭、食道、胃、小腸、大腸、膵外分泌などにおける各疾患について具体的な各論の説明を受ける。
- 内分泌病学(月曜2限)
- S1タームとA1タームを通して、小動物における内分泌疾患の病態と診断法、治療法を学ぶ。扱う内容は甲状腺疾患、上皮小体疾患、膵臓疾患、副腎疾患、脳下垂体疾患、生殖器疾患など。
- 病理学各論(火曜2限・水曜1限)
- Coming Soon
- 画像診断学(水曜2限)
- Coming Soon
- 臨床病理学(木曜1限)
- Coming Soon
- 麻酔・鎮痛学(金曜1限)
- Coming Soon
- 外科学・手術学総論(金曜2限)
- Coming Soon
- 魚病学(集中講義)
- 魚類における疾病を扱う。
- 基礎臨床学実習Ⅰ(集中講義)
- 小動物の内科系疾患に対しての診断までの手順や、検査法(身体検査、神経学的検査、眼科検査、皮膚科検査)および採材法(採血法、採尿法、骨髄採取法、生検法)を学ぶ。これらに加え、超音波検査、内視鏡検査、内分泌検査なども扱う。
- 病理学実習(集中講義)
- 前半1単位分は病理組織学について総論を学びつつ実習として病理組織標本の観察を行う。後半1単位分は希望者のみで病理解剖、病理検査の実習を行う。
4SPターム
- 外科消化器病学(火曜2限・水曜1限)
- 小動物の消化器(食道・腸など)・肝臓・胆嚢における疾患のうち、外科的疾患の病態、診断法とその治療法を学ぶ。
- 野生動物医学(木曜1限)
- 野生動物の解剖、生態、病気、治療、救護法、保護を扱う。また、比較的新しい学問分野である「保全医学」について講義する。保全医学が何か気になる方はこちらを確認のこと。
- 基礎臨床学実習Ⅰ(集中講義)
- 同上
- 病理学実習(集中講義)
- 同上
- 動物衛生学実習(集中講義)
- 月曜日から金曜日まで、泊まり込みで牧場に行く。牧場にいる動物の採血を行って、血液・生化学検査に取り組む。
4A1ターム
- 肝臓病学(月曜1限)
- 犬と猫の肝臓、肝外胆道系、膵臓(膵外分泌)疾患の診断とその治療法を学ぶ。
- 人獣共通感染症(月曜2限・水曜2限)
- 社会学的、生態学的背景にも触れながら、人獣共通感染症の定義や歴史、対策を学ぶ。その後に各論として、細菌性・ウイルス性・真菌性・原虫性・寄生虫性などの様々な人獣共通感染症の解説を受ける。
- 獣医疫学(火曜2限)
- 疫学的指標と統計学の基礎を学んだ後に、感染症の空間的な分布と時間的な分布を明らかにする記述疫学、疾病のリスク要因を明らかにする分析疫学を学ぶ。また、診断や治療法の決定、損害や防疫措置の経済評価なども扱う。
- 泌尿器病学(木曜1限)
- ペットの腎臓や尿路系に関する疾患の病態、診断、その治療法を学ぶ。
- 内分泌病学(木曜2限)
- 同上
- 外科泌尿生殖器病学(金曜1限)
- 小動物の泌尿・生殖器疾患のうち、外科的疾患の病態とその診断法、治療法について学ぶ。扱う内容は腎臓、子宮、卵巣、前立腺、精巣、尿道、膀胱、尿管など。
- 外科軟部組織病学(金曜2限)
- 名前から想像が付きにくいが、腫瘍を学ぶ授業。腫瘍とは何かを学び、診断法・手術法・放射線療法・化学療法をはじめとした治療法について扱う。
- 病理学実習(集中講義)
- 同上
4A2ターム
- 神経病学(月曜1限)
- ペットの脳、脊髄、末梢神経および神経筋接合部に関する疾患の病態、診断、その治療法を学ぶ。
- 血液病学(水曜2限)
- 貧血・白血球増加症・白血球減少症・血栓症・リンパ系腫瘍・骨髄系腫瘍などの疾患の病態、診断、その治療法を学ぶ。
- 外科呼吸器循環器病学(金曜1限)
- 小動物の肺や心臓などの呼吸器・循環器の外科的疾患の病態、診断法、その治療法について学ぶ。
- 眼科学(金曜2限)
- 眼の解剖、生理について学ぶ。扱う内容としては、緑内障等の眼疾患の原因と病態生理、その治療法など。
- 病理学実習(集中講義)
- 同上
5年次~6年次
- 小動物内科・外科臨床実習(5年次~6年次)
- 病院の各診療科を回って行う臨床実習で、通称は「ポリクリ」。動物医療センターを訪問して内科、外科をそれぞれ11日ずつ見学する。
- 大動物臨床・臨床繁殖実習(5年次)
- 地方の家畜診療所を訪問し、家畜の臨床現場を知る。2020年度は、20名が千葉、10名が山形の家畜診療所を訪れた。
5年生の5月から6月にかけて、獣医師の国家資格の仮免許試験である「CBT試験」が行われ、学生獣医師の資格取得を目指す。不合格となると留年するだけでなく、病院での臨床実習に参加できなくなるため、遅くとも4年次の3月ごろから対策をする必要がある。6年次は卒業論文の執筆と共に、2月に受験する獣医師国家試験への対策を行う。
主な研究室紹介
詳細はこちら。
- 獣医微生物学教室(堀本泰介教授・村上晋准教授)
- キーワード:ウイルス、感染症、人獣共通感染症、医学・生命科学
- 主な研究内容
- 日本のコウモリから新型コロナウイルスと遺伝的に近縁なウイルスを検出する研究(参考)
- D型インフルエンザが牛の生産性の障害となる牛呼吸器病症候群の一因であることを示す研究
- 犬のガンを治療する組換えイヌアデノウイルスの開発研究
- クリミア・コンゴ出血熱ウイルスなど人獣共通感染症ウイルスの基礎研究とその診断法の開発研究
- 研究室HP:http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/ikushu/wp/
- 獣医薬理学教室(堀正敏教授)
- キーワード:骨格筋、平滑筋、天然化合物、医学・化学
- 主な研究内容
- 平滑筋が関わる疾病を分子レベルで調べ、治療薬の開発へと繋げる研究
- 動物のホメオスタシス維持・病態形成における血管内皮細胞の役割の解明とその制御を目指した研究
- 天然の生理活性物質(毒)や、食品に含まれる生理活性物質(毒)の作用の解明を目指す研究
- 研究室HP:http://www.vm.a.u-tokyo.ac.jp/yakuri/index.html
学科インタビュー
Coming Soon
学生の声
- 高度な内容の動物実験によって臨床的な技術を経験できるところが魅力だと思う。授業は今のところは知識を詰め込む形なのであまり楽しいものではない。研究についても授業に関連した内容が頻繁に取り上げられている。
【コラム】~公認心理師について~
公認心理師は2017年に施行された「公認心理師法」に規定された医師、教師、薬剤師等と並ぶ本格的な国家資格で、心理系では初の国家資格です。
東京大学で公認心理師の資格を取得するためには定められた授業を履修しなければならず、その授業は教養学部前期課程・教養学部後期課程統合自然科学科認知行動コース・教育学部・文学部・部局横断型プログラムPHISEMにまたがっています。前期課程でしか履修できない授業や後期課程でしか履修できない授業があるので注意が必要です。