
i factorial
2023.4.18
学部生が研究発表を行い、異分野学問の交流の創出を目指すイベントを開催する学生団体。
目次
基本情報
| 執行代 | 特に決まっていない |
|---|---|
| 人数 | 11名 |
| 参加学年 | 学生+社会人 |
| 選考情報 | なし |
| 年会費 | なし |
| 活動頻度 | 月1度のオンラインミーティングとイベント運営。長期休暇には追加でイベントの運営と準備の会議。 |
| 公式サイト |
概要
■理念/指針・沿革
理念①
アマチュアのためのアカデミア:大学院生と異なり、学部生は学会に出ることができ
ない。しかし、意欲ある一部の学部生には、「学会に出て実際に論文を出すことは難しくとも研究をしてみたい」「自分の研究成果を発表したい」と感じている人もいる。そうした学部生の想いを実現する場を提供することが当団体の理念の一つである。
理念②
越境する知性:他分野の融合を団体の理念の一つとして掲げている。他の分野を学
び、それらの知を融合することで新たな学問分野を作り出すことを重視している。
沿革
設立者の2人もアカデミアに興味があったものの、実際の研究活動にハードルの高さを感じていた。彼らが推薦生のコミュニティにおいて、様々な分野の人と話す中で、理念①で示したような場を作ることや他分野の融合を推進していくことの重要性を実感した。こうして2021年春に当団体は設立された。
■活動内容 ※2022年度の情報
i factorialの活動は主に「越境する知性会議」と「脱線する知性カフェ」の2つのイベントを開催すること。その2つのイベントについて、発表者を一般に募集し、運営(司会進行やZoom管理)やSlackコミュニティの運営を行う。
「越境する知性会議」とは
多様な分野の学生が個々の興味に基づいた研究について発表しているのを聞き、これを基にディスカッションを行って学問の裾野を広げるイベントである。年2回の長期休みごとに開催され、流れとしては「個人の研究発表に続き、少人数でディスカッションを行い課題を考察(運営から発表に関連する課題を2〜3個提示)、そして全体で課題を整理し、参加者に刺激を与えたり、参加者の研究テーマのキッカケを作っていく。」という形である。過去の事例としては、「魚の群れの動きを物理学の知識を用いて数式で解き明かせるのではないかという研究」や、「防災教育の問題を技術的に解決しようと試みる研究」などがある。
「脱線する知性カフェ」とは
月に1回開催される、「越境する知性会議」の短縮版のサイエンスカフェである。「越境する知性会議」と同様、多様な研究・勉強をしている学生と交流をすることで、新しい科学を見つけることを目標にしている。イベントは研究発表と雑談とで構成されており、発表は自然科学だけでなく社会科学・人文科学の分野の内容も歓迎している。過去には短歌がテーマになったこともある。なお、雑談では発表内容などについて話し合う。発表者の持つ時間が越境する知性会議よりも長いため、十分な説明が必要な専門的内容の発表の場として活用される。
※2022年度の対面活動の見通し
現在はオンラインが中心である。しかし、場所に関わらず参加できるようにするため、次回以降はハイブリッド形式を検討中である。
メンバー構成
■メンバー構成
人数
11人
学年
新2〜3年生
執行代
特に決まっていない
ジェンダーバランス
女性はおよそ1-2割程度
加入時期
一年を通じて入会が可能
属性
・メンバーは現時点ではほとんど東大生だが、多様性確保の観点から他大学からも募集している
・理系が多い
・研究に関心がある学生団体なので、アカデミア志向の人が多い
・複数サークルに所属している人もいる
・リサーチインターンシップや研究室インターンをする人は一定数いる一方で、民間企業やNPOでインターンを行っている人は少ない
・学会や勉強会に参加する人もいる
活動実態
1年間でどのくらいのメンバーが活動から離脱してしまう?
まだ活動期間が1年に達していないので不明。
メンバー間でコミット量の差はどのくらいある?
運営メンバーの11人は全員、研究をはじめとした個人の活動にも打ち込みつつコミットしている。
遊びや打ち上げにしか来ないメンバーもいる?
ほぼいない。
活動頻度
通常活動
月に1回のオンラインミーティングを行っている。
イベント前後の期間
「越境する知性会議」の前は企画会議が週1回程度行われ、研究発表のリハーサルも行う。なお、これ以外では特に負担が増えることはない。
年間予定
8〜9月「越境する知性会議」を開催。運営メンバーは開催月に企画会議(週1程度)に参加しつつ、本番に運営を行う。なお、一般参加者は当日に参加するだけで良い。
2〜3月「越境する知性会議」を開催。
※なお、毎月行うこととして、「脱線する知性カフェ」の開催(運営メンバーは当日運営作業のみ一般参加者は当日に参加するだけである)と、事務会議において事務関係の情報を共有することがある。
募集情報
選考あり/選考なし:
選考なし
募集対象:
学部生や院生、中高生、社会人も入会可能。
実際に入会する人:
学部1〜2年生
入会手続き内容:
公式TwitterにDMを送信。
内部のホンネ
○魅力
・個人の時間をほとんど拘束しないので、自分の勉強や研究に十分に時間を割ける。
・勉強へのモチベーションの高い人が集まるので、学習意欲が湧く。
・運営メンバーが個性的で面白い。
△大変なところ
・上手に企画を設計して運営するのはアイデア力を要するため難しい。
・メンバーの属性等において多様性の確保が難しい。
新歓日程詳細
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連カテゴリー

イベント企画
大学生や高校生を対象としたイベントを企画したり、様々な問題を外部に発信したりする団体。
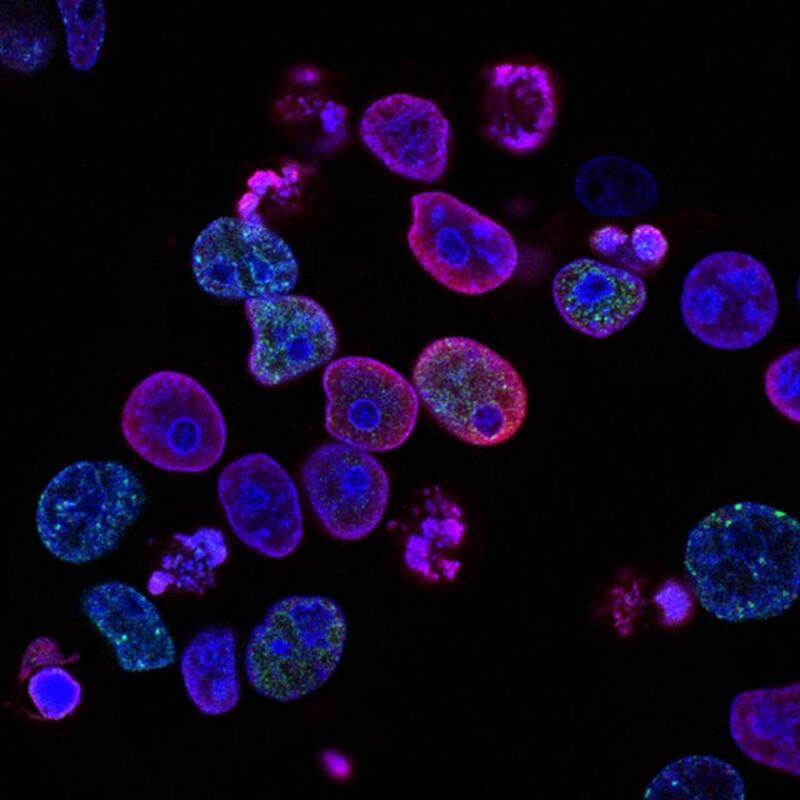
自然科学(生物・理工・医・薬)
自然科学に魅力を感じ、それらへの理解を深めていく団体。

人文科学(教育・文学・芸術)
教育・文学・芸術など「人文科学」を活動の軸として、研究やイベントの開催を行う団体。
関連サークル

UT RISE
「東京大学を誰にとっても居心地のいい多様性のある大学に変え、社会全体の変化を促す」というゴールを掲げ、主にジェンダー問題の解決に向けて活動している団体

Business Contest KING 実行委員会
「学生による学生のためのビジネスコンテスト運営団体」として国内最大のビジコンを開催している学生団体。
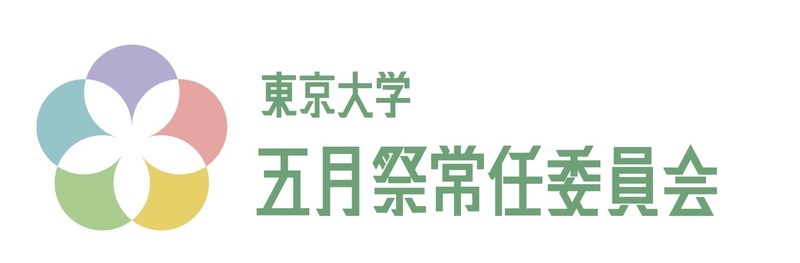
五月祭常任委員会
東大の学園祭、五月祭を企画・運営する学生団体。

ミライエコール
中高生の学校生活において、学生自身の声を反映させることを目指す学生団体。




