
模擬国連駒場研究会
模擬国連
こまけん
国際問題
議論
2024.3.7
国連などで行われている国際会議を「模擬」する活動。
目次
基本情報
| 執行代 | 2年目の会員が年始から年末まで(規定あり) |
|---|---|
| 人数 | 35名程度 |
| 参加学年 | 学部生のみ |
| 選考情報 | なし |
| 年会費 | 2024年度は入会費3000円を本入会時(6月)にいただきます。2年目から年会費6000円を徴収します |
| 活動頻度 | 通常活動:毎週水曜日19:00〜21:00@駒場キャンパス |
https://twitter.com/komabaMUN?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor |
|
| 公式サイト |
活動の様子
概要
■理念/指針・沿革
理念/指針
「知の総力戦」をモットーに掲げ、各人が模擬国連活動に励んでいます。
沿革
創設は2006年。模擬国連という活動自体は、1983年に難民高等弁務官としても活躍された緒方貞子氏が組織として模擬国連活動を始めたことが日本での普及のきっかけとなり、今や700人以上が取り組んでいる。
■活動内容
模擬国連とは、国連などで行われている国際会議を「模擬」する活動である。参加者はそれぞれ一国の大使に扮し、会議の議題に対して各国の立場から議論・交渉を行い、決議案の採択を通じて国益を反映することを目指す。相手を論破することではなく、あくまでも合意を得るのが目標であるということがディベートなどとは異なる点であり、単純な二項対立で括ることのできない多様なアクターがいる中で、どのように交渉をまとめるかということが模擬国連の醍醐味といえる。
■OBOGの進路/活動
〈進路〉
・外務省が多いようなことはなく、民間から公務員、大学院進学まで多様。
・参考例(三菱UFJ銀行/マッキンゼー/財務省、金融庁などの官公庁/ZOZOなど)
メンバー構成
■メンバー構成
人数
・全体で35名程度
・毎年1,2年生が25名程度
学年
・1-4年生
ジェンダーバランス
・女性はおよそ5割
加入時期
・通年だが、新歓期終了後の5-6月ごろが多い。
属性
・東京大学の学生が多いが、他大学(お茶大、ICU、成蹊、明治、上智、青学等)の会員も一定数いる。
・文系が多いが、理系も結構いる。
・大所帯ではないので距離が近い。
・活発な人が多い。模擬国連に関しては真面目。
離脱率
・およそ10%
活動実態
1年間でどのくらいのメンバーが活動から離脱してしまう?
およそ10%
メンバー間でコミット量の差はどのくらいある?
それなりにある。
遊びや打ち上げにしか来ないメンバーもいる?
全くいない。
活動頻度
通常活動
・通常活動:毎週水曜 19:00~21:00 @駒場キャンパス
コンテスト/イベント前後の期間
・会議:年6回
・3週前くらいから本格的にリサーチ開始。(全国大会では1ヶ月前くらい)
年間予定
4月 春の1日体験会議
5月 新歓会議
6月 前期会議
7月 前期打ち上げ
8月 夏合宿 (旅行)
9月 秋会議
10月 新メン会議
12月 後期会議
2月 冬合宿
3月 強化会議
募集情報
選考なし
募集対象:
全学年
実際に入会する人:
1年生中心(2年生の人もいます!)
入会手続き内容:
入会届け (google form)を提出し、入会。
内部のホンネ
○魅力
・ディベートなどとは異なり、総合的な競技性(議論の土台を設定する力、議論の運用術、交渉術、物事を俯瞰する力など)がある。
・4年間続けられる。続ければ続けるだけ強い大使になれる。
・学術的な観点(国際法など)でも奥が深い。
・全国大会等を通じ、全国の模擬国連研究会の会員と知り合うことができる。
・個性的なメンバーが多く、また人数も比較的少ないため、深い関係を築ける。夏・冬には海やスキーなどへ旅行にも行ったりする。
△大変なところ
・一つの会議に向けた準備に時間がかかる。
・最初、知的に「強い」先輩に圧倒され、議論に入っていきにくい
新歓日程詳細
説明会:4/5、4/8、4/17、4/25、4/30、5/15
国益を立てる会:4/11、4/24
ミニ模擬:4/13、4/16、5/3
春の一日会議に向けた勉強会:4/15
春の一日会議:4/21
新歓会議に向けた勉強会:5/13
新歓会議:5/18、5/19
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連サークル

東京大学 アマチュア無線クラブ
東大唯一の「アマチュア無線」を扱う団体。電波の送受信設備を自ら整備している。

iGEM UTokyo (iGEM東大)
iGEMは生物版ロボコンの世界大会。生物を遺伝子を介してプログラミングし、課題解決する。
RoboTech
NHK学⽣ロボコン、ABUロボコンで優勝を⽬指すサークル。
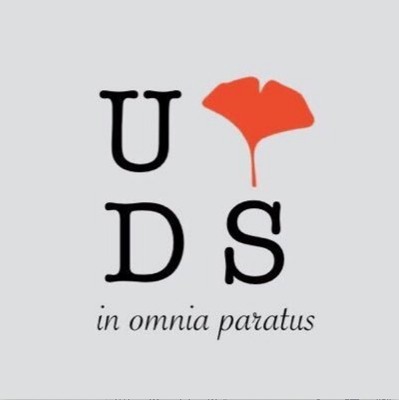
UTDS(東京大学英語ディベート部)
普段の練習や大会参加を通じて英語即興ディベートに取り組む。






