
「障害者のリアルに迫る」ゼミ
障害
社会課題
現場主義
フィールドワーク
イベント運営
福祉
2024.3.9
「タブーなく『障害』について考える」ことを目的としているゼミ。
目次
基本情報
| 執行代 | 学年や入会時期に基づく執行代制度は無い |
|---|---|
| 人数 | 主題科目の時は40名、自主ゼミの時には20名ほど。 |
| 選考情報 | なし |
| 年会費 | なし |
| 活動頻度 | 週一で駒場で講義 |
| 公式サイト |
活動の様子
概要
■理念/指針・沿革
・沿革
「障害者のリアルに迫る」東大ゼミは、経済学部の学生によって、2013年に開講されて以来、有志の学生により運営されている自主ゼミナールです。
・理念・指針
さまざまな「障害」に生きづらさを抱える人々や、「障害」問題に関わる実践家や専門家など、多彩なゲストの語りを聞き、タブーなき対話を重ねる中で、「障害」および人間への深い理解を目指す。
「障害」を身体障害や精神障害、知的障害といった一般的によく知られる「障害」に限らず、依存症や性的マイノリティなど、広い意味での様々な生きづらさとして考え、障害を巡る色々な問いについて考えること、自らの中に生まれた思いに立ち止まって考え話し合うことのできる場を作っていく。
自主ゼミ/全学自由研究ゼミナール(前期教養学部)として駒場キャンパスで開講される授業では、障害をめぐる歴史や制度について学ぶことに加えて、障害当事者や関係者のリアルな息づかいや生活、人生に触れることを主な目的としています。
■活動内容
《ビフォーコロナ》
基本的には講義形式で、それに加えて質疑応答、受講生同士のディスカッションを行っている。講義終了後にゲスト講師を交えて懇親会を行っており、講義では聞けないディープな話を聞くことや、受講生同士での本音のディスカッションをすることができる。
課外活動として、長期休暇中に社会福祉法人を見学している。法人の方に経営の仕方や取り組みをうかがうほか、利用者ともお話しする機会がある。昨年度は、通常の福祉施設のみならず、医療刑務所なども訪問した。
外部向けのイベントも開催している。ゼミで書籍『なんとなくは、生きられない。』を出版した際に、出版記念イベントを開催し、学生達とゲスト講師の対談を行なった。障害を扱う映画の上映会を監督に来ていただいて開催したり、「ゼミ祭り」としてゼミの活動を振り返るイベントを開いたりと、様々なイベントを企画・運営している。
《アフターコロナ》
授業・懇親会共に対面がメインとなり、法人見学なども積極的に行っている。
参考として、2023年度講義情報は以下になる。
2023Sセメスター(主題科目)
第1回 初回ガイダンス・野澤和弘氏
第2回 福祉施設へのインターンを経験した運営学生2人による対談
第3回 トゥレット当事者会
第4回 岡部宏生氏(NPO法人「境を越えて」理事長,ALS当事者)・佐藤裕美氏(ALS当事者)
第5回 馬場拓也氏(社会福祉法人「愛川舜寿会」理事長)
第6回 北川聡子氏(社会福祉法「麦の子会」理事長)・麦の子会のスタッフの方
第7回 星野敏夫氏(toiro cafe責任者)
第8回 牧野賢一氏(NPO法人UCHI代表)・UCHIを利用する当事者の方
第9回 松浦秀俊氏(双極はたらくラボ編集部)
第10回 蔭山真知子氏(「コルネリア・デランゲ症候群の親の会」代表)
第11回 熊谷晋一郎氏(東大先端研准教授,脳性麻痺当事者)
第12回 ディスカッション
第13回 かしわ哲氏(サルサガムテープ)
2023Aセメスターは授業開講せず、リアゼミ10周年記念イベント「障害者のリアル×東大生のリアル」に向けた準備を行い、12月10日に開催した。
また、9月に千葉合宿(恋する豚研究所・株式会社ベストサポート・社会福祉法人千楽見学)を行った。
・OBOGの進路/活動
〈進路〉
所属学生の学部はバラバラなので多種多様。
〈諸活動例〉
「東大生が福祉分野を学んでいる」というテーマで取り上げられることはある。
メンバー構成
■メンバー構成
人数
運営は10名。受講生は、主題科目(単位付き)の時は40名、自主ゼミの時には20名ほど(2023Sセメスターは主題科目)。
学年
運営・受講生合わせると1年生から院生まで幅広い。
ジェンダーバランス
女性はおよそ6割
加入時期
運営は、一度受講生として参加していた人がほとんど。運営になる学年は様々。
属性
・文系から理系まで様々。若干文系の方が多い。
・学年も1年生から院生まで幅広い。
・どの学年からでも入ることができ、学年や入会期による区別は存在しない。
・兼サーをしている人はかなり多く、兼サー率は8-9割ほど。
・所属先はスポーツ系から文化系まで様々。特にどこが多いということは無い。
活動実態
1年間でどのくらいのメンバーが活動から離脱してしまう?
およそ10%
メンバー間でコミット量の差はどのくらいある?
それなりにある
遊びや打ち上げにしか来ないメンバーもいる?
全くいない
活動頻度
通常活動
週一で駒場で講義(単位取得希望者は8割程度の出席必須)
コンテスト/イベント前後の期間
通常の授業期間では1回程度、長期休暇では1-2回の社会福祉法人などの訪問(有志。誰でも好きなものに参加可能。コロナの状況下では少ないが、長期休暇の遠方訪問時には1泊or2泊の合宿形式があることも。)
年間予定
4月: Sセメスター授業スタート。
4-7月: 13回の講義(講演)を週一回実施。学期中に1回程度の法人など訪問
8-9月: 合宿(遠方の法人訪問。1泊or2泊)夏季休業中に1-2回の法人など訪問
9月: Aセメスター授業スタート
9-1月: 13回の講義を週一回実施。学期中に1回程度の法人など訪問
2-3月: 合宿(遠方の法人訪問。1泊or2泊)春休み中に1-2回の法人など訪問
※見学等はコロナにより年間予定の通りとはいかないとしても、できる範囲で実施する
募集情報
選考なし
募集対象
全学年
実際に入会する人
全学年
入会手続き内容
入会登録のようなものも特に必要ない。 ただし、主題科目として開講された場合は、単位が必要な場合は履修登録をする必要がある。
特に単位が必要ではない場合は学期途中からでも参加可能。
内部のホンネ
○魅力
・「タブーなく語る」が標語。他では言えないような本音を言える場を目指している。
・ゲスト講師の話を理解するだけではなく、講義やディスカッションを通じてひとりひとりが悶々と考えていくことを目的としている。一つの「正解」を要求されず、もやもやとした状態が積極的に許容される。
・障害の問題に関心のある人もいれば、障害のある人と全く話したことがない人も参加している。障害に関する知識や立場によらず、参加している各自が思ったままに話せる場を目指している。
△大変なところ
・運営に入ると、各授業の講師へのアポ取りを担うことになるのが若干大変なことも。
新歓日程詳細
リアゼミSNSにて情報発信していく予定です。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連サークル

KIP 知日派国際人育成プログラム
「『日本知らずの国際人』から『知日派の国際人』へ」を掲げ、学生・若手社会人で討論を行う会員制グループ。
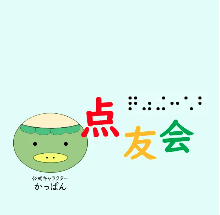
東京大学 点友会
点字を学び、学園祭パンフレットの点訳や触地図の作製などを行う団体。

Tottoko Gender Movement
大学から性差別・性暴力をなくしジェンダー平等な大学の実現を目指して活動する東大の学生・院生による団体

本郷Web3バレー
「Web3で未来の日本を牽引する東大生の拠点になる」ことをビジョンに掲げる東大生ブロックチェーンコミュニティ。Web3を技術面だけでなく多角的に学習し、社会への活用方法を考え、事業も作れて開発もできる東大生が育つエコシステムを形成する。






