
ut.code();
プログラミング
web開発
アプリ開発
工学
2024.3.9
2019年度に発足した開発系のプログラミングサークル。
目次
基本情報
| 執行代 | 主に2年の11月から3年の10月まで |
|---|---|
| 人数 | 600名程度 |
| 参加学年 | 学部生+院生 |
| 選考情報 | なし |
| 年会費 | なし |
| 活動頻度 | 週1-2回 |
| LINE | |
| 公式サイト | |
| 公式メアド |
contact[a]utcode.net
([a]を@にしてメールを送信してください) |
活動の様子
概要
■理念/指針・沿革
ut.code();は、2019年度に発足した開発系のプログラミングサークル。ソフトウェアを広く扱い、「学習・交流・開発」を活動の3本柱としている。
1)学習
・プログラミングは学び始めが一番難しい。0→1部分を強力にサポートする新歓活動を実施する。
・ソフトウェア開発技術は日々進化を続けているため、初学者が無駄なく学習することは困難。常に最新の状態にメンテされた信頼性の高い学習パスを作成・公開する。
2)交流
・ソフトウェア開発には、体系化されていない様々な知識や経験が生かされている。他者との交流を通してそうした知見を得るためのイベントを定期的に開催する。
・実社会で経験を積むことで、飛躍的な成長の機会が得られる。インターンシップや学外イベント情報などを集積し、構成員のキャリア構築を支援する。
3)開発
・学生や社会をより良くするためのプロダクトを開発し、実践的な力を身に着ける機会を提供する。
・共同開発を通して同じ志を持つ仲間を見つけることで、学習への意欲が向上する。
■活動内容
・毎年恒例のプロジェクト
毎年恒例のプロジェクトは主に全学ゼミ/自主ゼミの運営・五月祭と駒場祭・合宿など3つ。
五月祭、駒場祭では参加したいメンバーを募り、アイデアを出した後はチームに分かれて開発を進めていく。準備を通して、実践的な開発のノウハウと、プロダクト完成の喜びを実際に体感してもらうことができる。2022年の駒場祭においてはグランプリを獲得することができた。
・通年のプロジェクト
毎年恒例のプロジェクトのほかに、通年のプロジェクトが季節に関わらず動いている。
現在あるプロジェクトの例としては
・シ楽バス: 履修登録支援ツール
・だるめし: 質問に答えていくだけで献立を提案してくれるアプリ
・CreateCPU: Web ブラウザ上で論理回路を学ぶことのできるプラットフォーム
・Dot Tutor Learn: 体験型点字学習サイト
・Dot Tutor Translate: 点字翻訳サイト
などがある。春休みからはこれらの他に新たなプロジェクトも本格始動する。
メンバー構成
人数
Slack ワークスペースに現在600名ほど。
学年
学部1年〜博士課程。
執行代
主に2年の11月から3年の10月まで
体制
学友会の正式加盟サークルとして認定され、現在サークルの継続的な仕組み作りに取り組んでいる。
ジェンダーバランス
女性はおよそ1-2割。
加入時期
新歓期に主に1、2年生が加入するが、中途加入者も多数存在する。
属性
プログラミングを学びたいという気持ちで来る人が多い。
離脱率
コミュニティとしての側面を重視して Slack 参加のみのメンバーも認めているため、離脱という概念はあまりない。
活動実態
1年間でどのくらいのメンバーが活動から離脱してしまう?
およそ0%(コミュニティとしての側面を重視して Slack 参加のみのメンバーも認めているため、離脱という概念はあまりない。)
メンバー間でコミット量の差はどのくらいある?
激しい
遊びや打ち上げにしか来ないメンバーもいる?
全くいない
活動頻度
・サークル全体として
運営ミーティングを隔週で実施(オンライン)。
五月祭・駒場祭前には企画に参加するメンバーを募集して企画の制作を行う。
各セメスターの開始前には全学ゼミ・自主ゼミの運営に参加するメンバーを募集してゼミの運営を行う。
春休み・夏休みには合宿を行うほか、不定期にハッカソンやブレスト大会も行っている。
・プロジェクトごと
プロジェクトごとに基本的に週に1回オンラインでのミーティングを行う。
隔週〜月1程度で、学生会館などで対面の作業会を行う。
日程調整やペース配分などはプロジェクトメンバーが相談しあって決めるためかなり融通が利く。
年間予定
・4月:新歓・Sセメスターのゼミの開講
・5月:五月祭
・8月:夏季講習会・夏合宿・駒場祭準備開始
・9月:夏季講習会
・10月:Aセメスターのゼミの開講
・11月:駒場祭
・12月:プロジェクトのブレインストーミング
・1月:五月祭準備開始
・3月:春合宿
※1 他に、通年のプロジェクトも個別に動いている。
※2 その他ハッカソン、ブレストを不定期で開催している。
募集情報
選考あり/選考なし
選考なし
募集対象:
基本的に東大生のみ。学年制限もない(大学院生も参加可能)。
実際に入会する人:
入会者の8割は1~3年生だが、4年生や大学院生も一定数存在。
入会手続き内容:
ut.code(); ウェブサイトの「参加」ページ( https://utcode.net/join/ )のリンクから Slack ワークスペースに参加
内部のホンネ
○魅力
・成果物が出来上がったときの喜びはひとしお。
・同じように学習する仲間が心の支えになる。
△大変なところ
・「プログラミング」と一言でいってもシステム開発と情報科学はかなりかけ離れた立場にある。ut.code();は前者に該当する団体で、考えることよりも調べたり覚えたりすることが圧倒的に多いため大変。
・一人前になるまでの道のりが長いためモチベーションの維持が大変。
新歓日程詳細
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連カテゴリー
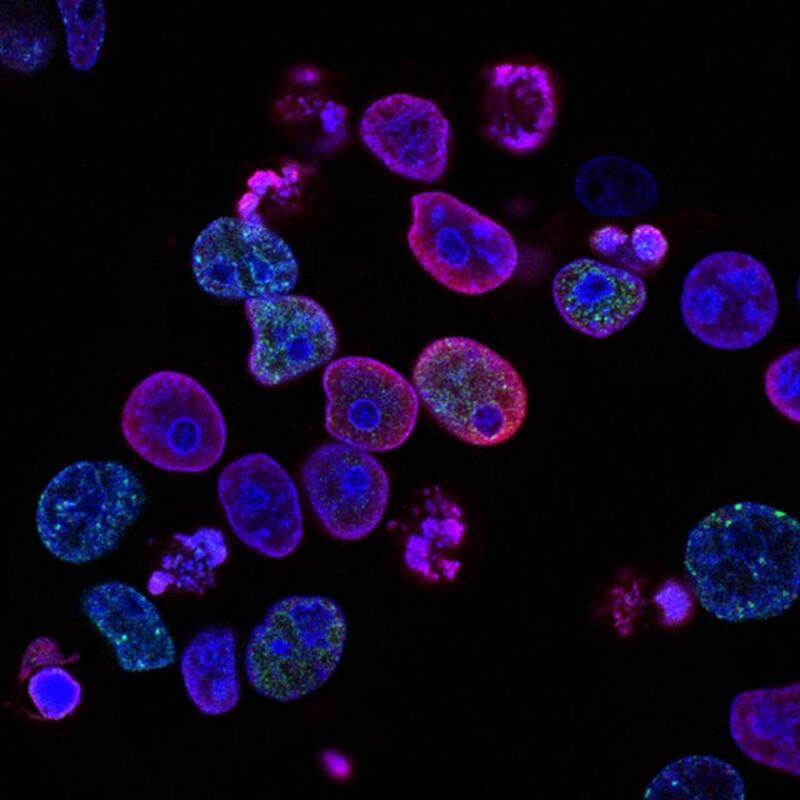
自然科学(生物・理工・医・薬)
自然科学に魅力を感じ、それらへの理解を深めていく団体。
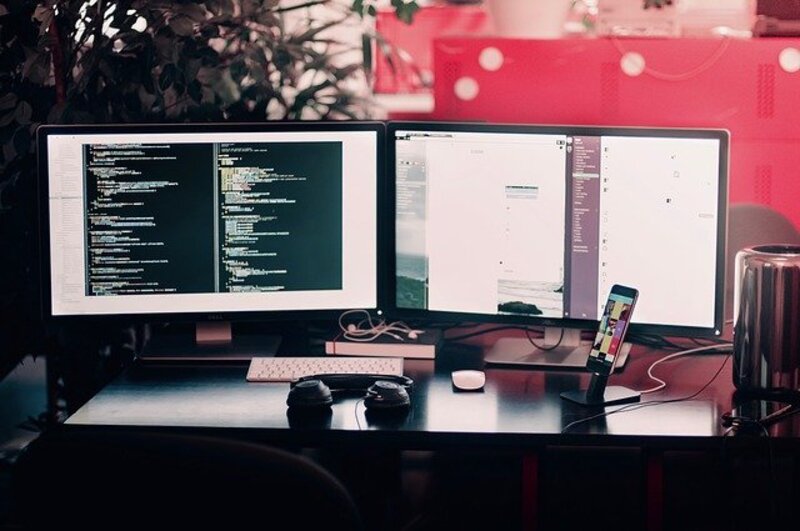
設計開発・デザイン
社会で普遍的・実践的に活用できるスキル習得(デザイン・アプリ開発・プロダクト開発)を学ぶ団体。
関連サークル

国際資源・エネルギー学生会議(IRESA)
資源・エネルギーという視点から社会を眺め知見を共有する学生団体。

競技AIサークル 灯|TOMOSHIBI
競技AIプログラミングサークル。kaggleを主とした大会での優秀成績獲得を目指す。
鉄門灯誓会

東京大学VRサークル UT-virtual
VRやARなどの、現実を拡張する技術(XR)の普及を目指す団体。




