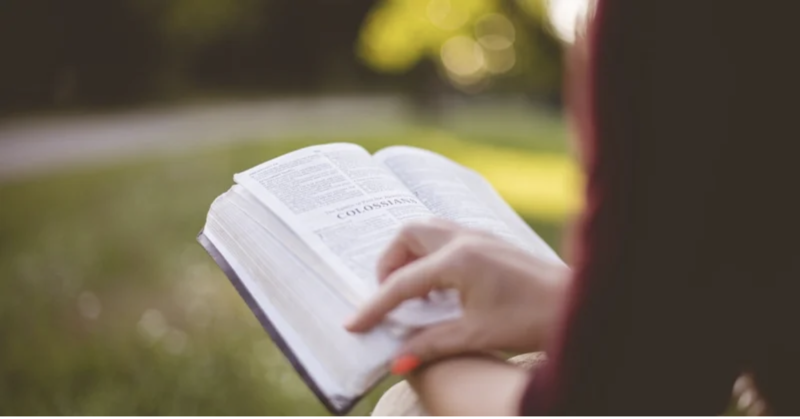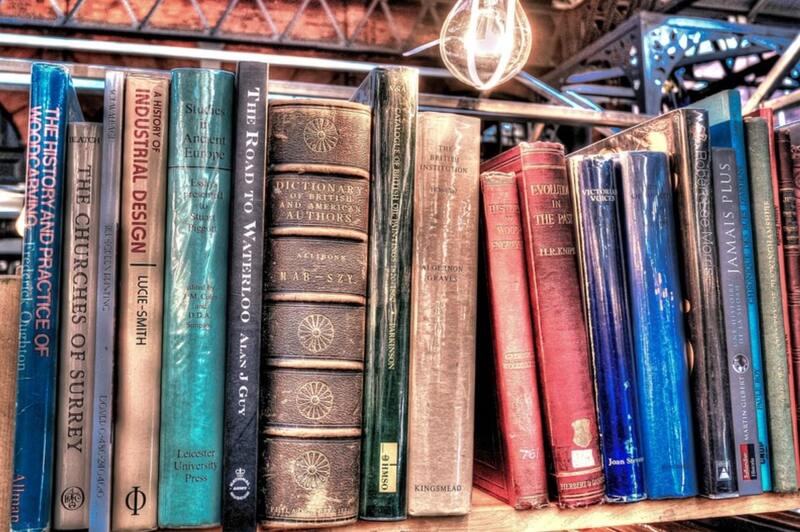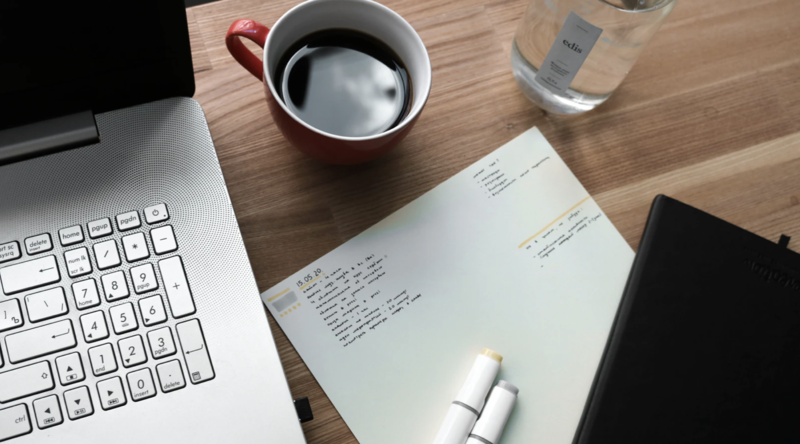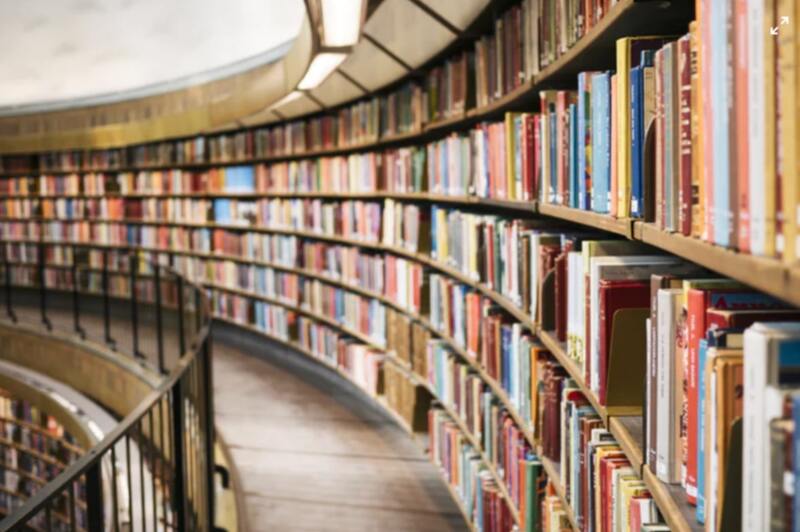新入生の皆さん、Sセメスターの履修はもう組み始めましたか?
シラバスを眺めていると、あの授業もこの授業も面白そうに見えたのに、履修してみたら思っていたよりつまらなかった... 逆に、必修との兼ね合いで仕方なく取ったけど実はめちゃめちゃ面白かった!なんてこともよくあります。
そこでこの記事では、シラバスを読むだけでは分からない
・UT-BASEメンバーおすすめの授業
・その授業の推せるポイント
をご紹介していきます!
参考のため、総合科目の系列等も記載していますが、はじめは「このような授業があるんだ!」という気持ちで読んでいただけると幸いです。
【凡例】
■科目名
①教員名
②曜限
③区分
④推せるポイント
目次
【総合科目A~C系列】
■言語構造論
①大関洋平
②金曜2限
③総合A系列
④A系列でありながら内容は自然言語処理に関するものです。総合科目のABC系列から何をとればいいか迷っている理科生の皆さんにとっては親しみやすい内容なので、とりやすい授業だと思われます。また文科生の人たち、特に言語・語学に興味がある人にとっても、機械の言語処理の仕組みを概観することによって言語を考察する異なる視点を得ることができます。さらには人工知能に対する理解にもつながり、全体的にバランスのいい授業でした。
■国際関係論
①湯川拓
②金曜2限
③総合B系列
④国際関係の理論について学ぶことができる。リアリズム・リベラリズムの立場の違い、それぞれの視点を比較しつつ概観する。具体的な事件を扱うのではなく、あえて理論を扱うことでより多くの事件に普遍的に当てはめることのできる考え方を身につけることができた。
■現代教育論
①佐々木英和
②水曜5限
③総合C系列
④「現代教育論」なので、もちろん教育についての話も聞けるが、何よりこの授業の魅力は双方向性とさまざまなことに対する分析力が上がることだと思う。隣の人と話したりグループで話したりする場面が多く、とても楽しかった。そのような交流を通して物事の本質を見る力を養うことができるのは、とてもお得だと思う。
【総合科目D~F系列】
■身体運動科学
①八田秀雄
②木曜日1限
③総合D系列
④運動するときのエネルギー消費や疲労の回復から、糖尿病や脂肪の燃焼などまで色々な身近な側面が取り上げられる。エネルギーの消費や摂取への理解が深まるだけでなく、より健康的な生活を送る上でもかなり役に立つ知識がたくさん。さらに、生物未履修でも困難なく理解できるくらい平易に解説されている。
■現代倫理
①高橋哲哉
②金曜日5限
③総合D系列
④2022年度は「赦し」をテーマに様々な論者の意見を比較したり、自分で考えたりと深いテーマを多角的に検討できる。哲学者の高橋哲哉先生の意見を直に聞けたり、
質疑応答の時間に先生と意見を気軽に交換できたりするのが魅力だと思う。
■応用動物科学Ⅰ
①三條場千寿
②木曜日5限
③総合E系列
④オムニバス形式でいろいろな研究に触れることができる。テーマが多様で面白い(2022年度はペットの問題行動・アレルギーなど身近なテーマが多かった)。身近なテーマが多いから文科生や専門的な知識を持っていない理科生でも理解しやすい。
■先進科学Ⅰα
①野口篤史
②金曜日2限
③総合E系列
④量子コンピュータを使うライセンスを東大からもらえて、実際に量子コンピュータを使って学習することができる。
【主題科目】
■医学に接する
①藤城光弘・東尚弘
②集中または水6または金6
③主題科目
④大学一年生で病院見学や医学部の研究室見学などをできる数少ない機会。科類に関わらず病院の中でいろいろなことを学べるのはとてもいい経験になると思う。
【最後に】
履修を組む際には、以下の記事も合わせてご覧ください!
・履修の入り口 第1章 〜基本用語〜
・履修の入り口 第2章 〜授業区分〜
・履修の入り口 第3章 〜授業の探し方〜
・履修の入り口 第4章-1 〜文科一類の履修〜
・履修の入り口 第4章-2 〜文科二類の履修〜
・履修の入り口 第4章-3 〜文科三類の履修〜
・履修の入り口 第4章-4 〜理科一類の履修〜
・履修の入り口 第4章-5 〜理科二・三類の履修〜
・履修の入り口 第5章 〜進学選択編〜
※この記事は、2024年度の情報に基づいて作成しています。年度によって曜日・担当教員が一部変更される可能性がありますのでご注意ください。校閲などを経て間違いがないように努めておりますが、もし間違いを発見した場合はそっとUT-BASEまで教えてください。